
Outlookのフォルダ整理術!大量メールの効率管理
Officeのお役立ち情報

記事の最終更新日:2025年7月11日
毎日、ものすごい数のメールが届いて、Outlookの受信トレイが、もはや手に負えない状態なんです。
プロジェクトごと、送信者ごとに、一生懸命フォルダ分けして整理しようと試みてはいるのですが、フォルダの数がどんどん増えていくだけで、結局、どのメールをどこに入れたか分からなくなってしまって。
メールをフォルダにドラッグして移動させる、という手作業に、一日の中で、かなりの時間を奪われている気もします。
この、情報の洪水から抜け出して、もっと効率的に、そしてストレスなく、大量のメールを管理するための、何かプロの技や、考え方のようなものは、ないのでしょうか?
そのお悩み、現代のビジネスパーソンが直面する、最も根深く、そして生産性を蝕む「病」とも言えます。
そして、その「病」の根本原因は、多くの方が陥る、「完璧なフォルダ分類」という名の、終わりのない幻想にあります。
プロフェッショナルのメール管理術は、その逆を行きます。
すなわち、「**分類(Sort)するな、検索(Search)せよ**」。
そして、「**手作業ではなく、ルール(Rule)に仕事をさせよ**」です。
あなたの仕事は、司書のように、全てのメールを、完璧な本棚に分類することではありません。
航空管制官のように、次々と舞い込んでくるメールを、瞬時に「処理」し、「仕分け」し、受信トレイという滑走路を、常に空(から)の状態に保つことなのです。
この記事では、そのための、シンプルかつ強力な「フォルダシステム」の設計思想から、Outlookの自動化機能である「仕訳ルール」と「クイック操作」の具体的な設定方法、そして、必要なメールを一瞬で見つけ出す「検索フォルダー」の活用術まで、あなたのメール業務を、苦役から、知的で、創造的な活動へと、変革するための、全ての知識と技術を解説します。
メール管理の哲学:受信トレイは「処理場」であり、「保管庫」ではない
まず、我々は、Outlookの受信トレイに対する、根本的な認識を改める必要があります。
受信トレイは、あなたのTo-Doリストでも、仕事のアーカイブ(保管庫)でもありません。
それは、外部から流れてくる、あらゆる種類の情報が、一時的に滞留する「荷捌き場」あるいは「処理プラント」です。
あなたの役割は、その荷捌き場に届いた荷物(メール)を、一つずつ、しかし迅速に手に取り、その場で、以下のいずれかの運命を決定することです。
- ・削除する(捨てる): 明らかに不要なメール。
- ・アーカイブする(保管する): 対応不要だが、記録として残しておくべきメール。
- ・対応する(処理する): 2分以内で返信や処理が終わるものなら、その場で対応し、アーカイブへ。
- ・委任する(転送する): 他の誰かが対応すべきものなら、転送し、「返信待ち」フォルダへ。
- ・後でやる(タスク化する): 2分以上かかる、複雑な対応が必要なメール。これを、後述する「アクション」フォルダや、ToDoリストへと転送する。
このプロセスを繰り返し、最終的に、受信トレイに一通のメールも残っていない状態、すなわち「**インボックス・ゼロ**」を目指します。
これにより、あなたは、「何か重要なメールを見落としているかもしれない」という、常に頭の片隅にこびりついている、精神的な重荷(認知的な負荷)から、完全に解放されるのです。
第一章:システムの設計 - シンプルで強力な「アクションベース」フォルダ構造
複雑な階層構造のフォルダは、作ることに満足してしまい、結果的に、分類の手間と、検索の困難さを増大させるだけの、罠となりがちです。
我々が目指すのは、日々の業務フローに直結した、ごく僅かで、しかし強力な、アクションベースのフォルダ構造です。
受信トレイの直下に、以下の4つの主要なフォルダを、この順番で作成することから始めましょう。
(フォルダ名の先頭に数字を付けるのは、フォルダの表示順を、意図通りに固定するためです)
- ・`01_Action`: 「後でやる」と判断した、対応が必要なメールを、一時的に格納する場所です。このフォルダにあるメールは、全て、あなた自身が、何らかのアクションを起こすべき「未完了タスク」であることを意味します。一日のうち、決まった時間に、このフォルダを集中して処理します。
- ・`02_Waiting For`: 他者に何かを依頼したり、返信を待っていたりする状態のメールを格納します。このフォルダを、週に一度など、定期的に見返すことで、「あの件、どうなったかな?」という、フォローアップの漏れを、確実に防ぐことができます。
- ・`03_Read/Review`: すぐに読む必要はないが、後で時間のある時に、ゆっくりと目を通したい、メールマガジンや、業界ニュース、社内の情報共有メールなどを、格納します。移動中や、休憩時間などに、このフォルダを消化します。
- ・`04_Archive`: 上記のいずれにも当てはまらない、全ての「対応済み」のメールを、ここに一括で放り込みます。プロジェクトごとや、送信者ごとに、細かく分類する必要は、一切ありません。なぜなら、我々は、Outlookの強力な検索機能を、完全に信頼するからです。
この、たった4つのフォルダが、あなたのメール管理システムの、揺るぎない土台となります。
第二章:自動化エンジンその1 - 「仕訳ルール」で、受信トレイを自動で整理する
「仕訳ルール」は、あなたが設定した条件に基づいて、受信したメールを、自動で、指定したフォルダに振り分けたり、分類したりしてくれる、Outlookの強力な自動化エンジンです。
これを使いこなすことで、そもそも、あなたの手作業を必要とするメールの数を、劇的に減らすことができます。
「ホーム」タブ > 「ルール」 > 「仕訳ルールの作成」から、新しいルールを作成します。
実践例1:CCメールの自動振り分け
日々のメールの中で、多くの場合、緊急性が低いのが、自分が「To」ではなく、「Cc」に入っているメールです。
これらのメールを、受信トレイを素通りさせて、直接「`03_Read/Review`」フォルダに格納するルールを作成しましょう。
「仕訳ルールの作成」ダイアログで、「詳細オプション」をクリックし、ルールウィザードを起動します。
- 【条件】ステップ1で、「[CC]に自分の名前がある場合」にチェックを入れます。
- 【処理】ステップ1で、「指定フォルダーへ移動する」と「開封済みにする」にチェックを入れます。
- 【処理】ステップ2で、下線部分をクリックし、移動先のフォルダとして「`03_Read/Review`」を選択します。
この、たった一つのルールを設定するだけで、あなたの受信トレイに届くメールの量は、体感で、3割から5割は、削減されるはずです。
実践例2:特定の送信者や件名を、自動で分類する
定期的に送られてくる、特定のメールマガジンや、特定のシステムからの定型的な通知メールも、受信トレイを埋め尽くす、主な原因です。
「差出人が〇〇の場合」や、「件名に特定の文字(例:「【メルマガ】」)が含まれる場合」といった条件で、それらのメールを、直接「`03_Read/Review`」や、専用のフォルダに振り分けるルールを作成しましょう。
第三章:自動化エンジンその2 - 「クイック操作」で、手動での処理を高速化する
「クイック操作」は、メールを手動で処理する際に、複数の操作を、一つのボタンに登録し、ワンクリックで実行できるようにする、もう一つの強力な自動化機能です。
「ホーム」タブにある「クイック操作」のギャラリーから、新しい操作を作成できます。
実践例1:最強の「処理完了」ボタンの作成
あなたが、あるメールへの対応を完了した時に行う、一連の操作を、一つのボタンにまとめます。
- 名前:「処理完了」
- アクション1:「開封済みにする」
- アクション2:「分類項目を“完了”に設定する」
- アクション3:「`04_Archive`フォルダーに移動する」
このボタンを作成しておけば、メールを処理した後、このボタンを押すだけで、そのメールは、あなたの視界(受信トレイ)から、完全に消え去り、適切に保管されます。
実践例2:「アクションアイテム化」ボタンの作成
対応に時間がかかるメールを、`01_Action`フォルダに格納するためのボタンです。
- 名前:「要対応」
- アクション1:「`01_Action`フォルダーに移動する」
- アクション2:「フラグを設定する」(フォローアップのフラグが付きます)
これらの、あなた自身のワークフローに合わせた、カスタムの「クイック操作」ボタンをいくつか用意しておくだけで、日々のメール処理の速度と、正確性は、飛躍的に向上します。
第四章:「探す」技術 - 検索フォルダと高度な検索クエリ
このシステムでは、対応済みのメールは、全て、一つの巨大な「`04_Archive`」フォルダに、集約されていきます。
「それでは、後から、特定のメールを探すのが大変ではないか?」
その心配は、一切不要です。
なぜなら、Outlookの検索機能は、あなたが、何千、何万というフォルダを、目で探すよりも、遥かに高速で、遥かに正確に、目的のメールを見つけ出してくれるからです。
高度な検索クエリの活用
Outlook上部の検索ボックスには、単なるキーワードだけでなく、特定の構文(クエリ)を入力することで、非常に高度な検索が可能です。
- 特定の送信者からのメール:`from:"山田太郎"`
- 特定の件名を持つメール:`subject:"会議のおしらせ"`
- 添付ファイル付きのメール:`hasattachments:yes`
- 特定の期間内のメール:`received:2024/01/01..2024/03/31`
これらのクエリは、「AND」「OR」「NOT」といった論理演算子で、組み合わせることも可能です。
「検索フォルダー」による、仮想的なビューの作成
これこそが、「分類しない」メール管理術の、真髄です。
「検索フォルダー」とは、物理的にメールを移動させることなく、特定の検索条件に合致するメールだけを、あたかも、一つのフォルダに入っているかのように、仮想的に表示してくれる、特殊なフォルダです。
フォルダ一覧で右クリックし、「新しい検索フォルダー」を選択します。
ここには、「未読のメール」や「フラグが設定されたメール」といった、定義済みのテンプレートのほか、あなた自身で、自由な条件の検索フォルダーを作成できます。
例えば、以下のような、非常に便利な検索フォルダーを作成しておくと良いでしょう。
- 「上司からのメール」検索フォルダー: `from:"上司の名前"` という条件で作成します。
- 「添付ファイル付き(未処理)」検索フォルダー: `hasattachments:yes` かつ `folder:"受信トレイ"` といった条件で作成します。
- 「プロジェクトX関連」検索フォルダー: `subject:"[ProjectX]"` OR `body:"プロジェクトX"` といった、件名や本文に、特定のキーワードを含むメールを、横断的に表示させます。
これにより、あなたは、メールを物理的に一つのフォルダにしか置けない、という制約から解放され、「送信者」という切り口、「プロジェクト」という切り口、「添付ファイルの有無」という切り口、といったように、一つのメールを、複数の、仮想的な視点から、いつでも確認できるようになるのです。
まとめ:メール管理とは、あなたの「意思決定の訓練」である
Outlookのフォルダを整理する技術とは、最終的に、あなたの「意思決定」の質と、速度を高めるための、自己訓練のプロセスです。
受信トレイに届いた、一通一通のメールに対して、「これは何か?」「それは、私にとって重要か?」「次にとるべき、具体的なアクションは何か?」という問いを、瞬時に投げかけ、判断を下していく。
その訓練の先に、情報の洪水に溺れることのない、静かで、整然とした、知的生産のための、理想的な環境が待っています。
- ・受信トレイを「聖域」として扱う: そこは、未処理の案件だけが存在する、常に空(ゼロ)を目指すべき場所。この思想が、全ての出発点です。
- ・シンプルな「アクションベース」フォルダを設計する: 複雑な階層はやめ、「要対応」「返信待ち」といった、次にとるべき行動に基づいた、ごく少数のフォルダで、システムを運用する。
- ・「仕訳ルール」と「クイック操作」に、雑務を委任する: あなたが手作業で行っている、全ての定型的な振り分けや、処理のプロセスは、Outlookの自動化機能に、完全に任せてしまいましょう。
- ・「検索フォルダー」で、複数の「視点」を持つ: 物理的な分類の限界を、「検索フォルダー」という、仮想的な分類で乗り越える。これにより、あなたは、あらゆる角度から、あなたの情報資産に、自在にアクセスできるようになります。
もう、受信トレイの未読件数に、怯える必要はありません。
この記事で解説した、体系的なアプローチを実践し、Outlookを、あなたという指揮官の意のままに働く、有能な「情報処理システム」へと、変貌させてください。

パソコン購入のためのお役立ち情報
パソコン選びがよく分からない方、ご不安のある方、悩む前に!お気軽にご相談ください!
専門スタッフが、性能・ご予算・お好みなどご希望に合ったパソコンをお探しします!



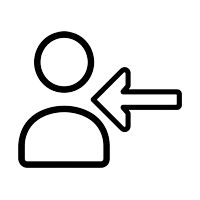 ログイン
ログイン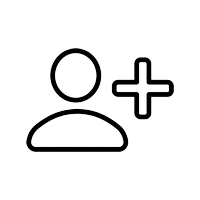 新しくアカウントを作成する
新しくアカウントを作成する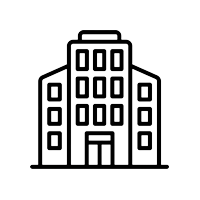 会社概要
会社概要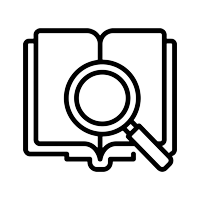 ご利用ガイド
ご利用ガイド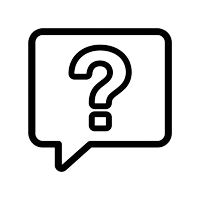 よくあるご質問
よくあるご質問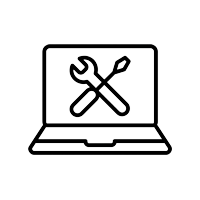 パソコン修理
パソコン修理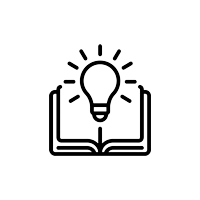 お役立ち情報
お役立ち情報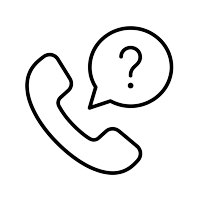 お問い合わせ
お問い合わせ 特定商取引に基づく表示
特定商取引に基づく表示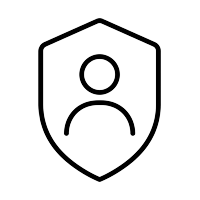 個人情報保護ポリシー
個人情報保護ポリシー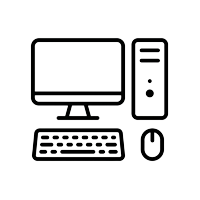 デスクトップパソコン
デスクトップパソコン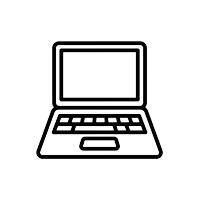 ノートパソコン
ノートパソコン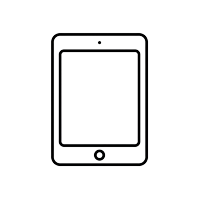 タブレット
タブレット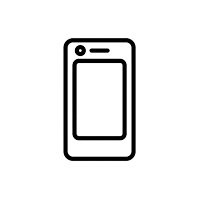 スマートフォン
スマートフォン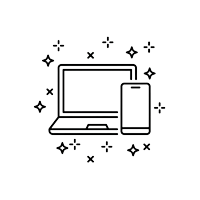 新品(Aランク)
新品(Aランク)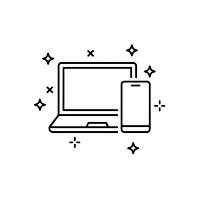 美品(Bランク)
美品(Bランク)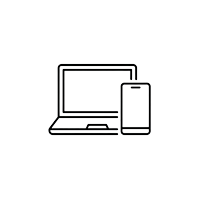 中古(Cランク)
中古(Cランク)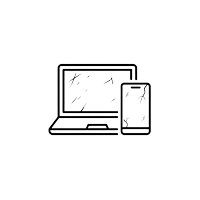 訳あり(Dランク)
訳あり(Dランク)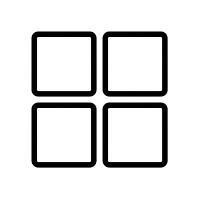 Windows 11
Windows 11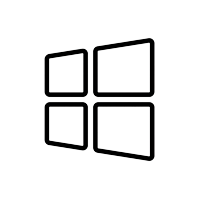 Windows 10
Windows 10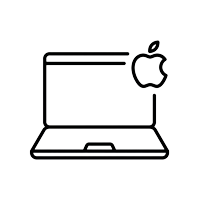 Mac OS
Mac OS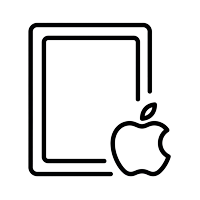 iPad OS
iPad OS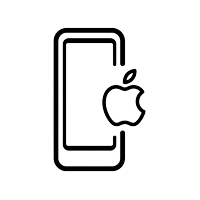 iOS
iOS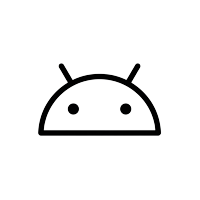 Android
Android コンシューマーモデル
コンシューマーモデル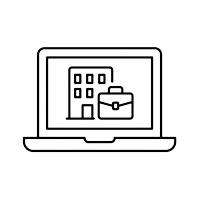 ビジネスモデル
ビジネスモデル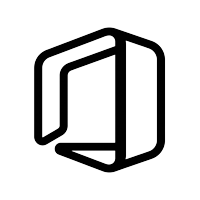 Microsoft Office搭載
Microsoft Office搭載 WPS Office搭載
WPS Office搭載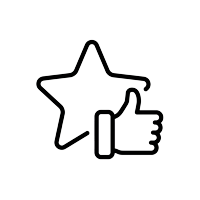 おすすめ商品
おすすめ商品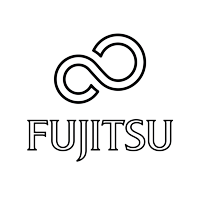
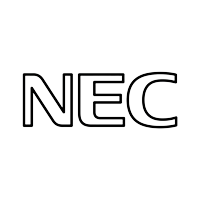
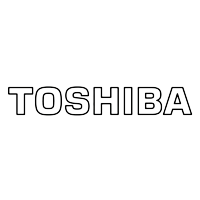


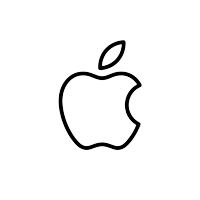


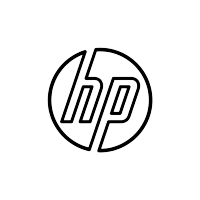
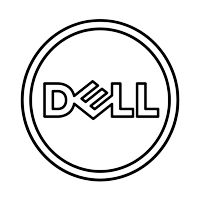

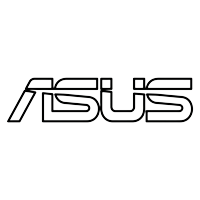
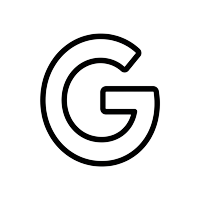

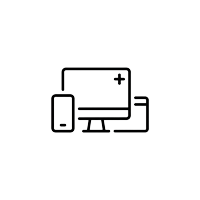
 Celeron|Athlon
Celeron|Athlon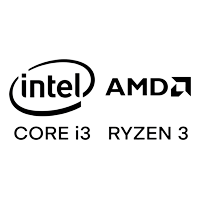 Core i3|Ryzen 3
Core i3|Ryzen 3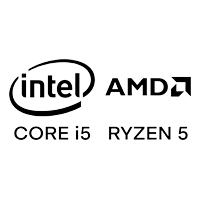 Core i5|Ryzen 5
Core i5|Ryzen 5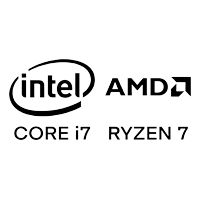 Core i7|Ryzen 7
Core i7|Ryzen 7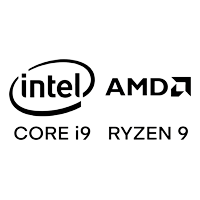 Core i9|Ryzen 9
Core i9|Ryzen 9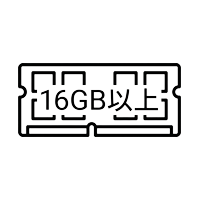 メモリ16GB以上
メモリ16GB以上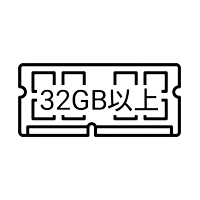 メモリ32GB以上
メモリ32GB以上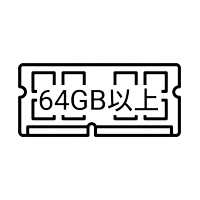 メモリ64GB以上
メモリ64GB以上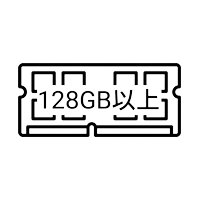 メモリ128GB以上
メモリ128GB以上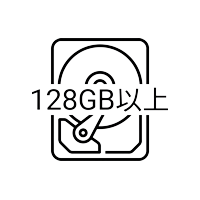 ストレージ128GB以上
ストレージ128GB以上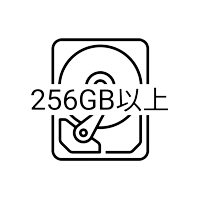 ストレージ256GB以上
ストレージ256GB以上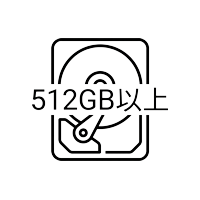 ストレージ512GB以上
ストレージ512GB以上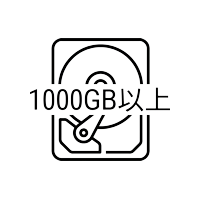 ストレージ1000GB以上
ストレージ1000GB以上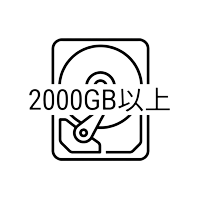 ストレージ2000GB以上
ストレージ2000GB以上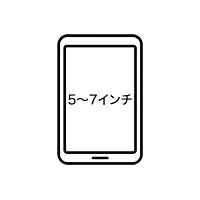 5〜7インチ
5〜7インチ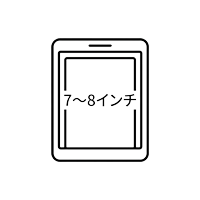 7〜8インチ
7〜8インチ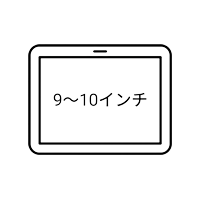 9〜10インチ
9〜10インチ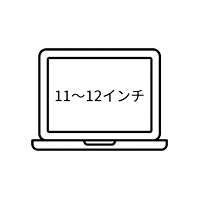 11〜12インチ
11〜12インチ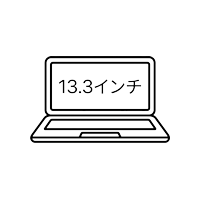 13.3インチ
13.3インチ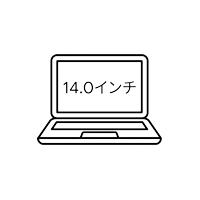 14.0インチ
14.0インチ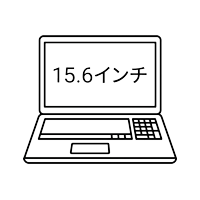 15.6インチ
15.6インチ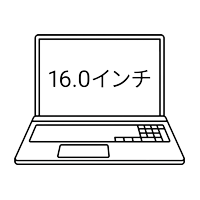 16.0インチ
16.0インチ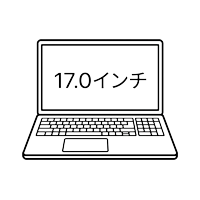 17.0インチ以上
17.0インチ以上




