
中古パソコンの売却時に知っておくべきデータ消去の手順
パソコン全般のお役立ち情報

記事の最終更新日:2025年7月10日
使わなくなったノートパソコンを、フリマアプリで売ろうと思っているんです。
もちろん、売る前にOSの初期化機能を使って「PCをリセット」はしたのですが、本当にこれで大丈夫なのか、すごく不安で…。
友人や家族の写真、仕事のファイル、保存していたパスワードなんかが、もし特殊なソフトで復元されてしまったら、と考えると、怖くて出品できません。
次の持ち主が、どんな人であっても絶対に安心なように、私の個人情報を、復元不可能なレベルまで、完全に消し去るための、プロが実践するような確実な方法はありませんか?
その懸念、デジタル社会における、最高レベルのセキュリティ意識です。
素晴らしいですね。
おっしゃる通り、PCの「初期化」や「リセット」という言葉の響きとは裏腹に、それだけではデータは完全には消去されていません。
それは、機密文書をゴミ箱に捨てるようなもので、本気で探せば、中身を取り出せてしまうのです。
真のデータ消去とは、文書をシュレッダーにかけるように、データの痕跡そのものを、物理的・論理的に破壊し尽くす「データマニピュレーション(破壊・無価値化)」のプロセスを指します。
そして、その正しい方法は、お使いのPCのストレージが、旧来の「HDD」か、現代的な「SSD」かによって、全く異なります。
この記事では、そのストレージの物理的な仕組みの違いから説き起こし、それぞれの媒体に最適化された、軍事レベルのデータ消去技術、そしてOSに標準で搭載されたツールの正しい使い方まで、あなたのプライバシーを未来永劫守り抜くための、完全な知識体系を授けます。
データ消去の原則:それは「削除」ではなく「破壊」である
パソコンのデータ消去について語る時、私たちがまず理解すべき、最も重要な原則があります。
それは、あなたがファイルを選択して「削除」し、ゴミ箱を空にしたとしても、そのデータは、ストレージ上から即座に消えているわけではない、という事実です。
OSが行っているのは、そのデータが占めていた領域を、「ここはもう空いているので、新しいデータを上書きしても良いですよ」という印(フラグ)を立てる管理情報の更新に過ぎません。
データの本体は、新しいデータが上書きされるまでの間、ストレージ上に「データ残存性(Data remanence)」として、幽霊のように存在し続けているのです。
専門的なデータ復元ソフトは、OSの管理情報を無視し、ストレージを直接スキャンすることで、この幽霊のようなデータの痕跡を読み取り、ファイルを復元することができてしまいます。
したがって、PCを第三者に譲渡する際のデータ消去とは、この痕跡自体を、復元不可能なレベルまで、意図的に、そして完全に破壊する行為でなければならないのです。
第一章:運命の分岐点 - HDDとSSD、全く異なるデータ消去の哲学
現代のPCに搭載されているストレージは、大きく分けてHDD(ハードディスクドライブ)とSSD(ソリッドステートドライブ)の二種類があります。
この二つは、データの記録方式が物理的に全く異なるため、安全なデータ消去の方法も、根本的に異なります。
間違った方法を適用すれば、データが消しきれないばかりか、SSDの場合はその寿命を縮めてしまうことさえあります。
【HDDの場合】物理的な磁気記録を「上書き」で塗り潰す
HDDは、プラッタと呼ばれる磁性体を塗布した円盤を高速で回転させ、磁気ヘッドを動かして、磁気のNSパターンとしてデータを記録します。
この磁気パターンを完全に破壊するためには、意味のない別のデータ(例えば、全ての領域を「0」で埋める、あるいはランダムなデータで埋める)を、ディスクの全領域にわたって、複数回「上書き」する必要があります。
この上書き処理には、その信頼性のレベルに応じて、いくつかの世界的な標準方式が存在します。
- ・ゼロフィル(Zero-Fill): ディスクの全領域を「0」のデータで1回上書きします。一般的なデータ復元ソフトでは、これだけでも復元はほぼ不可能となり、個人利用では十分なレベルと言えます。
- ・米国国防総省準拠方式(DoD 5220.22-M): 「0」で上書きし、次に「1」で上書きし、最後にランダムなデータで上書きする、といった3回以上の書き込みを行います。政府機関や企業で、機密データを廃棄する際に用いられる、非常に信頼性の高い消去方式です。
- ・グートマン方式(Gutmann method): 35回にもわたって、様々なデータパターンで上書きを行う、現存する最も強力な上書き消去方式の一つです。現代のHDDに対しては過剰とも言えますが、データ消去の原理を示す象徴的な存在です。
これらの処理を実行するには、DBANやParted Magicといった、USBメモリなどからPCを起動して使用する、専門のブータブル消去ツールを利用するのが一般的です。
【SSDの場合】「上書き」は無意味かつ有害。「Secure Erase」こそが唯一の正解
一方、SSDは、NANDフラッシュメモリと呼ばれる半導体チップに、電気的にデータを記録します。
SSDには、特定のメモリセルに書き込みが集中して摩耗するのを防ぐため、「ウェアレベリング」という、書き込み位置を常に分散させる、極めて高度な制御が内部コントローラーによって行われています。
このため、OSから「この場所に上書きしろ」という命令を送っても、SSDのコントローラーは、別の空いているセルに新しいデータを書き込み、元のデータが記録されたセルは、後で消去する候補として残してしまうのです。
つまり、**SSDに対して、HDDと同じ上書き消去をいくら繰り返しても、元のデータが消去されたという保証は全くなく、ただSSDの寿命を無駄に削っているだけ**、という最悪の結果を招きます。
SSDのデータを、正しく、安全に、そして瞬時に消去するための、唯一の正しい方法。
それが、SSDのファームウェア自体に搭載されている、**「Secure Erase(セキュア消去)」**というコマンドです。
これは、SSDのコントローラーに対して、「全てのメモリセルの電荷をリセットせよ」と直接命令する、いわば「工場出荷状態への強制初期化」コマンドです。
これにより、全てのデータは復元不可能な状態になり、SSDは新品同様のパフォーマンスを取り戻します。
NVMe規格のSSDでは、さらに強力な「Sanitize」といったコマンドも用意されています。
これらのコマンドは、多くの場合、PCのBIOS/UEFI画面や、SSDメーカーが提供する専用の管理ツール(例:Samsung Magicianなど)から実行することができます。
また、後述するOSの初期化機能も、SSDに対してはこのSecure Erase(あるいはそれに準ずるTRIMコマンド)を呼び出すように設計されています。
第二章:OS標準ツールの活用 - WindowsとmacOSの正しい初期化手順
専門ツールを使うのはハードルが高い、と感じる方も多いでしょう。
幸い、現代のOSには、これらのストレージの違いを理解し、適切な処理を自動で行ってくれる、非常に賢い初期化機能が備わっています。
Windows 11:「このPCをリセット」と「ドライブのクリーニング」
Windows 11でPCを初期化する場合、「設定」>「システム」>「回復」から、「このPCをリセット」を実行します。
売却が目的ですので、必ず「**すべてを削除する**」を選択してください。
次の「設定の変更」画面で、最も重要な選択肢が現れます。
それが、「**ドライブのクリーニングを実行しますか?**」という質問です。
ここで「はい」を選ぶことで、単なるファイルの削除ではなく、データの痕跡を積極的に消去する処理が行われます。
Windows 11は、この際にストレージの種類を自動で判別し、HDDであれば前述の「ゼロフィル」を、SSDであれば「TRIM」コマンドの発行(Secure Eraseに準ずる処理)を、それぞれ実行してくれます。
処理には数時間を要しますが、あなたのプライバシーを守るためには、絶対にスキップしてはならないステップです。
macOS:「すべてのコンテンツと設定を消去」による暗号化消去
近年のMacは、内蔵ストレージが標準で、強力に暗号化されています。
この特性を利用した、極めて安全かつ高速な消去方法が、macOS Monterey以降に搭載された「すべてのコンテンツと設定を消去」機能です。
これは、iPhoneやiPadの初期化と同じ仕組みで、データそのものを一つ一つ上書きするのではなく、その**データの暗号化に使用した「鍵」を、破壊してしまう**のです。
鍵を失った暗号データは、もはや意味のない、ただのランダムな情報の羅列となり、復元は原理的に不可能となります。
この「暗号化消去(Cryptographic Erase)」は、処理が一瞬で終わるという、大きなメリットもあります。
「システム設定」>「一般」>「転送またはリセット」から、この機能を実行できます。
第三章:最後の砦 - 物理的破壊という選択肢
PCが故障しており、ソフトウェア的なデータ消去が実行できない場合や、国家機密レベルの、極めて重要な情報を扱っていた場合など、いかなるリスクも許容できない状況では、最終手段として、ストレージの「物理的破壊」を選択することになります。
HDDであれば、プラッタにドリルで複数の穴を開けたり、強力な磁石(ネオジム磁石など)で磁気データを破壊(デガウス)したりする方法があります。
SSDの場合は、内蔵されているNANDフラッシュメモリチップそのものを、ハンマーで粉砕する、といった方法が考えられます。
より確実を期すのであれば、専門のデータ破壊サービス業者に依頼し、ストレージを物理的にシュレッダーにかけてもらうのが、最も安全な方法です。
第四章:消去前の最終確認 - デジタルな足跡を消す
ストレージのデータを消去する前に、各種ウェブサービスとの紐付けを解除しておくことも、忘れてはならない重要なステップです。
- ・各種アカウントからのサインアウト: Microsoftアカウント、Googleアカウント、iCloudといった、OSに紐付いているアカウントからは、必ずサインアウトしておきます。
- ・ソフトウェアのライセンス認証解除: Microsoft Officeや、Adobe Creative Cloudといった、特定のPCにライセンスが紐付いているソフトウェアは、次のPCで利用するために、必ず認証解除の手続きを行ってください。
- ・デバイス登録の解除: GoogleやApple、Microsoftなどのアカウント管理ページにアクセスし、「信頼できるデバイス」の一覧から、売却するPCを削除しておきましょう。
そして、何よりも重要なのが、**全ての必要なデータのバックアップ**を、これらの消去プロセスを開始する前に、必ず完了させておくことです。
まとめ:データ消去とは、あなたのデジタルな過去に対する「責任」である
中古パソコンを安心して手放すためのデータ消去は、正しい知識と、適切な手順、そして何よりも、自身のプライバシーに対する強い責任感によって成り立っています。
そのプロセスは、もはや単なるITスキルではなく、デジタル社会を生きる上での、必須の教養と言えるでしょう。
- ・ストレージの種類を見極める: あなたのPCのストレージは、HDDか、SSDか。この問いへの答えが、正しいデータ消去方法を選択するための、全ての出発点です。
- ・HDDは「上書き」、SSDは「Secure Erase」: HDDには、DoD準拠方式などの複数回の上書きが有効。SSDには、それは有害無益であり、Secure Eraseコマンド(またはそれに準ずるOSの機能)が唯一の正解です。
- ・OSの標準機能を信頼し、正しく使う: Windows 11の「ドライブのクリーニング」や、macOSの「すべてのコンテンツと設定を消去」は、現代のストレージに最適化された、非常に信頼性の高い消去機能です。売却の際は、必ずこれらのオプションを利用してください。
- ・消去前の「足跡消し」を忘れない: ストレージを破壊する前に、各種アカウントの紐付けを解除し、バックアップを完璧に取得しておくこと。これが、スムーズで安全な売却プロセスの最後の仕上げです。
あなたの個人情報は、一度流出してしまえば、二度と取り戻すことはできません。
この記事で得た知識を武器に、あなたのデジタルな過去と、そして未来のプライバシーを、あなた自身の力で、完璧に守り抜いてください。

パソコン購入のためのお役立ち情報
パソコン選びがよく分からない方、ご不安のある方、悩む前に!お気軽にご相談ください!
専門スタッフが、性能・ご予算・お好みなどご希望に合ったパソコンをお探しします!



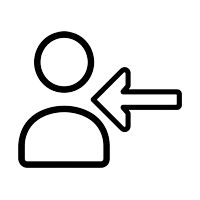 ログイン
ログイン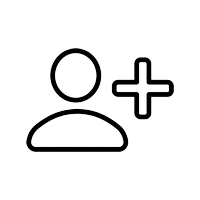 新しくアカウントを作成する
新しくアカウントを作成する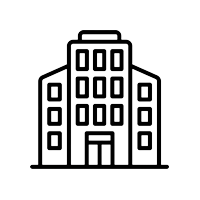 会社概要
会社概要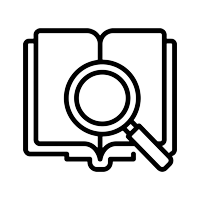 ご利用ガイド
ご利用ガイド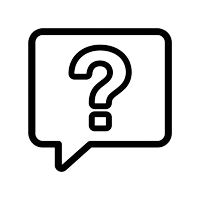 よくあるご質問
よくあるご質問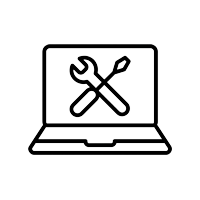 パソコン修理
パソコン修理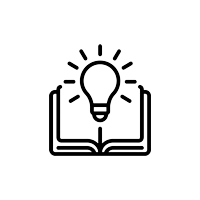 お役立ち情報
お役立ち情報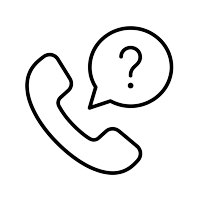 お問い合わせ
お問い合わせ 特定商取引に基づく表示
特定商取引に基づく表示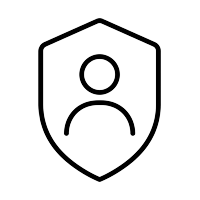 個人情報保護ポリシー
個人情報保護ポリシー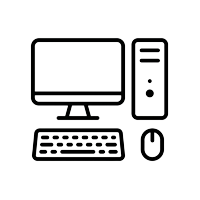 デスクトップパソコン
デスクトップパソコン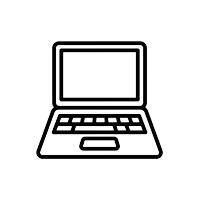 ノートパソコン
ノートパソコン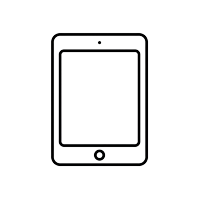 タブレット
タブレット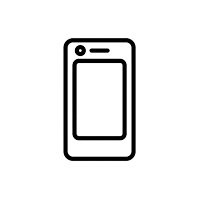 スマートフォン
スマートフォン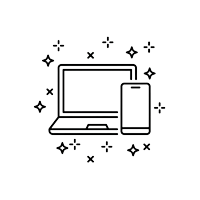 新品(Aランク)
新品(Aランク)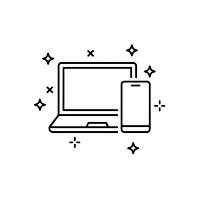 美品(Bランク)
美品(Bランク)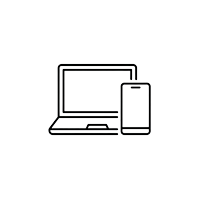 中古(Cランク)
中古(Cランク)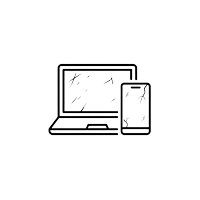 訳あり(Dランク)
訳あり(Dランク)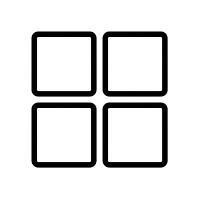 Windows 11
Windows 11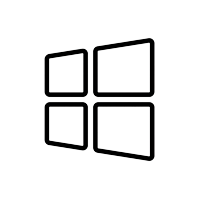 Windows 10
Windows 10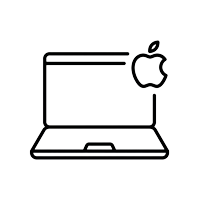 Mac OS
Mac OS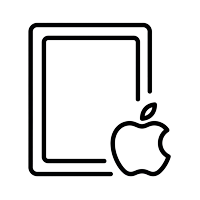 iPad OS
iPad OS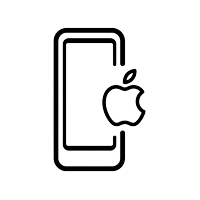 iOS
iOS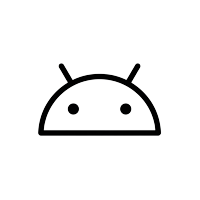 Android
Android コンシューマーモデル
コンシューマーモデル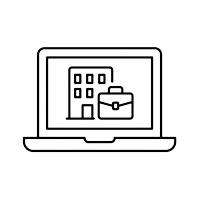 ビジネスモデル
ビジネスモデル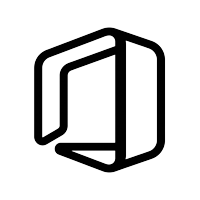 Microsoft Office搭載
Microsoft Office搭載 WPS Office搭載
WPS Office搭載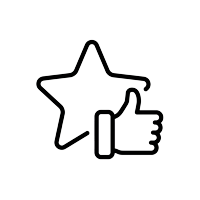 おすすめ商品
おすすめ商品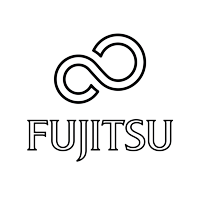
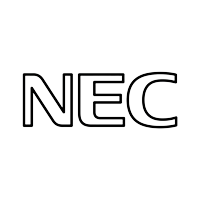
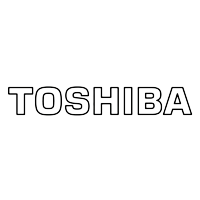


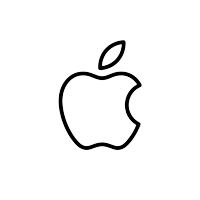


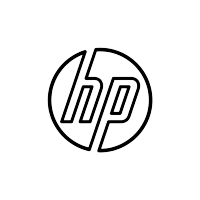
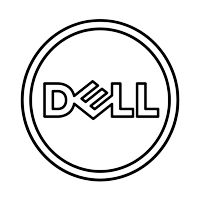

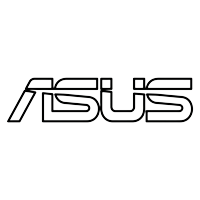
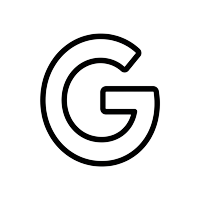

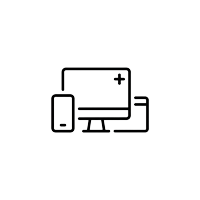
 Celeron|Athlon
Celeron|Athlon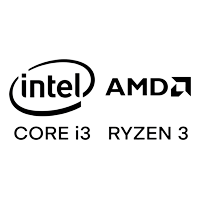 Core i3|Ryzen 3
Core i3|Ryzen 3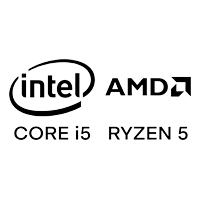 Core i5|Ryzen 5
Core i5|Ryzen 5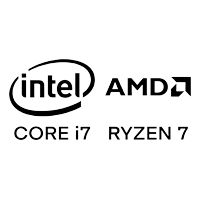 Core i7|Ryzen 7
Core i7|Ryzen 7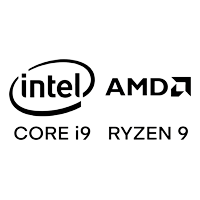 Core i9|Ryzen 9
Core i9|Ryzen 9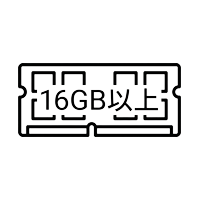 メモリ16GB以上
メモリ16GB以上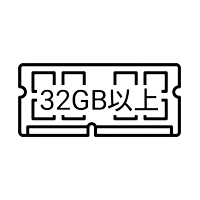 メモリ32GB以上
メモリ32GB以上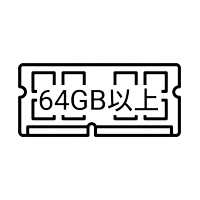 メモリ64GB以上
メモリ64GB以上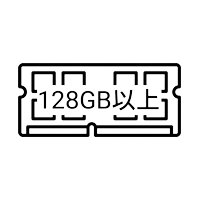 メモリ128GB以上
メモリ128GB以上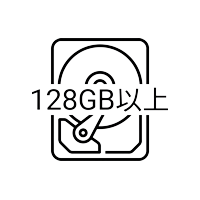 ストレージ128GB以上
ストレージ128GB以上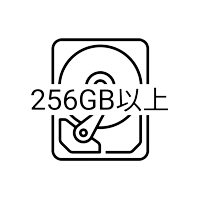 ストレージ256GB以上
ストレージ256GB以上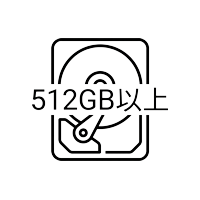 ストレージ512GB以上
ストレージ512GB以上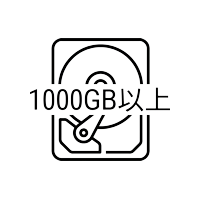 ストレージ1000GB以上
ストレージ1000GB以上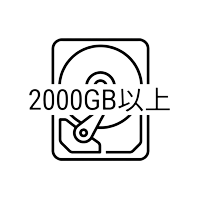 ストレージ2000GB以上
ストレージ2000GB以上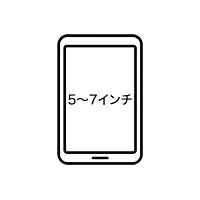 5〜7インチ
5〜7インチ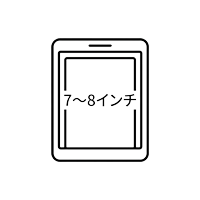 7〜8インチ
7〜8インチ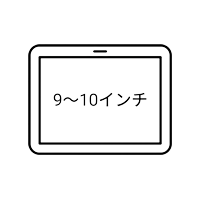 9〜10インチ
9〜10インチ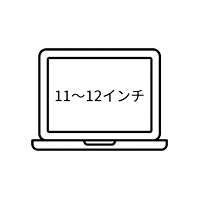 11〜12インチ
11〜12インチ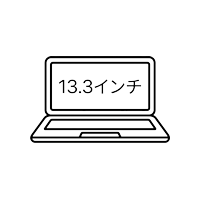 13.3インチ
13.3インチ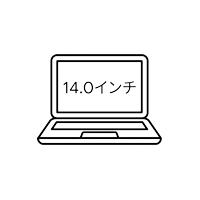 14.0インチ
14.0インチ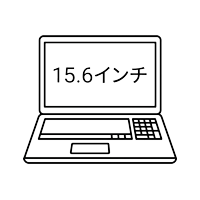 15.6インチ
15.6インチ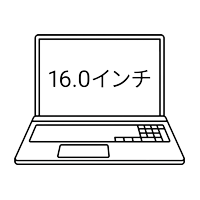 16.0インチ
16.0インチ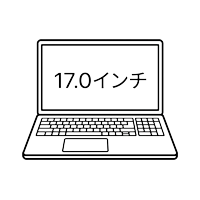 17.0インチ以上
17.0インチ以上




