
中古パソコンと互換性のある周辺機器の選び方
パソコン全般のお役立ち情報

記事の最終更新日:2025年7月10日
在宅ワーク用に、性能の良い中古デスクトップPCをお店で選んでもらったんです。
次は、作業がしやすくなるように、大きなモニターや、使いやすいワイヤレスキーボード、高画質なウェブカメラを買い足したいなと思っています。
でも、最新の周辺機器が、この中古パソコンでちゃんと動くのか、すごく不安で…。
パソコンの裏側にある接続ポート(端子)も、色々な形があって、どれとどれを繋げばいいのか分かりません。
せっかく買ったのに「接続できなかった」とか「本来の性能が出なかった」なんてことになったら、悲しいです。
中古パソコンの能力を最大限に引き出すための、周辺機器選びのポイントを、専門家の視点から教えてください。
その視点、素晴らしいです。
周辺機器は、パソコンという「頭脳」の能力を、私たちの五感や作業空間へと拡張するための、極めて重要な「手足」です。
そして、中古パソコンにおける周辺機器選びの極意は、いわば「インターフェースの考古学」。
PC側が話せる「古い言語(規格)」と、新しい周辺機器が話す「現代の言語(規格)」を、正しく通訳し、繋ぎ合わせる技術にあります。
重要なのは、「動くかどうか」だけでなく、「その周辺機器が持つ最高のパフォーマンスを、中古PCがボトルネックになることなく引き出せるか」を見極めることです。
この記事では、モニター、キーボード、オーディオ、ストレージといった主要な周辺機器ごとに、まずあなたのPCの「能力」を鑑定する方法から始め、次に、その能力に最適な製品を選ぶための基準、そしてそれらを正しく接続するための、プロフェッショナルな知識と具体的な手順を、体系的に解説していきます。
最高の「手足」を与えて、あなただけの中古PCシステムを完成させましょう。
周辺機器選びの哲学:システムは「最も弱い環」の速度で動く
PCと周辺機器で構成されるシステム全体のパフォーマンスは、その中で最も性能の低い部分、すなわち「ボトルネック」によって決定づされます。
例えば、F1カーのような超高速な外付けSSDを購入したとしても、それを、一車線の田舎道のような、古いUSB 2.0ポートに接続してしまえば、データの転送速度は、田舎道の制限速度まで落ちてしまいます。
逆に、4K解像度という広大な情報量を表示できる最新のモニターを持っていても、PC側の映像出力能力がそれに追いついていなければ、その美しいキャンバスに絵を描くことはできません。
したがって、中古パソコンにおける周辺機器選びとは、単に欲しい機能を持つ製品を選ぶだけでなく、まず、あなたのPCという「母艦」が持つ、各ポートや内部コンポーネントの「限界性能」を正確に把握し、その性能を最大限に活かせる、あるいは、その性能で十分に機能する、バランスの取れた製品を選択する、という高度なマッチング作業なのです。
この思想を持つことが、無駄な出費を避け、満足度の高いPC環境を構築するための、最も重要な羅針盤となります。
第一章:視覚世界の拡張 - モニターの互換性と性能を最大限に引き出す
モニターは、PCの出力を我々が認識するための、最も重要なインターフェースです。
中古PCで、特に高解像度モニターを利用する場合には、入念な事前調査が不可欠です。
ステップ1:PC側の映像出力ポートを鑑定する
まず、お使いの中古PCの背面や側面にある、映像出力ポートの種類を正確に識別します。
中古PCでは、しばしば古い規格と新しい規格のポートが混在しています。
- ・VGA(D-Sub15ピン): 青色の台形のアナログポート。画質の劣化が避けられないため、他の選択肢がない場合の最終手段と考えましょう。
- ・DVI: 白色の大きなポート。デジタル専用のDVI-Dと、アナログも出力できるDVI-Iがあります。HDMIへの変換は容易ですが、音声は伝送されません。
- ・HDMI: 最も一般的なポート。ただし、中古PCに搭載されている場合、そのバージョンに注意が必要です。4K解像度を、滑らかな60Hzのリフレッシュレートで表示するには、**HDMI 2.0**以上の規格に対応している必要があります。古いHDMI 1.4では、4K表示はできても、30Hzに制限されてしまい、マウスカーソルの動きなどがカクカクして見えます。
- ・DisplayPort (DP): HDMIと並ぶ、高機能なデジタルポート。古いバージョンでも比較的高解像度・高リフレッシュレートに対応しており、中古PCで高解像度モニターを活かすための、信頼性の高い選択肢です。
ステップ2:PCのグラフィック能力を把握する
接続できるモニターの最大数や、最大解像度は、PCのグラフィック機能(GPU)によって決まります。
「デバイスマネージャー」の「ディスプレイアダプター」の項目で、搭載されているGPUのモデル名を確認し、その仕様をインターネットで検索することで、「最大解像度」や「マルチモニターサポート数」を知ることができます。
ここで重要な専門的テクニックとして、多くのデスクトップPCでは、BIOS/UEFI設定で、CPU内蔵グラフィックス(iGPU)と、増設されたグラフィックボード(dGPU)の、両方を同時に有効化する「IGPU Multi-Monitor」のような設定が可能です。
これを有効にすれば、例えばグラボから2画面、マザーボードから1画面、といった合計3画面出力も可能になり、中古PCの潜在能力を限界まで引き出すことができます。
ステップ3:ケーブルとアダプターを正しく選ぶ
PC側のポートと、新しいモニター側のポートが異なる場合、変換アダプターや変換ケーブルが必要になります。
ここで注意すべきは、変換には「方向性」がある、ということです。
例えば、「PC側(出力)がDisplayPort、モニター側(入力)がHDMI」という場合に使うべきは、「DisplayPort to HDMI」変換アダプターであり、その逆の「HDMI to DisplayPort」アダプターでは、映像は映りません。
また、4K/60Hzのような高帯域な信号を扱う場合は、アダプター自体もその信号に対応している、「アクティブタイプ」と呼ばれる、電力供給を必要とする高性能なものが必要になる場合があります。
第二章:触れる世界の最適化 - キーボードとマウスの接続方式
キーボードやマウスといった入力デバイスは、接続の確実性と、ワイヤレスの利便性のトレードオフを考えて選択します。
有線か、無線か、Bluetoothか
- ・有線接続(USB-A): 最も確実で、設定も不要な、プラグ&プレイの接続方式です。遅延やバッテリー切れの心配も一切ありません。中古PCのUSBポート(通常は黒色のUSB 2.0で十分)に接続するだけで、即座に利用できます。
- ・2.4GHzワイヤレス接続: レシーバー(受信機)となる小さなUSBドングルをPCに接続する方式です。Bluetoothに比べて接続が安定しており、遅延も少ないため、ゲーミング用途などでも広く使われています。ただし、貴重なUSBポートを一つ占有するのがデメリットです。
- ・Bluetooth接続: PC本体にBluetooth機能が内蔵されている場合(近年のノートPCはほぼ全て、デスクトップPCはモデルによる)に利用できます。USBポートを消費しないのが最大のメリットですが、PCの起動時(BIOS/UEFI画面)には認識されない、あるいは、まれに接続が不安定になることがある、といったデメリットも存在します。
中古PCのUSBポートの数や、Bluetooth機能の有無を確認し、ご自身の使い方(安定性重視か、携帯性・省ポート性重視か)に合わせて、最適な接続方式を選びましょう。
第三章:音の世界のアップグレード - オーディオデバイスの選択
中古PC、特にビジネス向けのモデルでは、内蔵のオーディオ機能が、必ずしも高品質ではない場合があります。
しかし、USB接続のデバイスを活用することで、これを劇的に改善できます。
PCの3.5mmイヤホンジャックは、PC内部の電気的なノイズ(雑音)を拾いやすく、音質の劣化の原因となることがあります。
そこで推奨されるのが、**USBヘッドセット**や、**USB-DAC**(ダック、※注釈:Digital-to-Analog Converter。デジタル音声信号を、人間が聞くことのできるアナログ信号に変換する、高品質な外付けサウンドカードのような装置)の利用です。
これらのUSBオーディオデバイスは、PC内部のオーディオ回路を完全にバイパスし、デバイスに内蔵された、より高品質な回路で音声処理を行います。
これにより、中古PCの元々のオーディオ性能に関わらず、クリアでノイズの少ない、高品位なサウンドを手に入れることができるのです。
これは、オンライン会議での明瞭な音声コミュニケーションや、音楽・映画鑑賞の質を向上させるための、非常に効果的なアップグレードです。
第四章:データ倉庫の拡張 - 外付けストレージの性能を最大限に活かす
外付けのSSDやHDDを接続する際、その転送速度は、PC側のUSBポートの「世代」によって、厳しく制限されます。
中古PCのUSBポートの仕様を正確に把握することが、ここでも重要になります。
ポートの色で見分けるのが、一つの簡単な目安です。
- ・USB 2.0(黒色): 転送速度は最大480Mbps。写真や文書といった、比較的小さなファイルのバックアップには十分ですが、大容量の動画ファイルや、高速な外付けSSDの性能を活かすには、明らかに力不足です。
- ・USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1(青色): 転送速度は最大5Gbps(5,000Mbps)。USB 2.0の約10倍の速度を誇り、外付けSSDの性能を、ある程度引き出すことができます。2025年現在、中古PCで快適な外付けストレージを利用するための、実用的な最低ラインと言えるでしょう。
- ・USB 3.1 Gen 2 / 3.2 Gen 2(赤色や水色): 転送速度は最大10Gbps。より高性能な外付けSSDの速度を、さらに活かすことができます。比較的新しいモデルの中古PCに搭載されていることがあります。
最新の高速な外付けSSDを購入しても、それをUSB 2.0ポートに接続してしまえば、その速度はUSB 2.0の上限に抑えられてしまいます。
あなたのPCが持つ、最も高速なUSBポートがどれなのかを事前に確認し、そこに、速度に見合った性能を持つ外付けストレージを接続する。
これが、ボトルネックを生まないための、賢い選択です。
第五章:最後の確認事項 - ドライバーと専用ソフトウェア
現代の周辺機器の多くは、OSに内蔵された標準ドライバーで動作する、プラグ&プレイに対応しています。
しかし、ゲーミングマウスのボタンカスタマイズ機能や、高機能ウェブカメラの色調整機能といった、その製品が持つ全てのポテンシャルを引き出すためには、多くの場合、メーカーの公式サイトから、専用のソフトウェアや、最新のドライバーをダウンロードし、インストールする必要があります。
新しい周辺機器を接続して、基本的な動作は確認できたとしても、一度、その製品のメーカー名と型番で検索し、専用のソフトウェアが提供されていないかを確認する習慣をつけることで、あなたが購入した製品の、隠された能力を、余すところなく活用することができるようになります。
まとめ:中古PCの周辺機器選びとは、知識による「価値の再創造」である
中古パソコンは、それ単体では、過去の性能を持つ、ただの機械かもしれません。
しかし、現代の高性能な周辺機器と、それを正しく接続・設定するための「知識」が組み合わさる時、その価値は再創造され、最新のPCにも劣らない、あなただけの、そしてあなたに最適化された、強力なワークステーションへと生まれ変わります。
- ・PCの「ポート構成」こそが、拡張性の設計図である: まず、あなたのPCが、どのような種類の、そしてどのバージョンのポートを持っているのかを、探偵のように鑑定すること。これが、全ての始まりです。
- ・モニター選びは「GPUの能力」と「ポートの規格」で決まる: 4K/60Hzという現代的な快適性を求めるなら、PC側のGPUとポートが、HDMI 2.0以上に対応しているかが、絶対的な判断基準となります。
- ・音質に不満なら「USBオーディオ」という特効薬を: PC本体のオーディオ回路をバイパスするUSB-DACやUSBヘッドセットは、中古PCの音響環境を、最も低コストで、かつ劇的に改善する魔法の杖です。
- ・ストレージの速度は「USBポートの世代」で決まる: 青色のUSB 3.0ポートこそが、高速なデータ転送のための生命線。最高のSSDも、接続するポートがボトルネックでは、その真価を発揮できません。
あなたの目の前にある中古パソコンは、無限の可能性を秘めた、カスタマイズのための最高のキャンバスです。
この記事を羅針盤として、あなたの使い方に完璧にフィットする周辺機器を選び抜き、あなただけの理想のPC環境を、ぜひ創造してください。

パソコン購入のためのお役立ち情報
パソコン選びがよく分からない方、ご不安のある方、悩む前に!お気軽にご相談ください!
専門スタッフが、性能・ご予算・お好みなどご希望に合ったパソコンをお探しします!



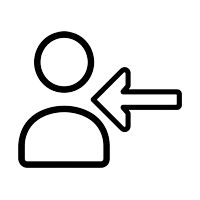 ログイン
ログイン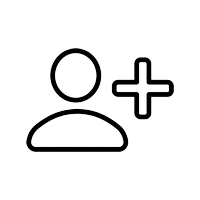 新しくアカウントを作成する
新しくアカウントを作成する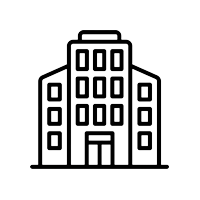 会社概要
会社概要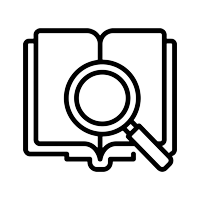 ご利用ガイド
ご利用ガイド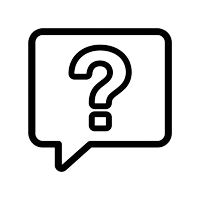 よくあるご質問
よくあるご質問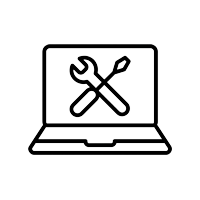 パソコン修理
パソコン修理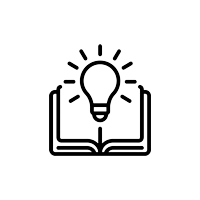 お役立ち情報
お役立ち情報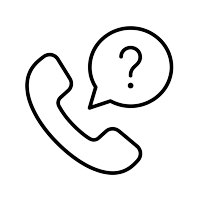 お問い合わせ
お問い合わせ 特定商取引に基づく表示
特定商取引に基づく表示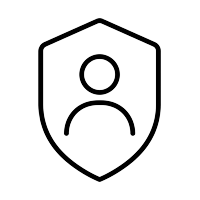 個人情報保護ポリシー
個人情報保護ポリシー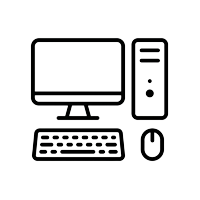 デスクトップパソコン
デスクトップパソコン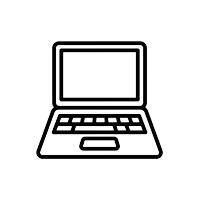 ノートパソコン
ノートパソコン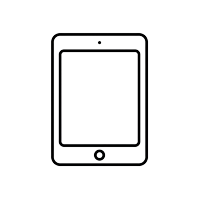 タブレット
タブレット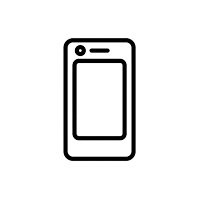 スマートフォン
スマートフォン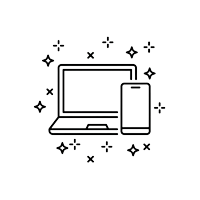 新品(Aランク)
新品(Aランク)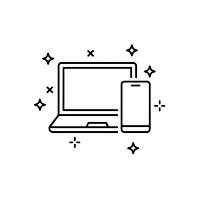 美品(Bランク)
美品(Bランク)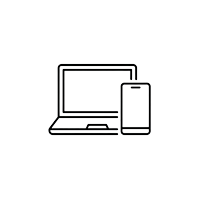 中古(Cランク)
中古(Cランク)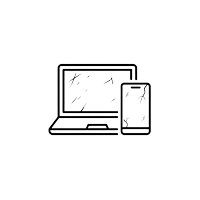 訳あり(Dランク)
訳あり(Dランク)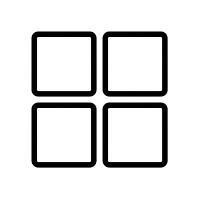 Windows 11
Windows 11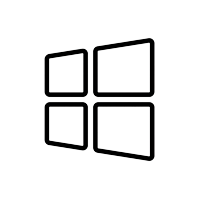 Windows 10
Windows 10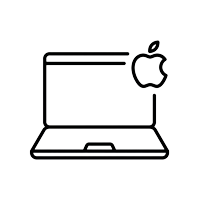 Mac OS
Mac OS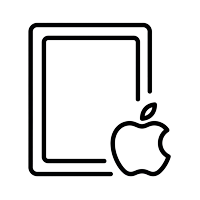 iPad OS
iPad OS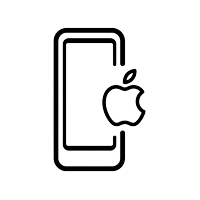 iOS
iOS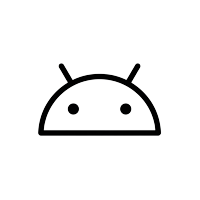 Android
Android コンシューマーモデル
コンシューマーモデル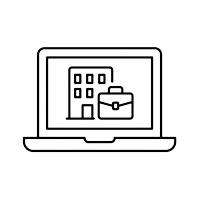 ビジネスモデル
ビジネスモデル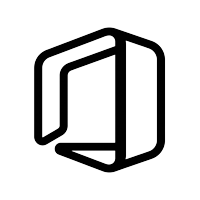 Microsoft Office搭載
Microsoft Office搭載 WPS Office搭載
WPS Office搭載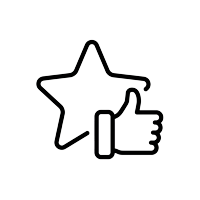 おすすめ商品
おすすめ商品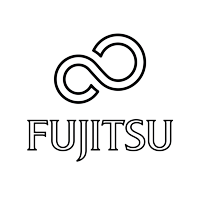
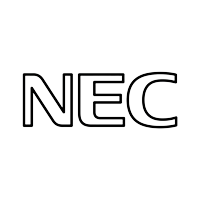
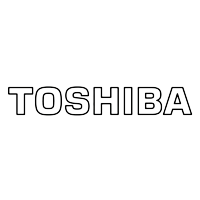


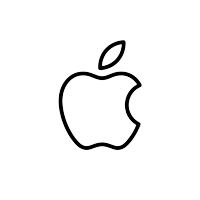


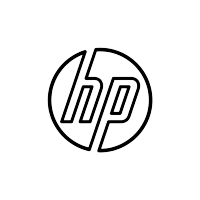
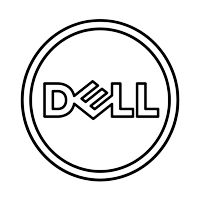

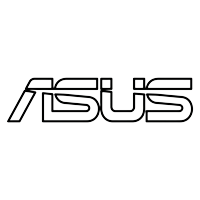
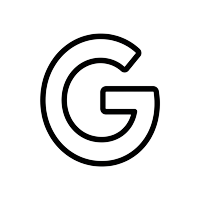

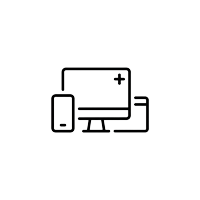
 Celeron|Athlon
Celeron|Athlon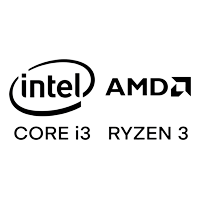 Core i3|Ryzen 3
Core i3|Ryzen 3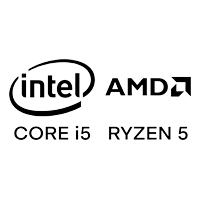 Core i5|Ryzen 5
Core i5|Ryzen 5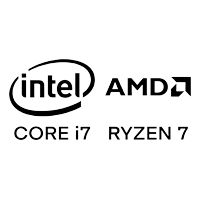 Core i7|Ryzen 7
Core i7|Ryzen 7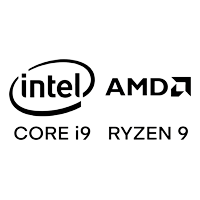 Core i9|Ryzen 9
Core i9|Ryzen 9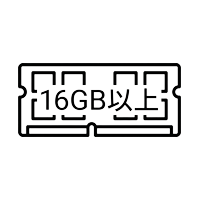 メモリ16GB以上
メモリ16GB以上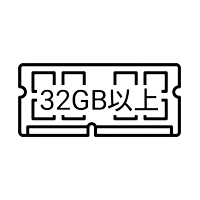 メモリ32GB以上
メモリ32GB以上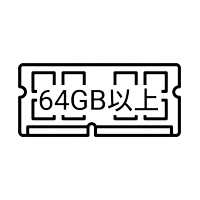 メモリ64GB以上
メモリ64GB以上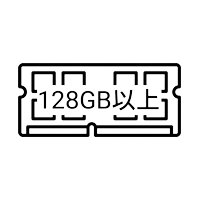 メモリ128GB以上
メモリ128GB以上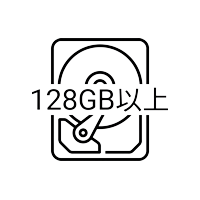 ストレージ128GB以上
ストレージ128GB以上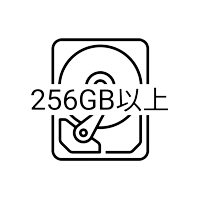 ストレージ256GB以上
ストレージ256GB以上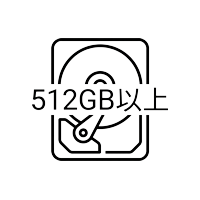 ストレージ512GB以上
ストレージ512GB以上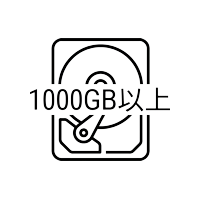 ストレージ1000GB以上
ストレージ1000GB以上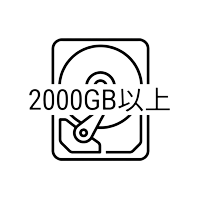 ストレージ2000GB以上
ストレージ2000GB以上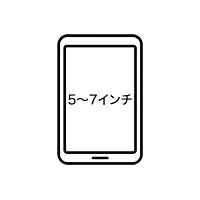 5〜7インチ
5〜7インチ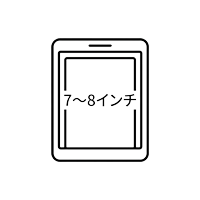 7〜8インチ
7〜8インチ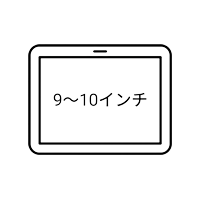 9〜10インチ
9〜10インチ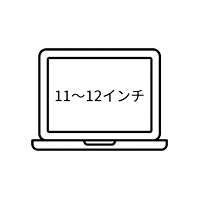 11〜12インチ
11〜12インチ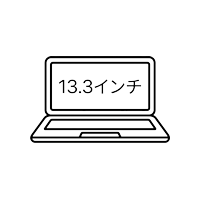 13.3インチ
13.3インチ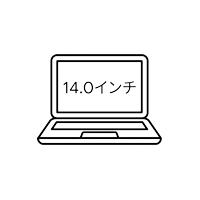 14.0インチ
14.0インチ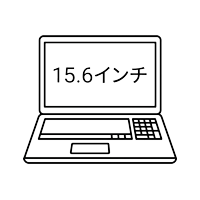 15.6インチ
15.6インチ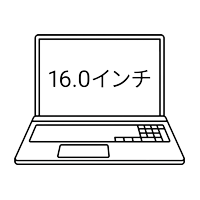 16.0インチ
16.0インチ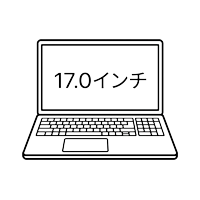 17.0インチ以上
17.0インチ以上




