
ノートパソコンで仮想マシンを使うメリットとデメリット
ノートパソコンのお役立ち情報

記事の最終更新日:2025年7月11日
Web開発の勉強をしているのですが、Windowsの私のノートパソコン上で、Linuxという別のOSを動かして、サーバーの練習をする必要があるんです。
先輩に相談したら、「仮想マシンを使えば、今のPCの中に、もう一台、仮想のPCを作れるよ」と教えてくれました。
なんだかSFみたいでワクワクするのですが、それって、普通のノートパソコンでも本当に可能なのでしょうか?
それに、そんなことをしたら、パソコンの動作がものすごく重くなったり、何かデメリットがあったりしないか、少し心配です。
ノートパソコンで仮想マシンを使うことの、具体的なメリットと、知っておくべきデメリットや注意点を、専門家の視点から詳しく教えてください。
その好奇心、ITの世界を探求する上で、最も素晴らしい才能ですよ。
あなたの先輩がおっしゃる通り、「仮想マシン(Virtual Machine)」は、まさに「PCの中に、もう一台の、完全に独立したPCをソフトウェアで創り出す」技術です。
それは、あらゆる実験や開発、学習を、メインの環境を一切汚すことなく、安全に行える「究極のデジタルな砂場(サンドボックス)」を手に入れることを意味します。
しかし、その魔法のような力の代償として、あなたのノートパソコンは、2台分のPCの仕事を、同時にこなすことを要求されます。
当然、そこには、CPU、メモリ、そしてバッテリーといった、有限なリソースを巡る、厳しい現実との交渉が伴います。
この記事では、仮想マシンがもたらす、計り知れないほどのメリットと、その裏側にある、無視できないデメリットと技術的なトレードオフを、プロの視点から、徹底的に、そして公平に解き明かしていきます。
仮想化という、強力な武器の、正しい使い方を一緒に学んでいきましょう。
仮想化の思想:それは「物理的制約」からの解放である
一台の物理的なコンピュータは、通常、一つのオペレーティングシステム(OS)によって支配されています。
Windowsを動かすためにはWindowsのPCが、Linuxを動かすためにはLinuxのPCが、それぞれ必要になる。
これが、我々が直面する、最も基本的な「物理的制約」です。
仮想化技術の根底にある思想は、この制約からの解放にあります。
ハイパーバイザー(※注釈:物理的なハードウェアを抽象化し、複数のOSが同時に動作するための基盤となるソフトウェア)という、特殊なソフトウェア層を介することで、CPU、メモリ、ストレージといった物理的なリソースを、論理的に分割し、それぞれを、独立した仮想的なハードウェア(仮想マシン)として、各OSに見せかけるのです。
これにより、一台の物理マシンという「舞台」の上で、Windows、macOS、Linuxといった、複数の異なる役者(OS)が、お互いに干渉することなく、同時に、それぞれの役を演じることが可能になります。
ノートパソコンで仮想マシンを使うということは、あなたの持ち運べるその一台のマシンを、必要に応じて、Windowsにも、Linuxサーバーにも、あるいは古いOSの実験機にも、自在に変身させられる、究極のポータビリティと柔軟性を手に入れることに他ならないのです。
第一章:メリット - ノートパソコンが「万能実験室」と化す時
ノートパソコンという限られた筐体の中で、仮想マシンは、開発者、学習者、そしてセキュリティ意識の高いユーザーにとって、計り知れないほどの恩恵をもたらします。
メリット1:完全な分離と安全性 - 究極のサンドボックス環境
これが、仮想マシンを利用する最大のメリットです。
仮想マシンは、ホストOS(あなたのメインのPC環境)から、完全に隔離された、独立した空間です。
仮想マシン内で行った、いかなる操作も、原則としてホストOSには一切影響を及ぼしません。
これにより、以下のような、通常ではリスクの高い活動を、絶対的な安全のもとで実行できます。
- ・ソフトウェアの安全性テスト: インターネット上で見つけた、信頼性の定かでないフリーソフトや、開発中のベータ版アプリケーションを、まず仮想マシンにインストールしてみる。もし、そのソフトがウイルスに感染していたり、システムを不安定にさせたりしても、被害は仮想マシン内に限定され、あなたのメイン環境は無傷のままです。
- ・マルウェアの解析: セキュリティ研究者は、仮想マシンを使って、ウイルスやマルウェアを意図的に実行させ、その挙動を安全に分析します。
- ・危険なウェブサイトへのアクセス: 怪しいメールに記載されたリンク先や、セキュリティ的に不安のあるウェブサイトを、まず仮想マシン内のブラウザで開いてみる。これにより、ブラウザの脆弱性を突くような攻撃からも、ホストOSを守ることができます。
メリット2:OSの多様性 - 一台で実現するマルチOS環境
仮想マシンを使えば、あなたのノートパソコンのOSとは異なる、別のOSを、アプリケーションの一つとして起動することができます。
例えば、あなたがWindowsユーザーであっても、Web開発の世界で標準となっているLinux環境(UbuntuやCentOSなど)を仮想マシンとして導入し、本格的なサーバー構築の学習や、開発を行うことができます。
逆に、Macユーザーが、Windowsでしか動作しない、特定の業務ソフトやPCゲームを利用するために、仮想マシン上にWindowsをインストールすることも一般的です。
さらに、古いバージョンのOSでしか動作しない、特殊な周辺機器のドライバーや、レガシーなソフトウェアを動かすためだけに、Windows XPやWindows 7の仮想マシンを保存しておく、といった、いわば「デジタルな動態保存」も可能になります。
メリット3:スナップショット - 「時間を巻き戻す」魔法の機能
スナップショットは、仮想化技術における、まさに「魔法」と呼ぶにふさわしい機能です。
これは、ある特定の時点における、仮想マシンの状態(メモリ、ディスク、設定の全て)を、そのまま「写真」のように保存する機能です。
例えば、仮想マシン上で、OSの重要なアップデートを適用する前や、システムの根幹に関わる、難しい設定変更に挑戦する前に、スナップショットを撮っておきます。
もし、その後の操作でシステムが起動しなくなったり、取り返しのつかないエラーが発生したりしても、全く問題ありません。
ただ、保存しておいたスナップショットの状態に「復元」するだけで、仮想マシンは、何事もなかったかのように、スナップショットを撮った、まさにその瞬間の状態に、一瞬で戻るのです。
これにより、ユーザーは「失敗」を恐れることなく、あらゆる挑戦的な実験や学習に、安心して取り組むことができます。
この機能の存在こそが、仮想マシンを、最高の学習・開発環境たらしめている、最大の理由の一つです。
第二章:デメリット - 無限の力に課せられる「物理法則」という名の制約
魔法のようなメリットの裏側で、仮想マシンは、ノートパソコンという物理的なハードウェアに対して、相応の「代償」を要求します。
その本質は、有限なリソースを、複数のOSで奪い合うことから生じる、避けられないトレードオフです。
デメリット1:リソースの大量消費という現実
仮想マシンを一台動かすことは、あなたのノートパソコンに、もう一台分のPCの仕事を、同時に要求するのと同じです。
これにより、CPU、メモリ、ストレージといった、全ての物理リソースが、ホストOSとゲストOS(仮想マシン内のOS)によって、激しく奪い合われます。
- ・CPUへの負荷: 2つのOSが同時にCPUの計算能力を要求するため、全体の処理能力は分散され、ホストOSの動作も含めて、システム全体の応答性が低下します。高負荷な仮想マシンを動かせば、当然、冷却ファンは高速で回転し、騒音も増加します。
- ・メモリの分割: 最も深刻な制約が、メモリ(RAM)です。仮想マシンに割り当てたメモリは、その間、ホストOSからは完全に見えなくなり、利用できなくなります。例えば、16GBのメモリを搭載したPCで、仮想マシンに8GBを割り当てれば、あなたが普段使っているホストOS側で利用できるメモリは、わずか8GBに半減してしまうのです。これが、仮想マシン利用の前提として、潤沢なメモリ搭載量(最低16GB、推奨32GB以上)が求められる理由です。
- ・ストレージ容量の圧迫: 仮想マシンの「ハードディスク」は、実際には、あなたのノートパソコンのストレージ上に作成される、巨大な単一のファイル(例:`.vmdk`や`.vdi`ファイル)です。Windows 11の仮想マシンを一つ作るだけでも、数十GBのディスク容量が、瞬時に消費されます。
デメリット2:パフォーマンスのオーバーヘッドと互換性の限界
仮想マシンは、物理的なハードウェアを、ハイパーバイザーというソフトウェア層を通じて、エミュレート(模擬)しています。
このエミュレーションの過程で、どうしても性能の「オーバーヘッド(余分な処理負荷)」が発生します。
特に、その影響が顕著に現れるのが、グラフィック性能です。
仮想マシンに提供されるグラフィックアダプターは、あくまで汎用的なエミュレーションであり、ホストPCが搭載する高性能な専用GPU(dGPU)の能力を、直接引き出すことは、通常できません。
そのため、3Dグラフィックスを駆使する最新のPCゲームや、GPUアクセラレーションを多用する動画編集、CADといった作業には、仮想マシンは全く向いていません。
また、USB接続の特殊なデバイスなどが、仮想マシン上では正しく認識されない、といった、ハードウェアレベルでの互換性の問題が発生することもあります。
デメリット3:バッテリー駆動時間への壊滅的な影響
ノートパソコンにとって、これは致命的な問題です。
仮想マシンを動作させている状態は、PCが最も高い負荷に晒されている状態の一つです。
CPUは常にアクティブな状態を保ち、メモリとストレージへのアクセスも頻繁に発生します。
結果として、バッテリーの消費は劇的に増加し、メーカー公称の駆動時間からは、到底考えられないほどの速さで、バッテリーは消耗していきます。
電源の確保できない、外出先での仮想マシンの利用は、よほど緊急の場合を除き、現実的な選択肢とは言えないでしょう。
第三章:もう一つの選択肢 - 軽量な代替技術「コンテナ」と「WSL」
全ての目的で、重量級の仮想マシンが必要なわけではありません。
特に、開発者が「Windows上で、Linuxのコマンドライン環境が欲しい」という、限定的な目的で利用する場合には、より軽量で、より高速な、代替技術が存在します。
それが、「コンテナ」や「WSL(Windows Subsystem for Linux)」です。
これらの技術は、仮想マシンのように、ハードウェア全体をエミュレートし、独立したOSカーネルを動かすのではなく、ホストOSのカーネルを共有しながら、アプリケーションの実行環境だけを、プロセスレベルで論理的に分離します。
これにより、OSを丸ごと起動する必要がなく、起動は一瞬で、CPUやメモリの消費も、仮想マシンに比べて、桁違いに少なくて済みます。
Windows 11に搭載されているWSL2は、Microsoftが公式にサポートする、Windows上で本格的なLinux環境を、極めて高いパフォーマンスで実現するための、革新的な機能です。
もしあなたの目的が、「LinuxのGUIデスクトップ環境を使いたい」あるいは「Windows以外のOS(例:macOS)を動かしたい」といったものではなく、純粋に「開発用のLinuxシェル環境が欲しい」ということであれば、仮想マシンではなく、WSL2を導入する方が、遥かに賢明で、快適な選択となります。
まとめ:仮想マシンは、目的を明確にして使う「専門家の道具」である
ノートパソコン上で仮想マシンを運用することは、あなたのPCの可能性を、物理的な一台という制約を超えて、無限に拡張する、強力な力をもたらします。
しかし、その力は、有限なリソースという、明確なコストの上に成り立っています。
仮想マシンを導入すべきか否か、その判断は、あなたがその力を使って「何をしたいのか」という、明確な目的意識にかかっています。
- ・メリット(得るもの): 安全な実験環境、複数OSの同時利用、そして時間を巻き戻すスナップショット機能。これらは、学習、開発、そしてセキュリティテストにおいて、何物にも代えがたい価値を提供します。
- ・デメリット(失うもの): CPU、メモリ、ストレージ、そしてバッテリーという、ノートパソコンの貴重な物理リソース。仮想マシンの実行は、これらのリソースに、常に高い「税金」を課します。特にグラフィック性能とバッテリー駆動時間は、大きな制約を受けます。
- ・代替案を検討する: あなたの目的が、もし「Windows上でLinuxのコマンドラインが使いたい」だけであれば、フル装備の仮想マシンではなく、WSL2という、より軽量で高速な、専用の解決策が存在することを、忘れてはいけません。
あなたのノートパソコンのスペックと、あなたが仮想マシンで実現したい目的を天秤にかけ、そのメリットが、デメリットを上回ると判断した時。
その時こそ、あなたのノートパソコンは、ただの作業道具から、あなただけの、万能で、安全な、究極の「デジタル実験室」へと、その姿を変えるのです。

パソコン購入のためのお役立ち情報
パソコン選びがよく分からない方、ご不安のある方、悩む前に!お気軽にご相談ください!
専門スタッフが、性能・ご予算・お好みなどご希望に合ったパソコンをお探しします!



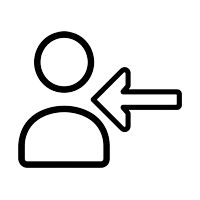 ログイン
ログイン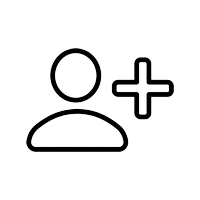 新しくアカウントを作成する
新しくアカウントを作成する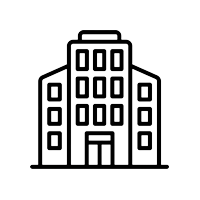 会社概要
会社概要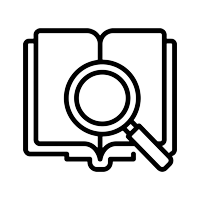 ご利用ガイド
ご利用ガイド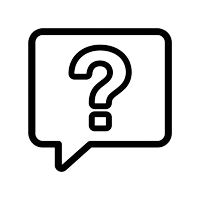 よくあるご質問
よくあるご質問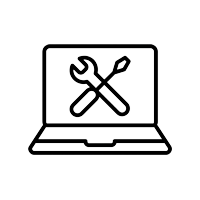 パソコン修理
パソコン修理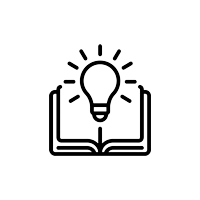 お役立ち情報
お役立ち情報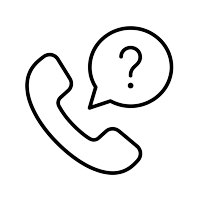 お問い合わせ
お問い合わせ 特定商取引に基づく表示
特定商取引に基づく表示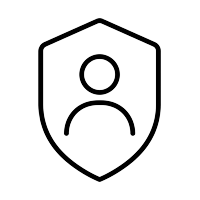 個人情報保護ポリシー
個人情報保護ポリシー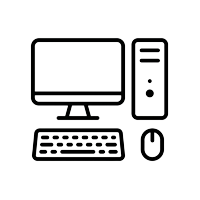 デスクトップパソコン
デスクトップパソコン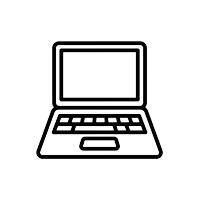 ノートパソコン
ノートパソコン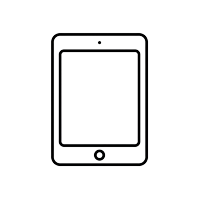 タブレット
タブレット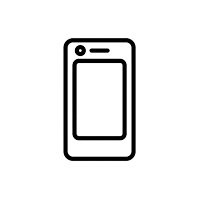 スマートフォン
スマートフォン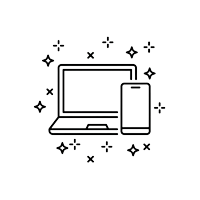 新品(Aランク)
新品(Aランク)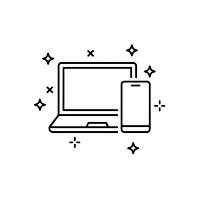 美品(Bランク)
美品(Bランク)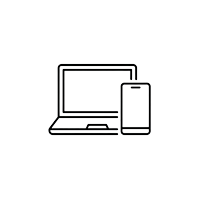 中古(Cランク)
中古(Cランク)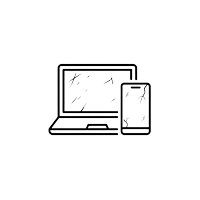 訳あり(Dランク)
訳あり(Dランク)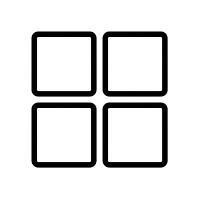 Windows 11
Windows 11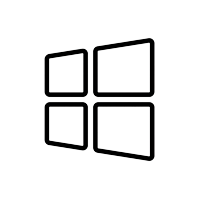 Windows 10
Windows 10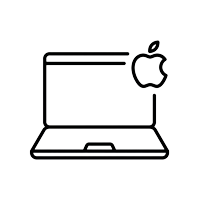 Mac OS
Mac OS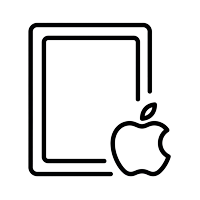 iPad OS
iPad OS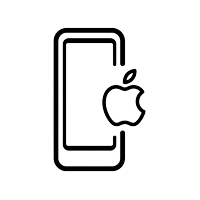 iOS
iOS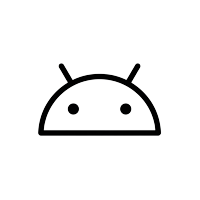 Android
Android コンシューマーモデル
コンシューマーモデル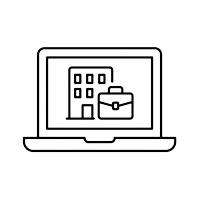 ビジネスモデル
ビジネスモデル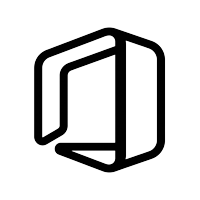 Microsoft Office搭載
Microsoft Office搭載 WPS Office搭載
WPS Office搭載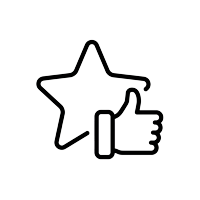 おすすめ商品
おすすめ商品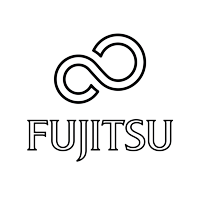
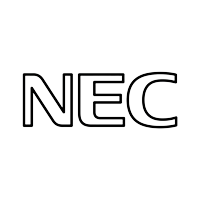
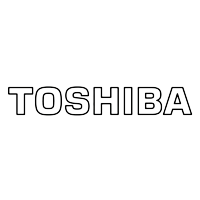


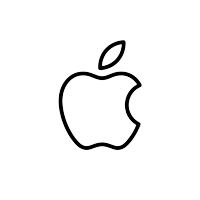


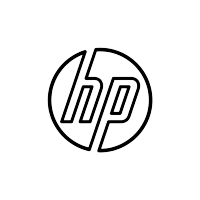
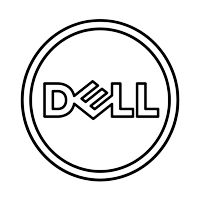

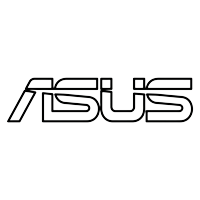
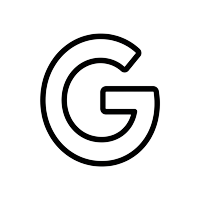

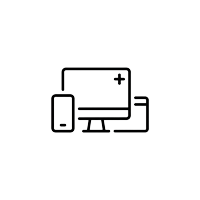
 Celeron|Athlon
Celeron|Athlon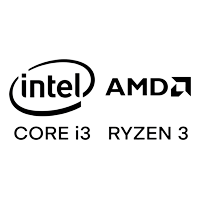 Core i3|Ryzen 3
Core i3|Ryzen 3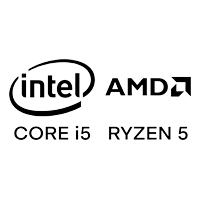 Core i5|Ryzen 5
Core i5|Ryzen 5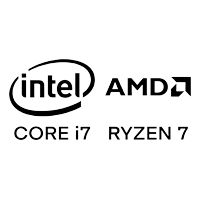 Core i7|Ryzen 7
Core i7|Ryzen 7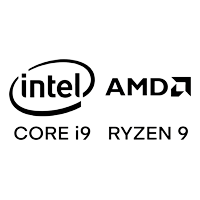 Core i9|Ryzen 9
Core i9|Ryzen 9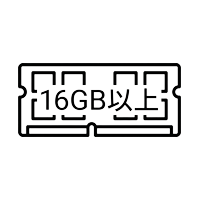 メモリ16GB以上
メモリ16GB以上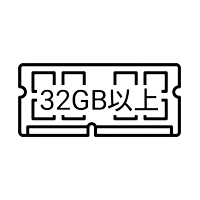 メモリ32GB以上
メモリ32GB以上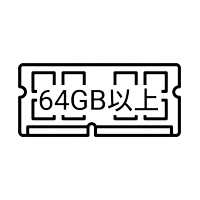 メモリ64GB以上
メモリ64GB以上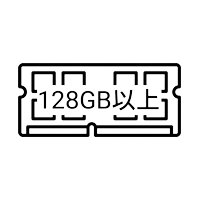 メモリ128GB以上
メモリ128GB以上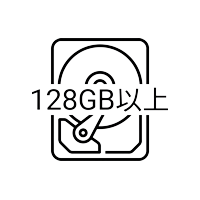 ストレージ128GB以上
ストレージ128GB以上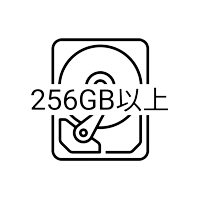 ストレージ256GB以上
ストレージ256GB以上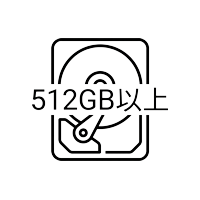 ストレージ512GB以上
ストレージ512GB以上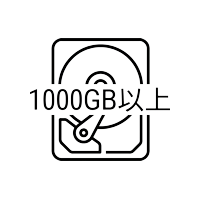 ストレージ1000GB以上
ストレージ1000GB以上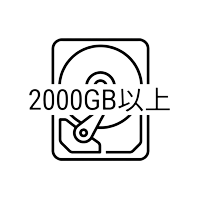 ストレージ2000GB以上
ストレージ2000GB以上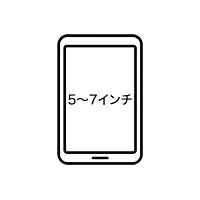 5〜7インチ
5〜7インチ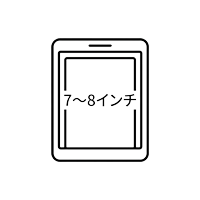 7〜8インチ
7〜8インチ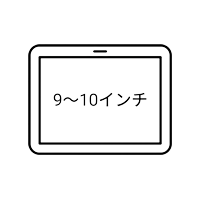 9〜10インチ
9〜10インチ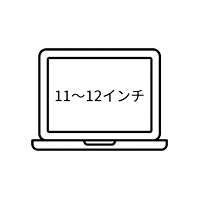 11〜12インチ
11〜12インチ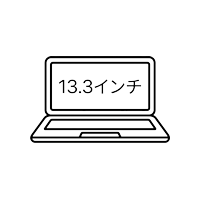 13.3インチ
13.3インチ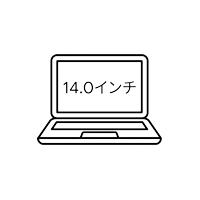 14.0インチ
14.0インチ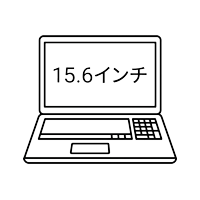 15.6インチ
15.6インチ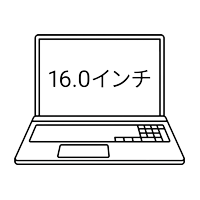 16.0インチ
16.0インチ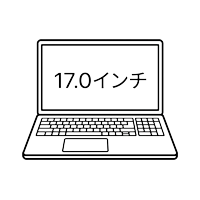 17.0インチ以上
17.0インチ以上




