
PowerPointでナレーション付きスライドを作成する方法
Officeのお役立ち情報

記事の最終更新日:2025年7月12日
最近オンライン研修用の資料を作っているのですが、PowerPointにナレーションを入れるのがとても難しくて…。
ただ音声を録音するだけでなく、もっとプロのようにBGMを加えたり、アニメーションとタイミングを完璧に合わせたりしたいんです。
何か上級者向けのテクニックまで含めて、詳しく教えてもらえませんか?
お任せください。
PowerPointのナレーション機能は、実は非常に奥が深いんですよ。
単なる録音に留まらず、そのポテンシャルを最大限に引き出すためのプロフェッショナルなテクニックが存在します。
この記事では、基本的な録音方法からBGMの挿入、高度な音声編集、さらには外部ツールとの連携に至るまで、考えられるあらゆるテクニックを網羅し、「日本一詳しい」と胸を張れるレベルで徹底的に解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたもプロ顔負けのナレーション付きスライドが作れるようになっていますよ。
PowerPointナレーションの基礎固め:録音前の重要な準備
視聴者の心に響く高品質なナレーションは、録音ボタンを押す前の「準備」でその品質の9割が決まると言っても過言ではありません。
最高のパフォーマンスを発揮するため、機材の選定、環境の整備、そして話す内容の整理という3つの重要なステップを、プロの視点で深く掘り下げていきましょう。
最高の音質を求めて:マイクの選定と設定

ナレーションの品質を決定づける最も重要な要素はマイクです。
ノートパソコンに内蔵されているマイクは手軽ですが、キーボードの打鍵音や冷却ファンの騒音、さらには自分自身の声がPC筐体内で反響した、こもった音を拾いがちです。
クリアで聞きやすい音声を録音するためには、外付けマイクの使用が絶対条件となります。
特におすすめなのが、USB接続の「コンデンサーマイク」です。
コンデンサーマイクは微細な音のニュアンスまで捉えることができる高感度なマイクで、人の声を暖かく明瞭に録音するのに非常に適しています。
マイクを選んだら、次はOSレベルでの設定です。
Windowsの場合、「設定」→「システム」→「サウンド」を開き、「入力」セクションで使用するマイクが正しく選択されているかを確認します。
さらに「デバイスのプロパティ」から入力レベル(マイクの感度)を調整します。
声が小さすぎず、かつ大きすぎて音が割れる「クリッピング」が起きない最適なレベル(一般的には最大入力の70%〜80%程度)に設定することが肝要です。
静寂は金なり:録音環境の最適化

優れたマイクも、騒がしい環境ではその真価を発揮できません。
録音環境の最適化とは、不要なノイズを徹底的に排除し、声の反響をコントロールすることです。
まず、エアコンや扇風機、空気清浄機といった定常的なノイズ源は、録音時だけは停止させましょう。
パソコン本体の冷却ファンノイズも大敵です。
可能であれば、マイクとPC本体の間に物理的な距離を置くか、指向性(特定方向の音だけを拾う性質)の鋭いマイクを使用し、PCがマイクの背面に来るように配置します。
次に重要なのが反響対策です。
壁や床、天井が硬い材質でできた部屋は声が反響しやすく、お風呂場で話しているような不自然な音になりがちです。
これを防ぐには、吸音材となるものを部屋に配置します。
厚手のカーテンを閉める、床にカーペットやラグを敷く、壁際に本棚や布製の家具を置くといった対策が非常に有効です。
より本格的に行うなら、マイクの周囲を吸音パネルで囲む「リフレクションフィルター」を使用すると、驚くほどクリアで締まりのある音質が得られます。
設計図を描く:台本の作成と読み込み練習

アドリブで話すことは、一見自然に聞こえるかもしれませんが、情報の抜け漏れや話の脱線、時間超過といったリスクを伴います。
プロフェッショナルなナレーションは、練り上げられた台本という設計図の上に成り立っています。
まず、各スライドで伝えたい核心的なメッセージを箇条書きで書き出します。
次に、それを口に出して話すための自然な話し言葉に変換していきます。
この際、専門用語を多用しすぎず、視聴者が直感的に理解できる平易な言葉を選ぶことが重要です。
台本が完成したら、必ず声に出して読む練習を繰り返します。
ストップウォッチで時間を計り、各スライドの表示時間とナレーションの長さが適切かを確認します。
言い淀む箇所や不自然な間がないか、録音した自分の声を客観的に聞き返すことで、台本のさらなるブラッシュアップが可能になります。
実践編:PowerPointでのナレーション録音テクニック
万全の準備が整ったところで、いよいよPowerPointでの録音作業に入ります。
PowerPointには大きく分けて2つの録音方法があり、それぞれの特性を理解し使い分けることで、作業効率と品質を飛躍的に向上させることができます。
全編を一気に収録:「スライドショーの記録」機能

プレゼンテーション全体の流れを通して、アニメーションや画面切り替えのタイミングに合わせて録音するなら、「スライドショーの記録」機能が最適です。
「スライドショー」タブを開き、「記録」ボタンをクリックすると、専用の録音インターフェースが表示されます。
左上の大きな赤い「記録」ボタンを押すと、3秒のカウントダウン後に録音が開始されます。
録音中は、通常のスライドショーと同様にクリックや矢印キーでアニメーションを再生したり、次のスライドに進めたりできます。
この機能の素晴らしい点は、それらの操作タイミングが音声と完全に同期して記録されることです。
画面下部にはペンやレーザーポインターツールがあり、スライドの特定の部分を指し示しながら説明することも可能です。
一つ重要な注意点として、スライドが切り替わるまさにその瞬間は、音声が記録されません。
したがって、各スライドの最後の言葉を話し終えた後、一呼吸置いてから次のスライドへ進むように心がけると、音声の途切れを防ぐことができます。
一枚ずつ丁寧に録音:「オーディオの録音」機能

プレゼンテーション全体ではなく、特定のスライドのナレーションだけを録り直したい場合や、簡単な音声メモを追加したい場合には、個別に音声を挿入する方法が手軽で便利です。
対象のスライドを選択し、「挿入」タブのリボンメニューから「オーディオ」→「オーディオの録音」を選びます。
シンプルな録音ダイアログボックスが表示されるので、録音データに分かりやすい名前を付け、録音ボタンを押してナレーションを吹き込みます。
停止ボタンを押して「OK」をクリックすると、スライド上にスピーカーアイコンが表示され、音声が埋め込まれます。
この方法は、「スライドショーの記録」で録音した一部分を差し替えたい時などに非常に重宝します。
ただし、この方法で挿入した音声は、スライド内のアニメーションとは自動で同期しません。
再生タイミングの調整は、後述するアニメーションウィンドウで手動設定する必要があります。
プロ級の仕上がりへ:ナレーション編集と音響効果
録音しただけの「素の」音声は、いわば原石です。
ここからは、PowerPointの編集機能を駆使して原石を磨き上げ、視聴者の耳に心地よく響く、洗練された音声コンテンツへと昇華させるための応用技術を解説します。
音声のカットと調整:トリミングと音量正規化

録音の開始前や終了後に入ってしまった不要な無音部分や、「えーっと」といった言い淀みは、聞き手にとってストレスの原因となります。
スライド上のスピーカーアイコンを選択し、リボンに表示される「再生」タブから「オーディオのトリミング」機能を使えば、これらの不要部分を簡単にカットできます。
音声の波形が表示される専用ウィンドウで、緑色の開始マーカーと赤色の終了マーカーをドラッグし、残したい範囲を指定するだけです。
さらに、音声の始まりと終わりを滑らかにする「フェードイン」「フェードアウト」効果も同じ「再生」タブから設定できます。
継続時間を0.5秒〜1秒程度に設定するだけで、音声が唐突に始まったり終わったりする印象がなくなり、プロフェッショナルな仕上がりになります。
また、スライドごとに録音した音声の音量がバラバラな場合は、「音量」ボタンから「大」や「中」に統一することで、聞きやすいプレゼンテーションになります。
雰囲気を演出する:BGMの挿入と音量バランス

適切に使用されたBGM(背景音楽)は、プレゼンテーション全体の雰囲気を演出し、視聴者の感情に訴えかけ、エンゲージメントを高める強力な武器となります。
BGMを開始したい最初のスライドで、「挿入」タブからオーディオファイルを読み込みます。
ここからが最も重要な設定です。
挿入したBGMのスピーカーアイコンを選択し、「再生」タブで以下の2つに必ずチェックを入れてください。
一つは「**スライド切り替え後も再生**」、もう一つは「**ループ再生**」です。
これにより、スライドが変わってもBGMが途切れず、曲が終了しても自動的に最初から再生され、プレゼンテーション全体を通して音楽が流れ続けるようになります。
そして、BGMはあくまで背景であるため、ナレーションの明瞭さを決して妨げてはなりません。
「音量」設定を「小」にし、実際にナレーションと重ねて聞きながら、ナレーションがはっきりと聞こえる最適なバランスを見つけてください。
動きと声を完璧に同期:アニメーションタイミングの神髄

「この言葉を言った瞬間に、この図形を出現させたい」といった、ナレーションとアニメーションの完璧な同期は、プレゼンテーションのクオリティを劇的に向上させます。
この精密な調整を行うための聖域が、「アニメーション」タブにある「**アニメーション ウィンドウ**」です。
アニメーションウィンドウを開くと、スライドに設定されたすべてのアニメーションが時系列でリスト表示されます。
各アニメーションの開始タイミングは、デフォルトでは「クリック時」になっていますが、これを「直前の動作と同時」または「直前の動作の後」に変更することで、自動再生のアニメーションシーケンスを組むことができます。
ナレーションとの同期で最も強力な武器となるのが「**遅延**」設定です。
例えば、スライドのナレーション音声(これもアニメーションの一つとして表示されます)を再生開始のトリガーとし、特定の図形のアニメーションを「開始:直前の動作と同時」に設定した上で、「遅延:2.5秒」と入力します。
これにより、ナレーションが始まってから2.5秒後に、その図形が動き出すという精密な制御が可能になります。
最適な秒数を見つけるには、プレビューを繰り返す地道な作業が必要ですが、この手間をかける価値は十分にあります。
アクセシビリティと活用の幅を広げる最終工程
素晴らしいナレーション付きスライドが完成したら、それをより多くの人々に、より効果的に届けるための仕上げ作業に入ります。
ここでは、コンテンツのアクセシビリティを高め、様々なプラットフォームで活用するための方法を解説します。
全ての視聴者へ:字幕(キャプション)の追加方法

字幕(キャプション)は、聴覚に障がいのある方への配慮(アクセシビリティ)という重要な役割はもちろん、騒がしい場所や音を出せない環境で視聴している人々の理解を助ける上でも非常に有効です。
PowerPointでは、WebVTT(Web Video Text Tracksの略。動画に字幕を表示するための標準的なファイル形式)という形式の字幕ファイルを作成し、ビデオに埋め込むことができます。
WebVTTファイルは、メモ帳などのテキストエディタで作成できるシンプルなテキストファイルです。
ファイルの先頭に「WEBVTT」と記述し、改行を挟んで「`HH:MM:SS.mmm --> HH:MM:SS.mmm`」の形式で字幕の表示開始時間と終了時間を指定し、その次の行に表示したいテキストを記述します。
これをUTF-8という文字コードで、拡張子を「.vtt」にして保存します。
作成したビデオ(MP4)をPowerPointのスライドに挿入し、「再生」タブの「キャプションの挿入」から、この.vttファイルを選択することで、ビデオ再生時に字幕が表示されるようになります。
完成品のエクスポート:ビデオ形式での保存

作成したナレーション付きスライドは、PowerPointファイル(.pptx)のままでは、視聴環境が限定されます。
YouTubeやSNS、ウェブサイトへの埋め込みなど、幅広く活用するために、ビデオ形式(MP4)でエクスポートしましょう。
「ファイル」→「エクスポート」→「ビデオの作成」を選択します。
ここで重要なのが、品質(解像度)の選択です。
一般的には、画質とファイルサイズのバランスに優れた「**フル HD (1080p)**」が最適です。
そして、エクスポート設定における最重要項目が「**記録されたタイミングとナレーションを使用する**」というドロップダウンメニューです。
必ずこれを選択してください。
これを選ばないと、せっかく苦労して設定したナレーションやアニメーションのタイミングがすべて無視されてしまいます。
全ての設定を確認したら「ビデオの作成」ボタンを押し、変換が完了するのを待ちます。
さらなる高みへ:外部ツールとの連携
PowerPointは非常に強力なツールですが、音声編集や動画編集の専門ソフトと連携させることで、そのクオリティはさらに上の次元へと到達します。
ノイズよさらば:Audacityによる高度な音声編集

もし録音したナレーションに「サー」というホワイトノイズや、空調の音がわずかに入ってしまった場合、無料でありながらプロ級の機能を誇る音声編集ソフト「Audacity」の出番です。
PowerPointのスライド上にあるスピーカーアイコンを右クリックし、「メディアに名前を付けて保存」で音声をWAVファイルとして書き出します。
そのファイルをAudacityで開き、「エフェクト」メニューから「ノイズの除去と修復」→「ノイズリダクション」を選択します。
まず、音声が入っていないノイズだけの部分を選択して「ノイズプロファイルを取得」ボタンを押し、Audacityに除去すべきノイズのパターンを学習させます。
次に、音声全体を選択して再度同じエフェクトを開き、設定を調整して「OK」を押せば、驚くほどクリーンな音声になります。
処理後の音声を再度書き出し、PowerPointに再挿入することで、ナレーションの品質を格段に向上させることができます。
究極の仕上げ:動画編集ソフトでの最終調整

最高のクオリティを追求するなら、PowerPointを「動きのある静止画を作成するツール」と割り切り、最終的な仕上げを専門の動画編集ソフトで行うという選択肢もあります。
PowerPointからはナレーションやBGMを付けずに、映像だけをMP4形式でエクスポートします。
そして、別途録音・編集したナレーション音声、BGM、効果音、テロップなどを、動画編集ソフトのタイムライン上で精密に配置していきます。
この方法の利点は、PowerPointでは不可能な、より複雑な編集が可能になることです。
例えば、ナレーションが話している間だけBGMの音量を自動的に下げる「オーディオダッキング」や、より多彩で洗練されたテロップや画面切り替え効果(トランジション)の追加など、まさにテレビ番組のような演出を施すことができます。
まとめ
本記事では、PowerPointでプロ品質のナレーション付きスライドを作成するための、準備から応用、さらには外部ツール連携に至るまでの全工程を、専門的な視点から徹底的に解説しました。
- 準備が成功の鍵:高品質なUSBマイクを用意し、静かで反響の少ない環境を整え、練り上げた台本に基づいて録音することが、全ての土台となります。
- 録音機能の使い分け:プレゼン全体の流れは「スライドショーの記録」で、部分的な修正は「オーディオの録音」で効率的に作業を進めましょう。
- 編集で品質向上:トリミングやフェード効果で音声を聞きやすく整え、BGMで雰囲気を演出し、「アニメーションウィンドウ」の「遅延」機能を駆使して動きと声を完璧に同期させることが、プロへの道です。
- 最終出力がゴール:アクセシビリティ向上のために字幕を用意し、適切な解像度(フルHD推奨)のMP4ビデオとして書き出すことを忘れないでください。
- 外部ツールで限界突破:Audacityでのノイズ除去や、専門の動画編集ソフトでの最終仕上げに挑戦することで、PowerPoint単体では到達できない、さらなるクオリティの高みを目指せます。
これらのテクニックは、一つ一つは地道な作業かもしれませんが、組み合わせることで、あなたのメッセージをより強力に、そして魅力的に伝えるための最高のツールとなります。
ぜひこの記事を参考に、あなたの知識と情熱が詰まった、素晴らしいナレーション付きコンテンツを作成してください。

パソコン購入のためのお役立ち情報
パソコン選びがよく分からない方、ご不安のある方、悩む前に!お気軽にご相談ください!
専門スタッフが、性能・ご予算・お好みなどご希望に合ったパソコンをお探しします!



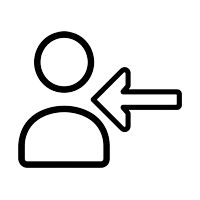 ログイン
ログイン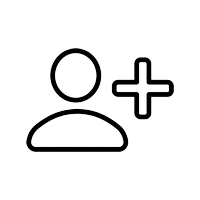 新しくアカウントを作成する
新しくアカウントを作成する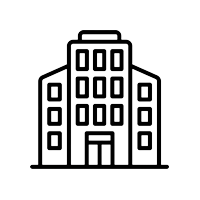 会社概要
会社概要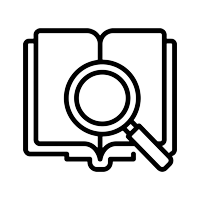 ご利用ガイド
ご利用ガイド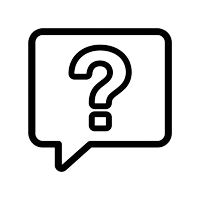 よくあるご質問
よくあるご質問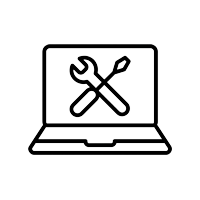 パソコン修理
パソコン修理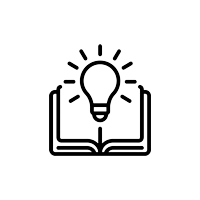 お役立ち情報
お役立ち情報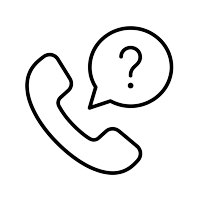 お問い合わせ
お問い合わせ 特定商取引に基づく表示
特定商取引に基づく表示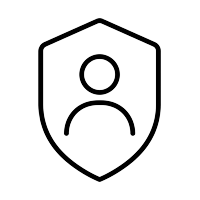 個人情報保護ポリシー
個人情報保護ポリシー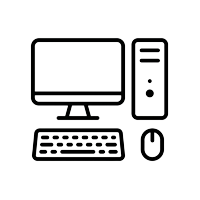 デスクトップパソコン
デスクトップパソコン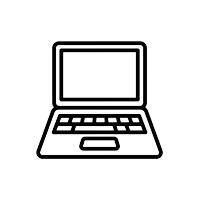 ノートパソコン
ノートパソコン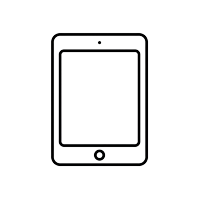 タブレット
タブレット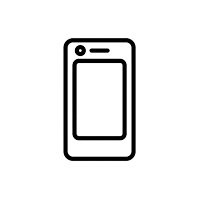 スマートフォン
スマートフォン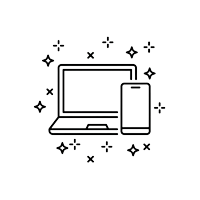 新品(Aランク)
新品(Aランク)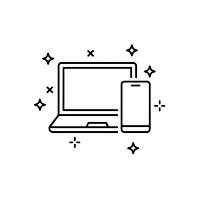 美品(Bランク)
美品(Bランク)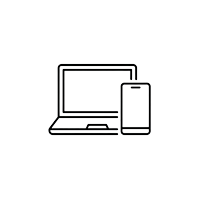 中古(Cランク)
中古(Cランク)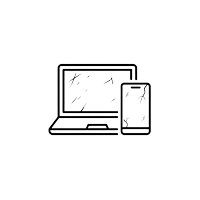 訳あり(Dランク)
訳あり(Dランク)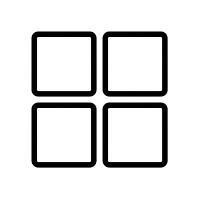 Windows 11
Windows 11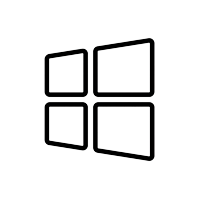 Windows 10
Windows 10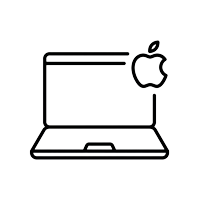 Mac OS
Mac OS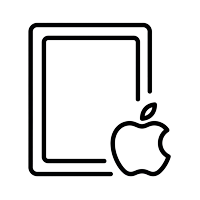 iPad OS
iPad OS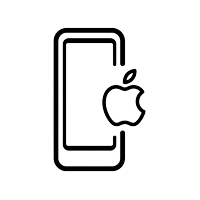 iOS
iOS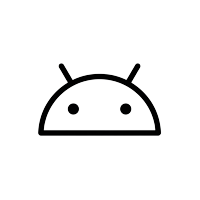 Android
Android コンシューマーモデル
コンシューマーモデル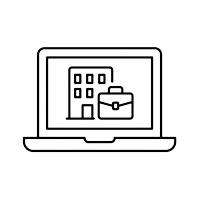 ビジネスモデル
ビジネスモデル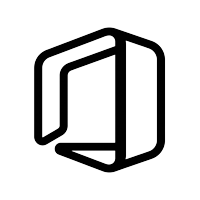 Microsoft Office搭載
Microsoft Office搭載 WPS Office搭載
WPS Office搭載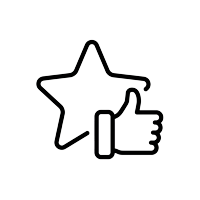 おすすめ商品
おすすめ商品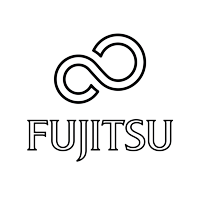
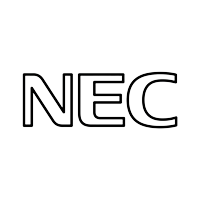
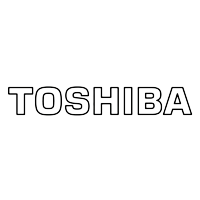


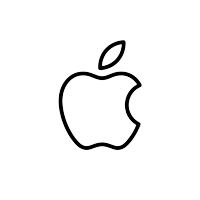


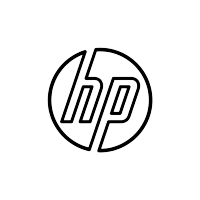
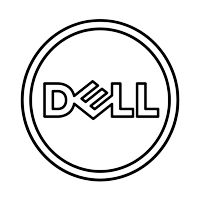

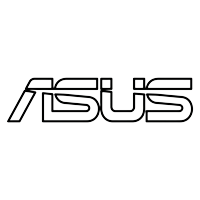
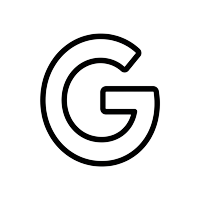

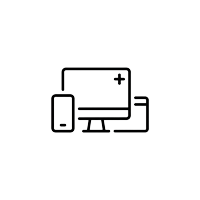
 Celeron|Athlon
Celeron|Athlon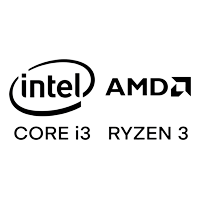 Core i3|Ryzen 3
Core i3|Ryzen 3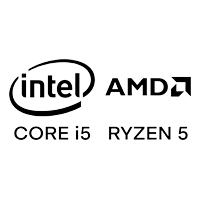 Core i5|Ryzen 5
Core i5|Ryzen 5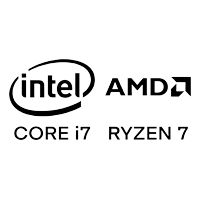 Core i7|Ryzen 7
Core i7|Ryzen 7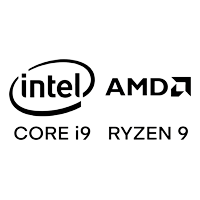 Core i9|Ryzen 9
Core i9|Ryzen 9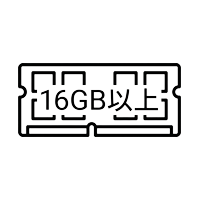 メモリ16GB以上
メモリ16GB以上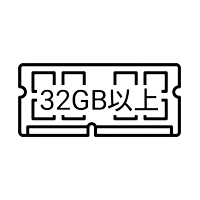 メモリ32GB以上
メモリ32GB以上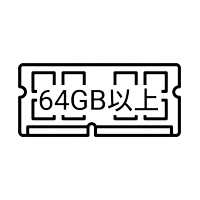 メモリ64GB以上
メモリ64GB以上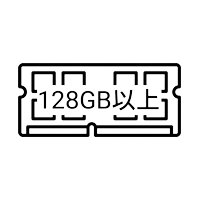 メモリ128GB以上
メモリ128GB以上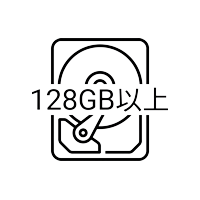 ストレージ128GB以上
ストレージ128GB以上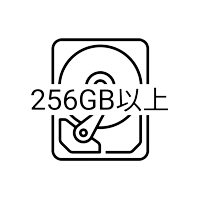 ストレージ256GB以上
ストレージ256GB以上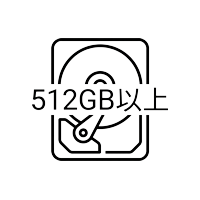 ストレージ512GB以上
ストレージ512GB以上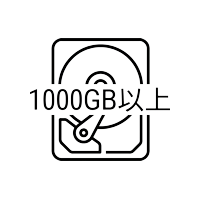 ストレージ1000GB以上
ストレージ1000GB以上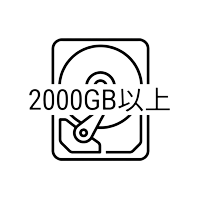 ストレージ2000GB以上
ストレージ2000GB以上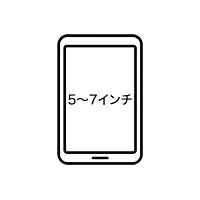 5〜7インチ
5〜7インチ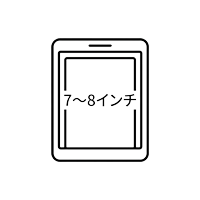 7〜8インチ
7〜8インチ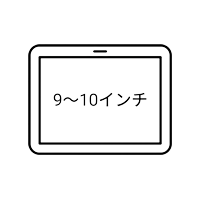 9〜10インチ
9〜10インチ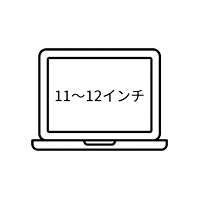 11〜12インチ
11〜12インチ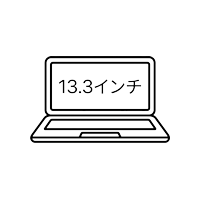 13.3インチ
13.3インチ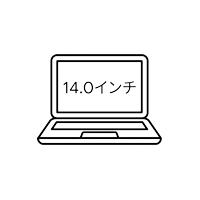 14.0インチ
14.0インチ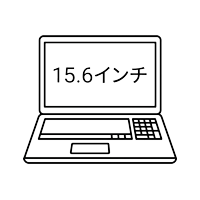 15.6インチ
15.6インチ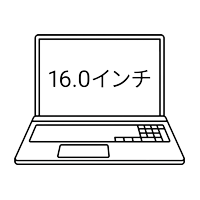 16.0インチ
16.0インチ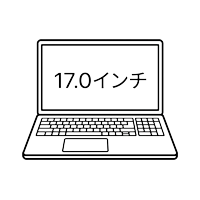 17.0インチ以上
17.0インチ以上




