
Windows 11の設定アプリで個別設定を一元管理する方法
Windowsのお役立ち情報

記事の最終更新日:2025年7月11日
最近、パソコンをWindows 11にアップグレードしたんです。
新しい「設定」アプリは、見た目はスッキリして綺麗なのですが、以前のコントロールパネルに慣れていたせいか、どこに何の設定があるのか、さっぱり分からなくなってしまいました。
ディスプレイの表示を変えたい時、プライバシーの設定を見直したい時、あるいはスタートアップに登録されているアプリを管理したい時など、目的の設定項目にたどり着くまでに、いつも時間がかかってしまいます。
この新しい設定アプリの全体像と、もっと素早く、そして効率的に目的の設定にアクセスするための、何かプロの技のようなものは無いのでしょうか?
その感覚、非常によく分かります。
Windows 11の「設定」アプリは、長年親しんだ「コントロールパネル」という、雑多な道具箱から、整然と区画された「モダンなショールーム」へと、住まいを移したようなものです。
最初は戸惑いますが、その設計思想と、論理的な構造を一度理解してしまえば、これほど分かりやすく、そして強力なツールはありません。
ご安心ください。
この記事では、まず、その新しいショールームの、全ての部屋(カテゴリ)を巡る、グランドツアーにご案内します。
その上で、今なお特定の役割を持つ、旧市街の「コントロールパネル」との関係性、そして、あらゆる設定画面に、一瞬でワープするための、専門家だけが知る「秘密の呪文(URIコマンド)」まで、あなたのWindows 11の管理能力を、別次元へと引き上げるための、全ての知識を授けましょう。
設定アプリの哲学:それは「対話」のための、統一されたインターフェース
Windows 11における「設定」アプリの導入は、単なるデザインの変更ではありません。
それは、これまでOSの各所に散らばり、時には「コントロールパネル」、時には個別のプロパティ画面といった、バラバラの作法で管理されていた、PCとの「対話」の窓口を、一つの、統一された、そして論理的な場所に集約しようとする、Microsoftの長年にわたる壮大なプロジェクトの、現時点での集大成です。
左側に並んだ、明確なカテゴリ。
検索バーによる、強力な横断検索機能。
そして、マウスだけでなく、タッチ操作にも最適化された、モダンなインターフェース。
これらは全て、ユーザーがPCの状態を、より直感的に把握し、その挙動を、より簡単に、そして安全にコントロールできるように、という設計思想に基づいています。
設定アプリを使いこなすことは、もはや単なるPCのカスタマイズではなく、あなたのPCという、最も身近なパートナーとの、円滑なコミュニケーション術を学ぶことに他ならないのです。
第一章:グランドツアー - 11のカテゴリを巡る、設定アプリの完全解説
`Win + I`というショートカットキーで、いつでも呼び出せる「設定」アプリ。
その左側に並ぶ11のカテゴリは、Windows 11の全ての機能を網羅する、目次となっています。
ここでは、各カテゴリの役割と、その中に隠された、特に重要で、見落としがちな設定項目を、一つずつ解説していきます。
システム (System)
PCの最も基本的な状態と、最も頻繁にアクセスする設定が、ここに集約されています。
- ・ディスプレイ: 画面の明るさ、解像度、そしてマルチモニターの配置といった、視覚環境の全てを管理します。特に、夜間の目の負担を軽減する「夜間モード」や、対応モニターで映像の表現力を高める「HDR」の設定は、ここで有効化します。
- ・サウンド: スピーカーやヘッドホンといった「出力デバイス」と、マイクなどの「入力デバイス」の切り替え、音量の調整を行います。「音量ミキサー」を開けば、アプリケーションごとに、個別の音量を設定することも可能です。
- ・電源とバッテリー: ノートパソコンの生命線です。「電源モード」を「トップクラスの電力効率」に設定することで、バッテリー駆動時間を最大化できます。また、「バッテリー節約機能」や、アプリごとのバッテリー使用状況の確認も、ここで行います。
- ・ストレージ: PCの空き容量を確認し、不要なファイルを自動で削除してくれる、賢いお掃除機能「ストレージセンサー」を有効化できます。
- ・バージョン情報: あなたのPCの正式名称、CPU、実装RAM、OSのエディションやバージョンといった、最も基本的な「自己紹介」が、ここに記載されています。
Bluetoothとデバイス (Bluetooth & devices)
マウス、キーボード、プリンター、イヤホンといった、PCに接続される、あらゆる「手足」を管理する場所です。
「デバイスの追加」から、新しいBluetooth機器のペアリングを行うのが、基本的な使い方です。
特に「タッチパッド」の項目では、3本指や4本指のスワイプといった、「高精度タッチパッド」ジェスチャーの動作を、あなたの好みに合わせて、細かくカスタマイズすることができます。
ネットワークとインターネット (Network & internet)
PCを外界と繋ぐ、全ての通信設定を司ります。
Wi-Fiや有線LANの接続状況の確認、IPアドレスやDNSサーバーの手動設定といった、高度なネットワーク構成も、ここから行えます。
また、公共のWi-Fiなどで、通信を暗号化するための「VPN」の追加設定や、PCをWi-Fiアクセスポイントとして機能させる「モバイルホットスポット」の設定も、このカテゴリに含まれます。
個人用設定 (Personalization)
あなたのPCの「見た目」と「雰囲気」を、あなた色に染め上げるための、デザインスタジオです。
壁紙や配色テーマの変更はもちろん、「タスクバー」の項目では、アイコンの配置(中央揃えか、左揃えか)や、検索、タスクビューといったボタンの表示・非表示を切り替えることができます。
「スタート」メニューに表示するアプリをカスタマイズするなど、日々の使い勝手に直結する、重要な設定が集まっています。
アプリ (Apps)
PCにインストールされている、全てのアプリケーションの管理・監督を行います。
「インストールされているアプリ」からは、不要になったアプリのアンインストールが可能です。
そして、最も重要なのが「**スタートアップ**」の項目です。
PCの起動と同時に、裏で自動的に立ち上がるアプリを、ここで管理・無効化することができます。
不要なスタートアップアプリを無効にすることは、PCの起動を高速化し、メモリの消費を抑える上で、極めて効果的です。
アカウント (Accounts)
あなたのMicrosoftアカウント情報や、サインイン方法を管理します。
パスワードの代わりに、顔認証や指紋認証、あるいはPIN(暗証番号)でサインインするための「Windows Hello」の設定は、セキュリティと利便性を両立させる上で、非常に重要です。
時刻と言語 (Time & language)
日付と時刻の自動設定や、タイムゾーンの変更を行います。
「言語と地域」では、表示言語の追加や、キーボードのレイアウト(例:日本語キーボード、英語キーボード)の追加・切り替え設定が可能です。
複数の言語で入力を行うユーザーにとって、中心的な設定場所となります。
ゲーム (Gaming)
PCゲーム体験を最適化するための機能が集約されています。
`Win + G`で呼び出せる「Xbox Game Bar」の設定や、ゲームプレイの録画(キャプチャ)に関する設定、そして、PCのリソースをゲームに優先的に割り当てる「ゲームモード」のオン・オフを、ここで行います。
アクセシビリティ (Accessibility)
全てのユーザーが、PCを快適に利用できるようにするための、補助機能の設定項目です。
文字のサイズを大きくしたり、画面のコントラストを高くしたり、あるいは、不要なアニメーションをオフにして、システムの視覚的な負担を軽減したり、といった設定が可能です。
パフォーマンス向上のために、アニメーションや透明効果をオフにする、といった使い方も有効です。
プライバシーとセキュリティ (Privacy & security)
あなたの個人情報と、PCの安全を守るための、最も重要な要塞です。
「Windows セキュリティ」からは、ウイルス対策やファイアウォールの状態を確認できます。
そして、その下にある「アプリのアクセス許可」のセクション。
ここでは、「場所」「カメラ」「マイク」といった、プライベートな情報へのアクセスを、どのアプリに許可するのかを、一つずつ、厳格に管理・制限することができます。
定期的にこの項目を見直し、不要な許可を与えているアプリがないかを確認する習慣は、現代のデジタルリテラシーとして、必須のものです。
Windows Update
OSを、常に最新で、最も安全な状態に保つための、アップデート管理を行います。
「更新の履歴」からは、これまでに適用されたアップデートの詳細を確認できます。
また、「詳細オプション」では、アップデートの再起動時間を、アクティブな時間帯を避けるように設定したり、オプションの更新プログラム(ドライバーの更新など)を、手動でインストールしたりすることができます。
第二章:旧市街の探索 - 今なお健在な「コントロールパネル」の役割
この新しい「設定」アプリへの機能移行は、現在も進行中のプロジェクトです。
そのため、一部の、特に古くからある、あるいは非常に詳細な設定項目は、今なお、旧来の「コントロールパネル」の中にしか、存在しません。
例えば、電源プランを、より細かくカスタマイズするための「電源オプション」の詳細設定や、特定のファイル拡張子とプログラムの関連付け、あるいは、旧来の「プログラムと機能」からのアンインストールなどです。
スタートメニューで「コントロールパネル」と検索すれば、いつでも、この懐かしい、しかし今なお強力な、旧市街を訪れることができます。
「設定」アプリで目的の項目が見つからない場合は、コントロールパネルの中を探してみる。
これが、Windows 11を使いこなす上での、一つの重要なテクニックです。
第三章:究極のショートカット - 「ms-settings:」URIコマンドによる直接アクセス
ここからは、あなたの設定画面へのアクセス速度を、別次元へと引き上げる、専門家向けの究極のテクニックを紹介します。
Windows 11の「設定」アプリの、各ページには、実は、ウェブサイトのアドレス(URL)のような、固有の「住所」が割り当てられています。
これが、「`ms-settings:`」で始まる、URI(Uniform Resource Identifier)コマンドです。
このコマンドを使えば、左側のカテゴリメニューを、何度もクリックして辿る必要なく、目的の設定画面を一瞬で、直接、呼び出すことができます。
使い方は簡単です。
キーボードの「`Windowsキー + R`」を押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログボックスを開き、そこに、目的のコマンドを入力して、エンターキーを押すだけです。
以下に、特に使用頻度が高く、便利なコマンドの一覧を示します。
- ・`ms-settings:display` - ディスプレイ設定
- ・`ms-settings:powersleep` - 電源とバッテリー
- ・`ms-settings:storagesense` - ストレージセンサー
- ・`ms-settings:startupapps` - スタートアップアプリ
- ・`ms-settings:appsfeatures` - インストールされているアプリ
- ・`ms-settings:network-wifi` - Wi-Fi設定
- ・`ms-settings:bluetooth` - Bluetoothとデバイス
- ・`ms-settings:personalization-background` - 背景の個人用設定
- ・`ms-settings:taskbar` - タスクバーの設定
- ・`ms-settings:privacy-webcam` - カメラのプライバシー設定
- ・`ms-settings:privacy-microphone` - マイクのプライバシー設定
- ・`ms-settings:windowsupdate` - Windows Update
さらに、このコマンドは、デスクトップ上に「ショートカット」として保存することも可能です。
デスクトップで右クリック > 「新規作成」 > 「ショートカット」を選択し、「項目の場所を入力してください」の欄に、例えば「`ms-settings:bluetooth`」と入力し、分かりやすい名前(例:「Bluetooth設定」)を付けて保存します。
これにより、あなたが最も頻繁にアクセスする設定画面への、ワンクリックでのアクセスが可能な、あなただけの「専用ボタン」が完成します。
まとめ:設定アプリを制する者は、Windows 11を制する
Windows 11の「設定」アプリは、単なるカスタマイズツールではありません。
それは、あなたのPCのパフォーマンス、セキュリティ、プライバシー、そして日々の使い勝手の全てを、あなた自身の手に取り戻すための、統合されたコントロールセンターです。
- ・まず、全体像を把握する: 11の主要カテゴリが、どのような役割分担になっているのか。この論理的な構造を理解することが、迷子にならないための、最初の地図となります。
- ・特に重要な設定項目を覚える: 「スタートアップアプリ」「アプリのアクセス許可」「ストレージセンサー」「電源モード」。これらの、PCの健全性に直結する項目は、定期的に見直す習慣をつけましょう。
- ・旧市街(コントロールパネル)の存在を忘れない: 新しい「設定」アプリにない、より深い設定項目は、今なお「コントロールパネル」の中に眠っています。二つの場所を、自在に行き来できるのが、パワーユーザーの証です。
- ・「`ms-settings:`」コマンドで、時間を買う: 頻繁にアクセスする設定画面へは、この究極のショートカットコマンドを使い、クリックの回数を、そして人生の貴重な時間を、節約しましょう。
あなたのPCは、あなたが設定した通りにしか、動きません。
ぜひ、この記事を片手に、あなただけの、最も快適で、最も安全で、そして最も効率的な、Windows 11環境を、あなた自身の力で、構築してください。

パソコン購入のためのお役立ち情報
パソコン選びがよく分からない方、ご不安のある方、悩む前に!お気軽にご相談ください!
専門スタッフが、性能・ご予算・お好みなどご希望に合ったパソコンをお探しします!



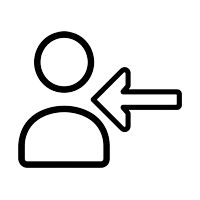 ログイン
ログイン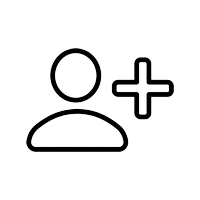 新しくアカウントを作成する
新しくアカウントを作成する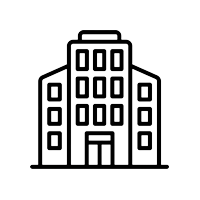 会社概要
会社概要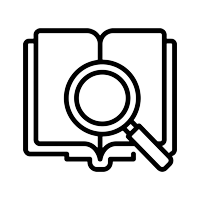 ご利用ガイド
ご利用ガイド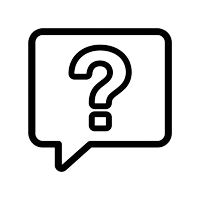 よくあるご質問
よくあるご質問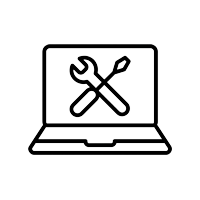 パソコン修理
パソコン修理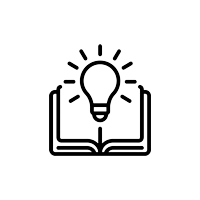 お役立ち情報
お役立ち情報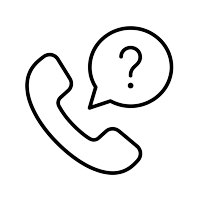 お問い合わせ
お問い合わせ 特定商取引に基づく表示
特定商取引に基づく表示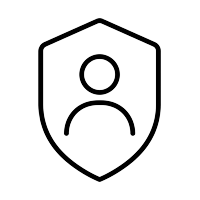 個人情報保護ポリシー
個人情報保護ポリシー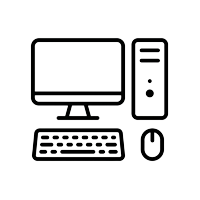 デスクトップパソコン
デスクトップパソコン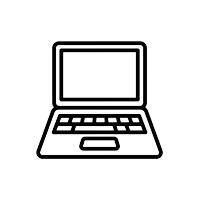 ノートパソコン
ノートパソコン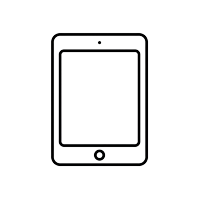 タブレット
タブレット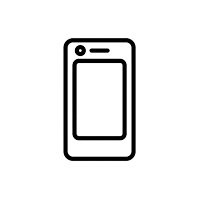 スマートフォン
スマートフォン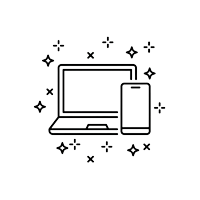 新品(Aランク)
新品(Aランク)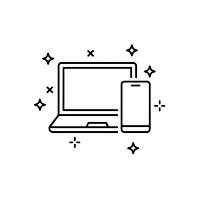 美品(Bランク)
美品(Bランク)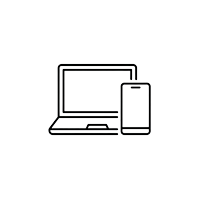 中古(Cランク)
中古(Cランク)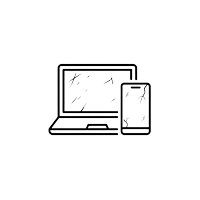 訳あり(Dランク)
訳あり(Dランク)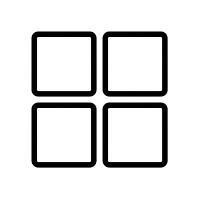 Windows 11
Windows 11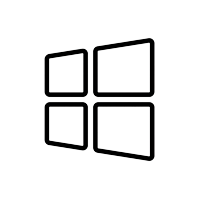 Windows 10
Windows 10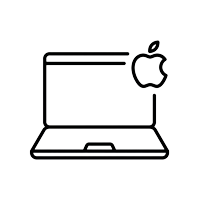 Mac OS
Mac OS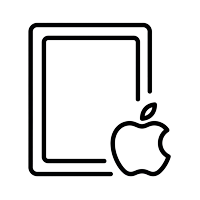 iPad OS
iPad OS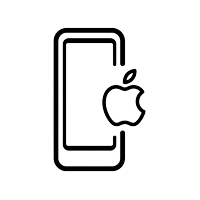 iOS
iOS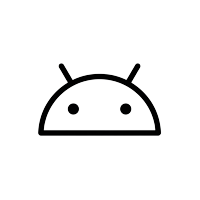 Android
Android コンシューマーモデル
コンシューマーモデル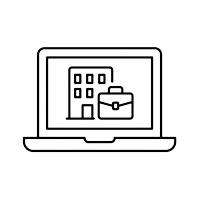 ビジネスモデル
ビジネスモデル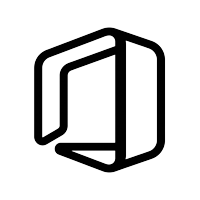 Microsoft Office搭載
Microsoft Office搭載 WPS Office搭載
WPS Office搭載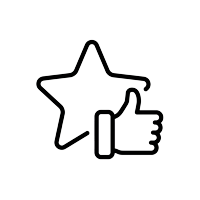 おすすめ商品
おすすめ商品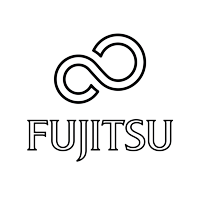
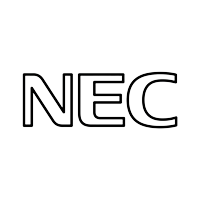
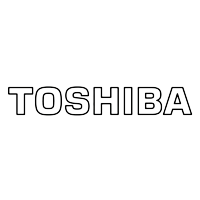


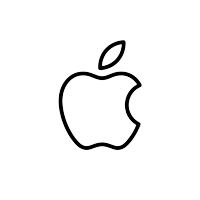


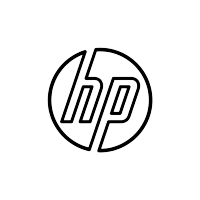
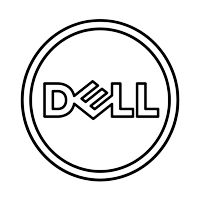

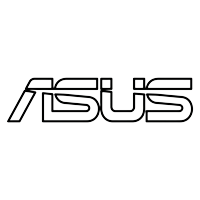
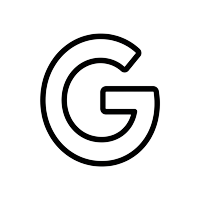

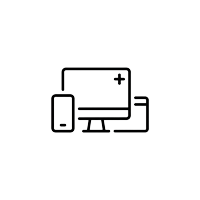
 Celeron|Athlon
Celeron|Athlon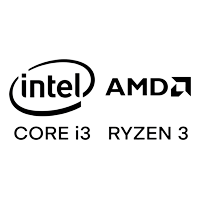 Core i3|Ryzen 3
Core i3|Ryzen 3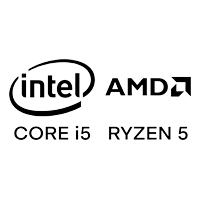 Core i5|Ryzen 5
Core i5|Ryzen 5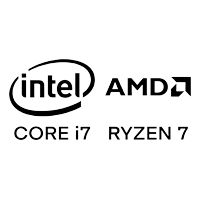 Core i7|Ryzen 7
Core i7|Ryzen 7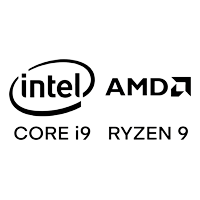 Core i9|Ryzen 9
Core i9|Ryzen 9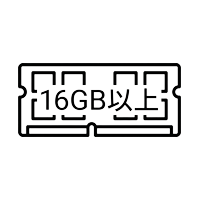 メモリ16GB以上
メモリ16GB以上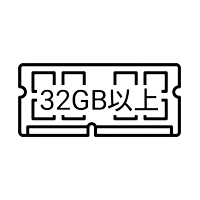 メモリ32GB以上
メモリ32GB以上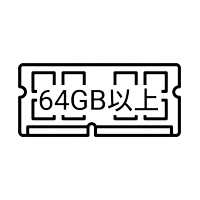 メモリ64GB以上
メモリ64GB以上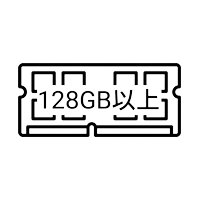 メモリ128GB以上
メモリ128GB以上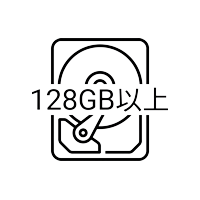 ストレージ128GB以上
ストレージ128GB以上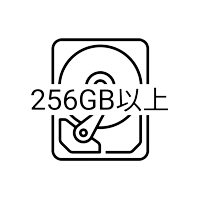 ストレージ256GB以上
ストレージ256GB以上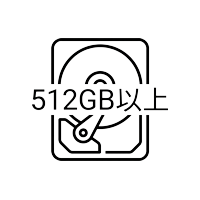 ストレージ512GB以上
ストレージ512GB以上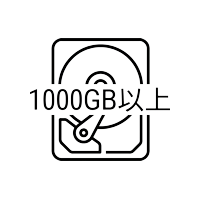 ストレージ1000GB以上
ストレージ1000GB以上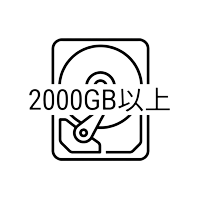 ストレージ2000GB以上
ストレージ2000GB以上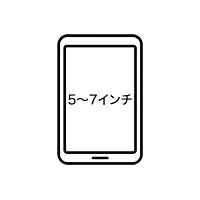 5〜7インチ
5〜7インチ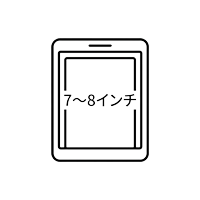 7〜8インチ
7〜8インチ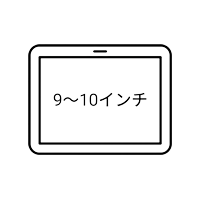 9〜10インチ
9〜10インチ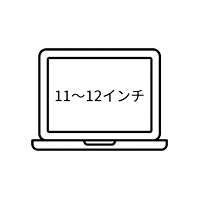 11〜12インチ
11〜12インチ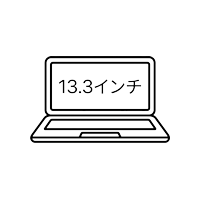 13.3インチ
13.3インチ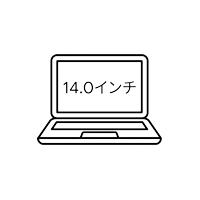 14.0インチ
14.0インチ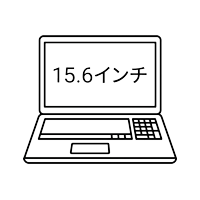 15.6インチ
15.6インチ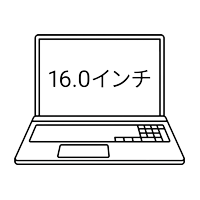 16.0インチ
16.0インチ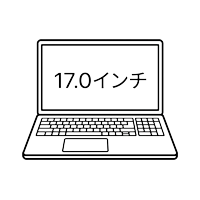 17.0インチ以上
17.0インチ以上




