
Wordで作るパンフレット!デザインから印刷まで
Officeのお役立ち情報

記事の最終更新日:2025年7月11日
今度、地域のイベントで、サークルの紹介をするための三つ折りのパンフレットを作ることになったんです。
でも、私たちが使えるソフトは、Microsoft Wordしかなくて…。
Wordにテンプレートがあるのは知っているのですが、デザインが少し古かったり、写真や文章を思うように配置できなかったりして、なかなかプロが作ったような、洗練された感じになりません。
そもそも、Wordで、デザイン性の高いパンフレットを自由にレイアウトすること自体、難しいのでしょうか?
用紙の設定から、デザインのコツ、そして、最終的に印刷会社に入稿できるような、きちんとしたデータを作成するまでの、一連の流れを教えてほしいです。
その挑戦、素晴らしいですね。
そして、多くの方が誤解していますが、Wordの真の力は、ビジネス文書の作成だけには留まりません。
その内部には、プロのデザイナーが使うDTPソフト(※注釈:InDesignやIllustratorのような、専門的な印刷物デザインソフト)にも匹敵する、高度なレイアウト機能が、実は隠されているのです。
その力を解き放つ鍵は、Wordを「文章作成ソフト」としてではなく、「**ページレイアウトソフト**」として捉え直す、という、意識の転換にあります。
「段組み」でページの骨格を作り、「テキストボックス」で文章の配置を完全にコントロールし、「図形の書式設定」でデザインの細部を追い込む。
この記事では、そのためのプロフェッショナルな思考法と、具体的な操作手順、さらには、印刷で失敗しないための「入稿データ」の作成ノウハウまで、あなたのWordを、最強のパンフレットデザインツールへと変貌させるための、全ての知識と技術を、体系的に解説していきます。
Wordデザインの哲学:あなたは「文筆家」ではなく「建築家」である
Microsoft Wordで、パンフレットのような、デザイン性が求められる印刷物を作成する際、私たちは、マインドセットを切り替える必要があります。
あなたは、物語を紡ぐ「文筆家」ではありません。
あなたは、テキスト、画像、図形といった、様々な素材を、限られた紙面の中に、機能的に、そして美しく配置していく、「建築家」あるいは「インテリアデザイナー」なのです。
文章が、ページの端から端まで、自動で流れていく、というWordの基本的なお作法は、一旦、忘れましょう。
代わりに、ページという「敷地」の上に、段組みという「骨格」を建て、テキストボックスや図形という「家具」を、ミリ単位で、意のままに配置していく。
この、DTP的な発想を持つことこそが、Wordという、ありふれたツールを使いながら、プロフェッショナルな成果物を生み出すための、最も重要な第一歩なのです。
第一章:設計図を描く - 成功する三つ折りパンフレットの構造計画
優れたパンフレットは、その作成の前に、周到な計画があります。
誰に、何を伝え、そして、どんな行動を促したいのか。
そして、その情報を、三つ折りという、6つの「面」で構成される、特殊なメディアの上に、どのように配置していくのか。
この設計図の質が、パンフレットの成否を決定づけます。
A4用紙を横向きにして、Z字型に三つ折りにする、最も一般的なパンフレットを例に、各面の役割を理解しましょう。
【外面:最初に目にする、興味を引くための3面】
- ・表紙(外面の右端): パンフレットが折られた状態で、最初に顧客の目に触れる、最も重要な面です。魅力的なキャッチコピー、美しいビジュアル、そしてロゴを配置し、「手に取って、開いてみたい」と思わせる必要があります。
- ・裏表紙(外面の中央): 最後の面に配置され、連絡先、地図、ウェブサイトのURLやQRコード、事業者の基本情報といった、問い合わせや次のアクションに繋げるための、詳細情報を記載します。
- ・中面への導入(外面の左端): 表紙を開いた時に、最初に現れる面です。中面で展開される内容への、興味を掻き立てるような、簡潔な導入文や、問いかけなどを配置します。
【中面:詳細情報を展開し、理解を深めるための3面】
- ・左面・中央面・右面: パンフレットを完全に開いた時に、一体として表示される、メインのコンテンツエリアです。サービスの詳細、商品の特徴、イベントのスケジュールといった、最も伝えたい情報を、複数の見出しや、写真、図解などを駆使して、分かりやすく、魅力的に展開します。
この6つの面の役割と、情報の流れを意識して、コンテンツを準備することが、後のデザイン作業を、スムーズに進めるための鍵となります。
第二章:土地の造成と骨組み - Word文書の基本設定
設計図が完成したら、いよいよWordという土地に、パンフレットという建物を建てるための、基礎工事と、骨組みの建設に入ります。
ステップ1:ページ設定(用紙の向きと余白)
まず、Wordのページを、パンフレットに適した状態に設定します。
「レイアウト」タブを開き、「印刷の向き」を「**横**」に変更します。
次に、「余白」をクリックし、「狭い」を選択するか、あるいは「ユーザー設定の余白」から、上下左右の余白を、可能な限り(例:10mm程度)小さく設定します。
これにより、限られた紙面を、最大限に活用するための、広い敷地が確保できます。
ステップ2:段組み(コラム)の設定
ここが、WordをDTPツールとして使うための、最初の、そして最も重要なステップです。
三つ折りパンフレットを作成するため、ページを、3つの「段(コラム)」に分割します。
「レイアウト」タブ > 「段組み」 > 「3段」を選択します。
これだけでは、ただ文章が3つの段に流し込まれるだけですが、さらに、プロフェッショナルな仕上がりのために、詳細設定を行います。
再度、「段組み」>「段組みの詳細設定」を開きます。
ここで、「**境界線を引く**」というチェックボックスをオンにしてみてください。
すると、各段の間に、折り目の目安となる、細い縦線が自動で表示されます。
また、「間隔」の数値を調整することで、各段の間の、余白の幅を、精密にコントロールすることができます。
第三章:内装工事 - テキストボックスと図形を駆使した、自由なレイアウト
骨組みが完成したら、次は、各部屋に、壁紙を貼り、家具(コンテンツ)を配置していく、内装工事の段階です。
ここで、Wordの「文章作成ソフト」としての常識を捨て、「**テキストボックス**」を、あなたの主要な武器として使います。
なぜ「テキストボックス」が最強の武器なのか
段組みを設定しただけのページに、直接、文章を打ち込んでいくと、テキストは、上の段から下の段へ、あるいは、左の段から右の段へと、滝のように、自動で流れ込んでしまいます。
これでは、各面が独立したパンフレットのレイアウトを、意図通りに作成することはできません。
そこで、「挿入」タブ > 「テキストボックス」>「横書きテキストボックスの描画」を選択し、6つの各パネルに相当する領域に、それぞれ独立したテキストボックスを配置していくのです。
テキストボックスは、それぞれが、独立した小さな「文書」のように振る舞います。
中のテキストは、他のテキストボックスにはみ出すことはありません。
そして、テキストボックス自体は、まるで図形のように、ページ上の任意の位置に、自由に移動させたり、サイズを変更したりできます。
さらに、枠線の色や太さ、背景の塗りつぶしの色も、自在に設定可能です。
この、テキストボックスで「区画」を作り、その中にコンテンツを流し込んでいく、という手法こそが、Wordで、自由なレイアウトを実現するための、絶対的な基本にして、奥義なのです。
画像の配置と「文字列の折り返し」のマスター
パンフレットに、写真やイラストといった画像を配置する際、その挙動を完全にコントロールするための鍵が、「文字列の折り返し」設定です。
画像を挿入し、その画像を選択すると表示される、「図の形式」タブ(または、右クリックメニュー)から、「文字列の折り返し」を選択します。
デフォルトの「行内」では、画像は、巨大な一文字のように扱われ、レイアウトの自由度がありません。
ここで、「**四角**」や「**外周**」、「**前面**」といった、別のオプションを選択します。
これにより、画像は、テキストの制約から解放され、ページ上の任意の位置に、自由にドラッグして配置できるようになります。
特に「前面」を選択すれば、画像は、他の全てのテキストや図形の上に、完全に自由に配置できます。
この設定をマスターすることで、テキストと画像が、互いに美しく、そして機能的に共存する、洗練されたレイアウトが、初めて可能になります。
第四章:竣工検査 - 印刷会社に入稿するための「プロの常識」
美しいデザインが完成しても、それが、印刷会社の求める仕様を満たしていなければ、意図通りの仕上がりにはなりません。
自宅のプリンターで印刷するだけなら問題ありませんが、プロの印刷会社に発注する場合には、いくつかの「専門的な常識」を知っておく必要があります。
色の表現方式:RGBとCMYK
PCのモニターが表示する色は、光の三原色である「RGB(赤・緑・青)」で表現されています。
一方、印刷所で使われるインクは、色の三原色に黒を加えた「CMYK(シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック)」で表現されます。
Wordは、基本的にRGBで色を管理しているため、画面上で見えている鮮やかな色が、CMYKで印刷された際に、わずかにくすんだ、あるいは沈んだ色合いに変化することがあります。
これは、Wordで印刷物を作成する上での、避けられない制約の一つとして、念頭に置いておく必要があります。
画像の解像度:300dpiという最低ライン
ウェブサイトで使われているような、低解像度の画像(一般的に72dpi)を、そのまま印刷物に使用すると、画像は、ぼやけて、ギザギザした、非常に見栄えの悪いものになってしまいます。
美しい印刷品質を得るためには、使用する画像の解像度が、**最低でも「300dpi」**(1インチあたりに、300個のドットがある、の意)であることが、強く推奨されます。
パンフレットに使用する写真は、必ず、元データの時点で、十分に高解像度なものを用意してください。
塗り足し(裁ち落とし)への配慮
パンフレットの端まで、背景色や写真が配置されているデザインの場合、「塗り足し(ぬりたし)」、あるいは「裁ち落とし(たちおとし)」と呼ばれる、特別なデータ作成の作法が必要になります。
これは、印刷後の断裁時に、わずかなズレが生じても、紙の端に、意図しない白いフチが出ないように、あらかじめ、仕上がりサイズよりも3mm程度、外側まで、背景や画像をはみ出させておく、という、プロの印刷業界の常識です。
Wordには、この「塗り足し」を自動で設定する機能はありません。
そのため、対応策としては、A4サイズのパンフレットを作る場合、用紙設定を、A4よりも一回り大きいカスタムサイズに設定し、その上で、仕上がり線(A4のサイズ)と、裁ち落とし線(さらに3mm外側)のガイドを、自分で引いて、デザインを行う、といった、高度なテクニックが必要になります。
あるいは、デザインの段階で、紙のフチぎりぎりまで、要素を配置しない、という割り切りも、一つの賢明な判断です。
最終納品形式:高品質なPDFでの書き出し
印刷会社に入稿するデータは、Wordファイル(`.docx`)のままではなく、全てのレイアウトやフォント情報が、完全に固定された、**PDF(Portable Document Format)**形式に変換するのが、絶対のルールです。
「ファイル」>「エクスポート」>「PDF/XPSドキュメントの作成」を選択します。
保存ダイアログの「最適化」の項目で、「標準(オンライン発行および印刷)」が選択されていることを確認してください。
これにより、印刷に適した、高品質なPDFファイルが生成されます。
まとめ:Wordは、あなたの創造力次第で、プロのデザインツールに化ける
Microsoft Wordは、多くの人が、その表面的な機能しか触れることのない、計り知れないポテンシャルを秘めた、巨大なツールボックスです。
その真価は、あなたが「できない」と諦める前に、「どうすればできるか?」と考え、その奥深い機能を探求し始めた時に、初めて、その姿を現します。
- ・思考を切り替える: Wordを、文章作成ソフトではなく、「ページレイアウトソフト」として捉え直す。この意識改革が、全ての始まりです。
- ・骨格は「段組み」で創る: 三つ折りパンフレットの基本構造は、「横向き・3段・境界線あり」の設定で、まず、その骨格を正確に構築します。
- ・レイアウトは「テキストボックス」で支配する: 文章や画像を、ページ上の意図通りの場所に、自由に配置するための、最強の武器は、テキストボックスです。これを制する者が、Wordレイアウトを制します。
- ・印刷の「作法」を尊重する: 高解像度の画像(300dpi)、塗り足しへの配慮、そして、最終納品形式としての高品質PDF。これらの、プロの印刷業界の作法を学ぶことが、あなたの成果物の品質を、保証します。
専用のデザインソフトがなければ、プロフェッショナルなパンフレットは作れない、というのは、もはや過去の思い込みです。
あなたの目の前にある、その使い慣れたWordというツールに、まだあなたが知らない、無限の力が眠っています。
この記事を手に、その力を解き放ち、あなたのアイデアやメッセージを、人の心を動かす、美しい形へと、ぜひ昇華させてください。

パソコン購入のためのお役立ち情報
パソコン選びがよく分からない方、ご不安のある方、悩む前に!お気軽にご相談ください!
専門スタッフが、性能・ご予算・お好みなどご希望に合ったパソコンをお探しします!



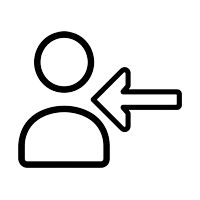 ログイン
ログイン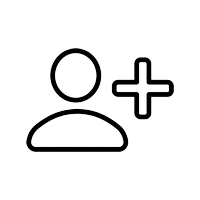 新しくアカウントを作成する
新しくアカウントを作成する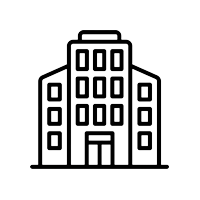 会社概要
会社概要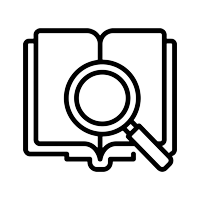 ご利用ガイド
ご利用ガイド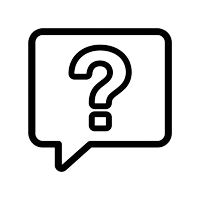 よくあるご質問
よくあるご質問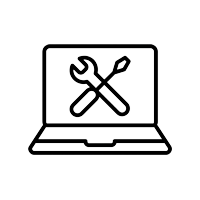 パソコン修理
パソコン修理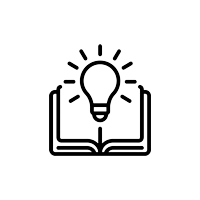 お役立ち情報
お役立ち情報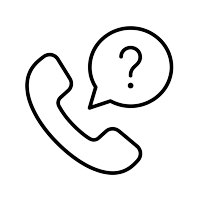 お問い合わせ
お問い合わせ 特定商取引に基づく表示
特定商取引に基づく表示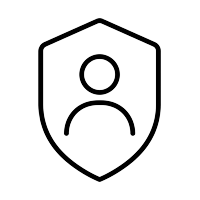 個人情報保護ポリシー
個人情報保護ポリシー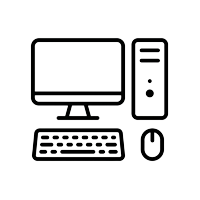 デスクトップパソコン
デスクトップパソコン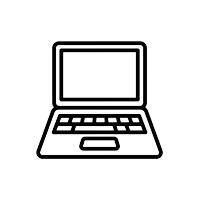 ノートパソコン
ノートパソコン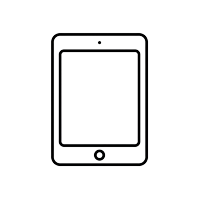 タブレット
タブレット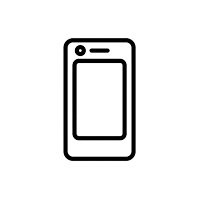 スマートフォン
スマートフォン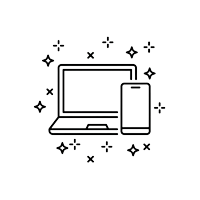 新品(Aランク)
新品(Aランク)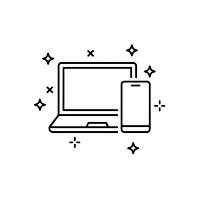 美品(Bランク)
美品(Bランク)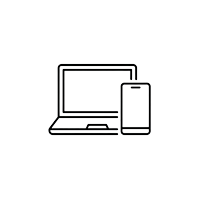 中古(Cランク)
中古(Cランク)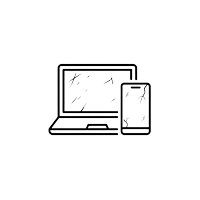 訳あり(Dランク)
訳あり(Dランク)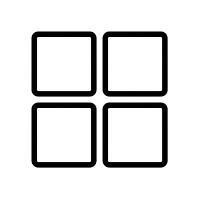 Windows 11
Windows 11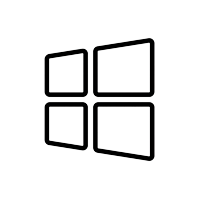 Windows 10
Windows 10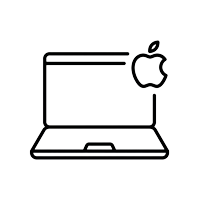 Mac OS
Mac OS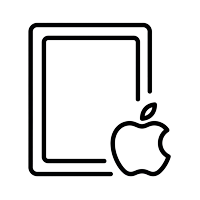 iPad OS
iPad OS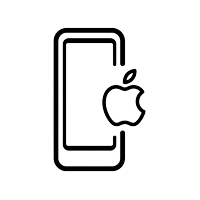 iOS
iOS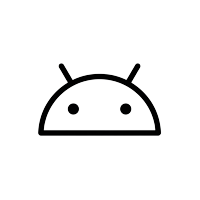 Android
Android コンシューマーモデル
コンシューマーモデル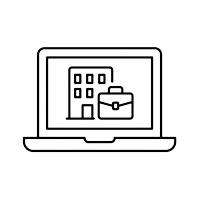 ビジネスモデル
ビジネスモデル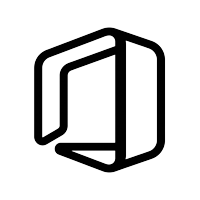 Microsoft Office搭載
Microsoft Office搭載 WPS Office搭載
WPS Office搭載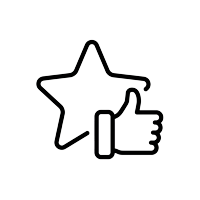 おすすめ商品
おすすめ商品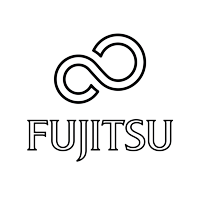
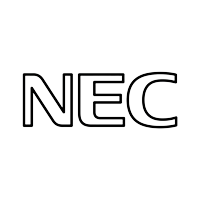
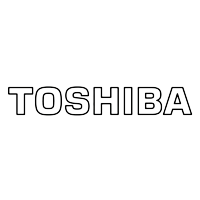


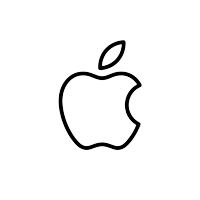


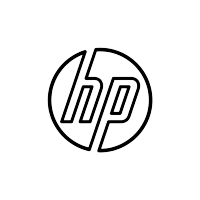
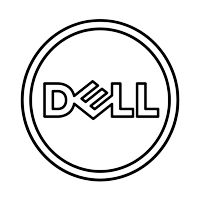

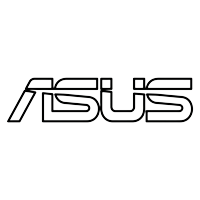
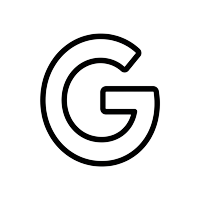

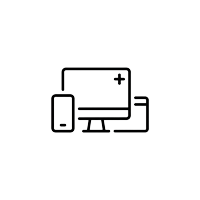
 Celeron|Athlon
Celeron|Athlon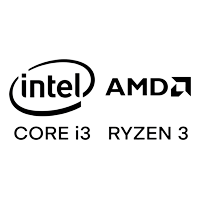 Core i3|Ryzen 3
Core i3|Ryzen 3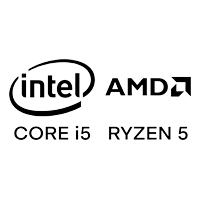 Core i5|Ryzen 5
Core i5|Ryzen 5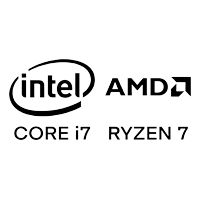 Core i7|Ryzen 7
Core i7|Ryzen 7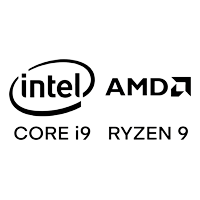 Core i9|Ryzen 9
Core i9|Ryzen 9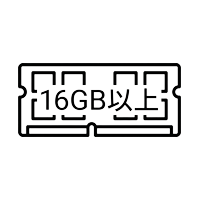 メモリ16GB以上
メモリ16GB以上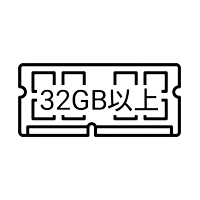 メモリ32GB以上
メモリ32GB以上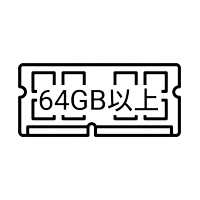 メモリ64GB以上
メモリ64GB以上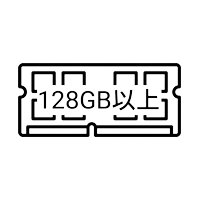 メモリ128GB以上
メモリ128GB以上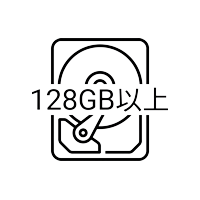 ストレージ128GB以上
ストレージ128GB以上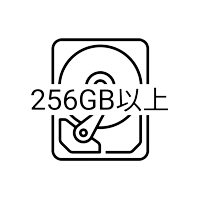 ストレージ256GB以上
ストレージ256GB以上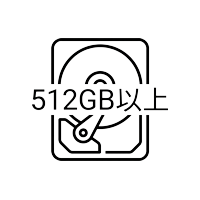 ストレージ512GB以上
ストレージ512GB以上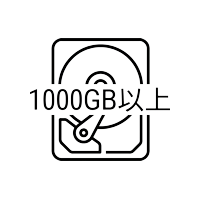 ストレージ1000GB以上
ストレージ1000GB以上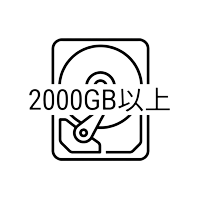 ストレージ2000GB以上
ストレージ2000GB以上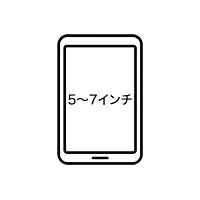 5〜7インチ
5〜7インチ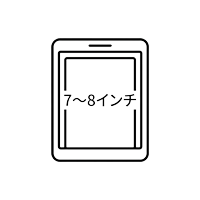 7〜8インチ
7〜8インチ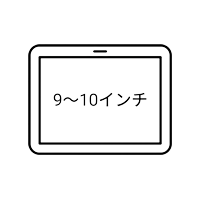 9〜10インチ
9〜10インチ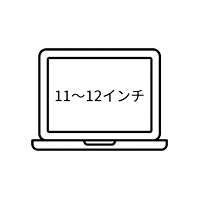 11〜12インチ
11〜12インチ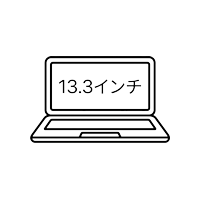 13.3インチ
13.3インチ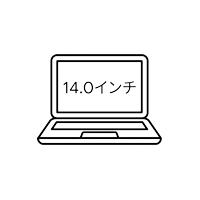 14.0インチ
14.0インチ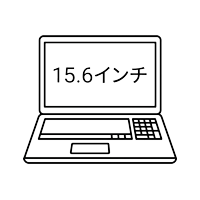 15.6インチ
15.6インチ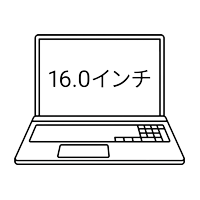 16.0インチ
16.0インチ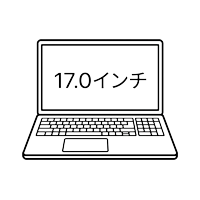 17.0インチ以上
17.0インチ以上




