
中古パソコンのハードディスククローン作成ガイド
パソコン全般のお役立ち情報

記事の最終更新日:2025年7月11日
使っている中古ノートパソコンの動作が遅いので、HDDをSSDに交換して、高速化したいんです。
でも、一番の悩みは、その後の再設定です。
Windowsを再インストールして、今まで使っていたたくさんのソフトを一つ一つ入れ直して、細かい設定も全部やり直して…と考えると、それだけで何日もかかってしまいそうで、気が遠くなります。
今のOSやソフト、データ、設定などを、環境を丸ごと、そっくりそのまま、新しいSSDに「お引越し」させるような、魔法みたいな方法はないのでしょうか?
そのお悩み、そして、その理想、よく分かります。
そして、あなたが求める「魔法」は、ちゃんと存在します。
それが、「ディスククローン作成」という、高度な技術です。
これは、例えるなら、お使いのPCの「脳移植手術」。
古いHDDという身体から、OS、アプリケーション、設定、そしてあなたの全てのデータという「意識」と「記憶」を、一滴も漏らさず、新しいSSDという、若く、高性能な身体へと、完全に移植するのです。
移植が終われば、PCは、何も変わらない使い慣れた環境のまま、まるで10歳若返ったかのような、驚異的なパフォーマンスを発揮し始めます。
この記事では、その「脳移植手術」を成功させるための、術前の準備(必要な道具)、執刀手順(クローン作成ソフトウェアの使い方)、そして術後のケア(最終設定)まで、専門医のように、緻密かつ体系的に、その全手順を解説していきます。
クローニングの思想:それは「時間」という最も貴重な資産を守る技術
パソコンのストレージ(HDDやSSD)を交換する際、多くの人が直面する最大の壁は、物理的な交換作業そのものではありません。
それは、OSの再インストールと、それに続く、無数のアプリケーションの再インストール、そして、長年かけて自分仕様に育て上げてきた、細かな設定の再現という、膨大で、退屈で、そして創造性の欠片もない、時間の浪費です。
ディスククローン作成という技術の本質は、この最も価値のある、しかし失われやすい「時間」という資産を、完璧に守ることにあります。
環境の再構築にかかる、数時間、あるいは数日にも及ぶ時間を、完全にゼロにする。
それは、あなたが、より早く、新しい、快適なPC環境での、創造的な活動へと復帰することを可能にする、極めて強力な、そして合理的な投資なのです。
バックアップが「万が一のための保険」であるならば、クローン作成は、「より良い未来へと、最短距離で移行するための、戦略的なワープ航法」と言えるでしょう。
第一章:術前準備 - 完璧なクローン作成のための道具と知識
高度な手術には、正確な知識と、適切な道具が不可欠です。
クローン作成を始める前に、以下の準備を万全に整えてください。
ステップ1:新しい身体(SSD)の選定
まず、移植先となる新しいSSDを選びます。
重要なのは、その「フォームファクター(形状)」と「インターフェース(接続規格)」です。
- ・SATA 2.5インチSSD: 従来のHDDと全く同じ、2.5インチの箱型の形状をしています。ほとんどのノートパソコンや、全てのデスクトップPCで利用できる、最も汎用性の高いタイプです。
- ・M.2 (エムドットツー) SSD: メモリのような、細長い基板状のSSDです。薄型ノートPCや、近年のデスクトップPCのマザーボードに搭載されています。M.2には、SATA接続のものと、さらに高速な**NVMe(エヌブイエムイー)**接続のものがあり、お使いのPCがどちらの規格に対応しているか、事前に仕様を確認する必要があります。
容量は、現在お使いのドライブの使用量よりも、十分に大きいものを選びましょう。
一般的には、500GB~1TB程度の容量があれば、当面の利用で困ることは少ないでしょう。
ステップ2:生命維持装置(接続ハードウェア)の用意
クローン作成のプロセスでは、古いドライブと新しいドライブを、PCに「同時に」接続する必要があります。
デスクトップPCの場合は、ケース内に空いているSATAポートと電源コネクタがあれば、そこに新しいドライブを接続するだけです。
しかし、ノートパソコンの場合は、以下のいずれかの外付け用変換ツールが、必須となります。
- ・USB-SATA変換アダプター/ケース: 新しいドライブがSATA 2.5インチSSDの場合に必要です。SSDをこのアダプターに接続し、PCのUSBポートに繋ぎます。
- ・M.2 NVMe SSD to USBエンクロージャー(外付けケース): 新しいドライブがM.2 NVMe SSDの場合に必要です。SSDをこのケースに組み込み、USBでPCに接続します。
これらのツールは、いわば、移植手術中に、新しい身体(SSD)に血液を送り込むための、生命維持装置の役割を果たします。
ステップ3:執刀医(クローニングソフトウェア)の選定
ディスクのクローン作成は、専用のソフトウェアを使って行います。
- ・SSDメーカー提供の無料ツール: Samsung(Data Migration)、Crucial(Acronis True Image for Crucial)、Western Digital(Acronis True Image WD Edition)といった、多くの主要なSSDメーカーは、自社製品のユーザー向けに、高機能なクローニングソフトウェアを無料で提供しています。あなたが購入したSSDのメーカーが、こうしたツールを提供している場合、それを利用するのが、最も簡単で確実な方法です。
- ・高機能なサードパーティ製フリーソフト: より高度な機能を求める上級者の間では、「Macrium Reflect Free Edition」や、Linuxベースのブータブルツールである「Clonezilla」といった、無料で利用できる、非常に強力なソフトウェアも広く使われています。
第二章:執刀 - クローン作成プロセスのステップ・バイ・ステップ
全ての準備が整ったら、いよいよ、最も重要なクローン作成のプロセスに入ります。
ここでは、最も一般的な、ノートパソコンのHDDを、USB変換アダプター経由で接続した新しいSSDへとクローンする手順を例に解説します。
ステップ1:新しいドライブの初期化と認識
新品のSSDを、変換アダプターを介してPCのUSBポートに接続しても、最初はエクスプローラーに表示されません。
まず、Windowsに、新しいドライブの存在を認識させる「初期化」という儀式が必要です。
「ディスクの管理」ツール(スタートボタンを右クリックして選択)を起動すると、「ディスクの初期化」ダイアログが自動で表示されるはずです。
パーティションのスタイルとして、「GPT(GUIDパーティションテーブル)」と「MBR(マスターブートレコード)」の選択を求められます。
基本的には、現在のシステムドライブ(C:ドライブ)と同じスタイルを選択するのが安全です。(ディスクの管理で、既存のディスクを右クリックし、プロパティの「ボリューム」タブで確認可能)
近年のPCは、ほぼ全てGPTです。
ステップ2:クローニングソフトウェアの実行とディスクの選択
クローニングソフトウェアを起動し、クローン作成の機能を選択します。
画面には、PCに接続されている全てのドライブが表示されます。
ここで、**細心の注意を払って**、以下の二つを選択します。
- ・ソースディスク(コピー元): あなたの現在のシステムドライブ(OSがインストールされている、古いHDD)を選択します。
- ・デスティネーションディスク(コピー先): 新しく接続した、空のSSDを選択します。
この選択を間違えると、**大切なデータが入っている元のドライブが、空のドライブの内容で上書きされ、全て消去されてしまいます。**
ドライブの名称や容量をよく確認し、絶対に間違えないようにしてください。
ステップ3:パーティションサイズの調整(大容量ドライブへのクローン)
新しいSSDが、元のHDDよりも大容量である場合、クローン作成ソフトは、パーティション(※注釈:ドライブ内の論理的な仕切り)のサイズをどうするか、尋ねてくることがあります。
そのままクローンすると、元のドライブと同じサイズのパーティションが作成され、残りの領域が「未割り当て」のままになってしまうことがあります。
多くのソフトウェアでは、クローン設定画面で、コピー先のパーティションのサイズを、グラフィカルにドラッグして、新しいドライブの最大容量まで広げることができます。
この調整を行うことで、新しいSSDの全ての容量を、無駄なく利用することが可能になります。
全ての確認が完了したら、「開始」や「実行」といったボタンを押し、クローン作成プロセスを開始します。
データの容量にもよりますが、この処理には数十分から数時間かかります。
完了するまで、PCの電源が落ちないよう、ACアダプターを接続したまま、静かに待ちます。
第三章:移植手術 - 物理的なドライブの交換
クローン作成が、100%成功したことを確認したら、いよいよ物理的な「移植手術」です。
PCの電源を完全にシャットダウンし、ACアダプターとバッテリー(取り外し可能な場合)を外します。
静電気によるパーツの破損を防ぐため、作業前には、金属製のドアノブなどに触れて、身体の静電気を放電しておきましょう。
ノートパソコンの裏蓋のネジを、精密ドライバーを使って慎重に外し、内部にアクセスします。
通常、2.5インチのドライブは、数本のネジでマウンターに固定されています。
SATAコネクタと電源コネクタをそっと外し、古いドライブを取り出します。
そして、先ほどクローンを作成した新しいSSDを、全く逆の手順で取り付け、裏蓋を閉じれば、手術は完了です。
第四章:術後の経過観察 - 起動確認と最終調整
全ての作業を終え、初めてPCの電源を入れる瞬間は、緊張するものです。
無事に、見慣れたWindowsのロゴが表示され、デスクトップが起動すれば、脳移植手術は成功です。
もし、正常に起動しない場合は、一度、再起動してBIOS/UEFI設定画面に入り、「Boot(ブート)」の項目で、起動ドライブの優先順位が、新しいSSDになっているかを確認してください。
起動を確認したら、最後にもう一手間だけ、最適化を行います。
「ドライブの最適化」ツールを起動し、新しいSSDが正しく「ソリッドステートドライブ」として認識され、TRIM(※注釈:SSDのパフォーマンスを維持するための必須機能)が有効になっていることを確認します。
通常は自動で認識されますが、もし最適化が必要と表示されていれば、実行しておきましょう。
これで、あなたのPCは、古い記憶を全て受け継いだまま、新しい、高速な身体を手に入れ、生まれ変わったのです。
取り外した古いHDDは、しばらくの間、万が一のためのバックアップとして保管しておき、問題がないことを確信できたら、専門のツールを使って、データを完全に消去してから、処分するようにしましょう。
まとめ:ディスククローンは、PCの「若返り」を、最も効率的に実現する魔法である
中古パソコンのパフォーマンスを、最も劇的に、そして最も費用対効果高く向上させる方法、それが、HDDからSSDへの換装です。
そして、その換装に伴う、最も大きな障壁である「環境の再構築」という、膨大な時間の浪費を、完全に消し去ってくれる技術が、ディスククローン作成です。
- ・準備が成功の9割を決める: 正しいフォームファクターの新しいSSD、PCとそれを繋ぐためのUSB変換アダプター、そして信頼できるクローニングソフトウェア。この三種の神器を、まず揃えること。
- ・ソースとデスティネーションの確認は、指差し確認で: コピー元(ソース)とコピー先(デスティネーション)の選択は、このプロセスにおける、唯一にして最大のリスクポイントです。絶対に、間違えてはいけません。
- ・パーティションサイズ調整を忘れない: より大容量のドライブに換装する際は、クローン作成時に、パーティションサイズを新しいドライブの最大容量まで拡張する設定を忘れないこと。これが、新しい領域を無駄にしないための鍵です。
- ・術後のケアまでが、クローン作成である: 換装後、BIOS/UEFIの起動順位を確認し、Windows上でTRIMが有効になっていることを確認する。この最後の仕上げが、新しいSSDの性能を、100%引き出します。
OSの再インストールという、数日に及ぶかもしれない、長く、退屈なトンネルを、クローン作成は、わずか数時間のワープで、あなたを駆け抜けさせてくれます。
その節約できた時間で、あなたは、生まれ変わった、高速なPCと共に、より創造的で、より価値のある、新しい仕事を始めることができるのです。

パソコン購入のためのお役立ち情報
パソコン選びがよく分からない方、ご不安のある方、悩む前に!お気軽にご相談ください!
専門スタッフが、性能・ご予算・お好みなどご希望に合ったパソコンをお探しします!



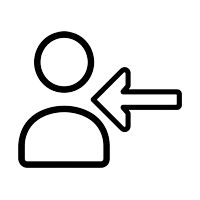 ログイン
ログイン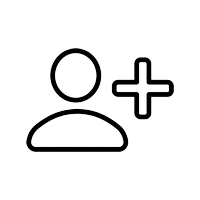 新しくアカウントを作成する
新しくアカウントを作成する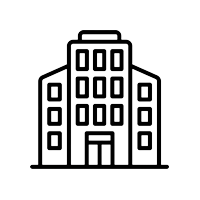 会社概要
会社概要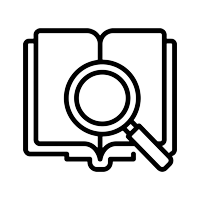 ご利用ガイド
ご利用ガイド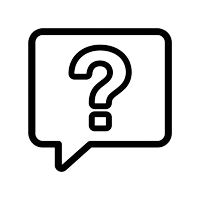 よくあるご質問
よくあるご質問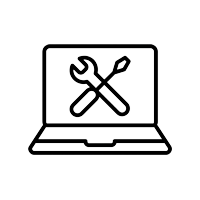 パソコン修理
パソコン修理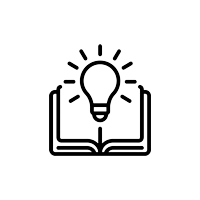 お役立ち情報
お役立ち情報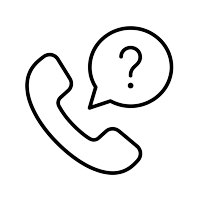 お問い合わせ
お問い合わせ 特定商取引に基づく表示
特定商取引に基づく表示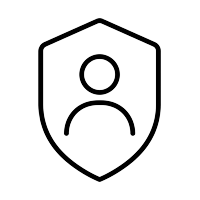 個人情報保護ポリシー
個人情報保護ポリシー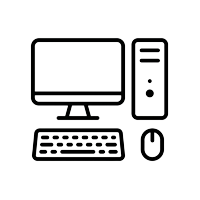 デスクトップパソコン
デスクトップパソコン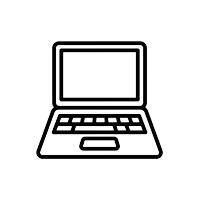 ノートパソコン
ノートパソコン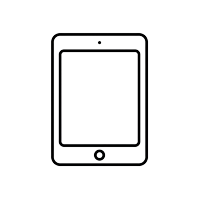 タブレット
タブレット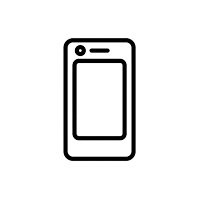 スマートフォン
スマートフォン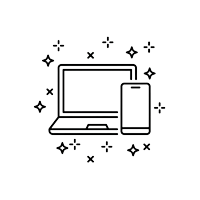 新品(Aランク)
新品(Aランク)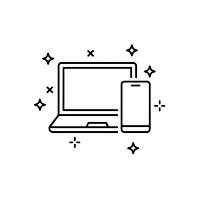 美品(Bランク)
美品(Bランク)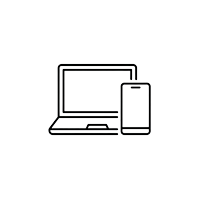 中古(Cランク)
中古(Cランク)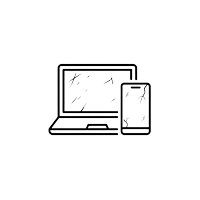 訳あり(Dランク)
訳あり(Dランク)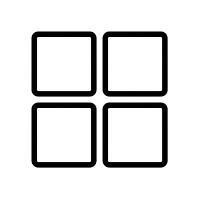 Windows 11
Windows 11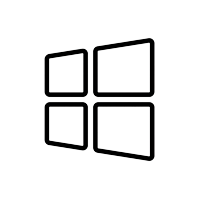 Windows 10
Windows 10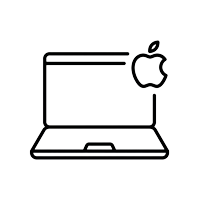 Mac OS
Mac OS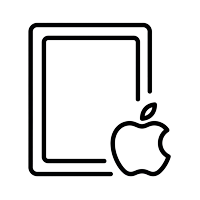 iPad OS
iPad OS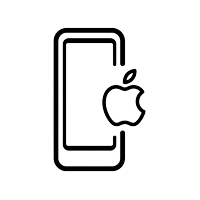 iOS
iOS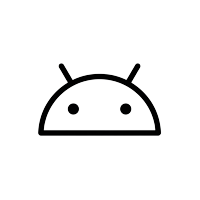 Android
Android コンシューマーモデル
コンシューマーモデル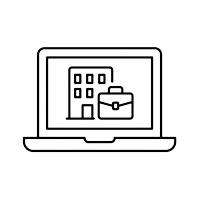 ビジネスモデル
ビジネスモデル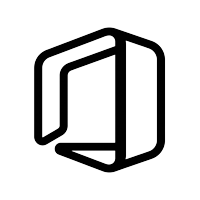 Microsoft Office搭載
Microsoft Office搭載 WPS Office搭載
WPS Office搭載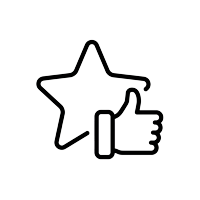 おすすめ商品
おすすめ商品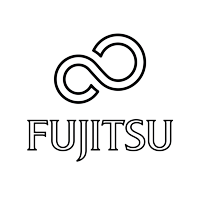
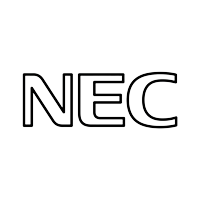
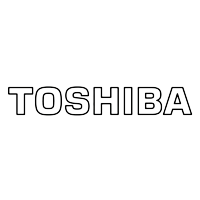


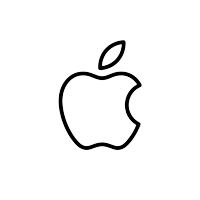


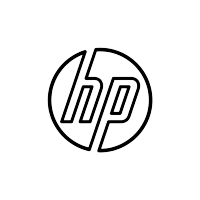
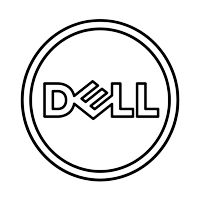

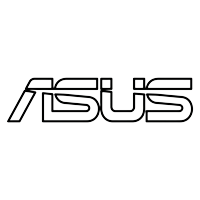
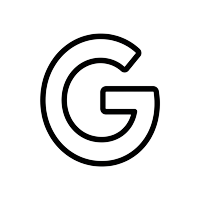

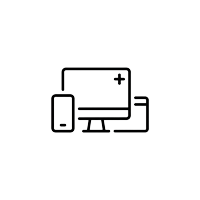
 Celeron|Athlon
Celeron|Athlon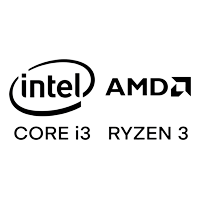 Core i3|Ryzen 3
Core i3|Ryzen 3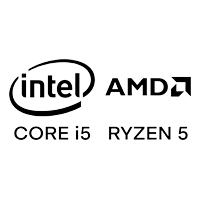 Core i5|Ryzen 5
Core i5|Ryzen 5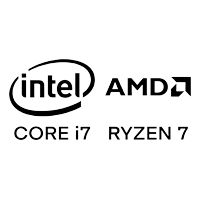 Core i7|Ryzen 7
Core i7|Ryzen 7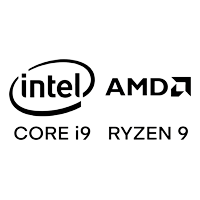 Core i9|Ryzen 9
Core i9|Ryzen 9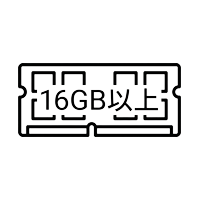 メモリ16GB以上
メモリ16GB以上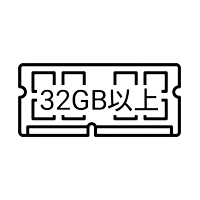 メモリ32GB以上
メモリ32GB以上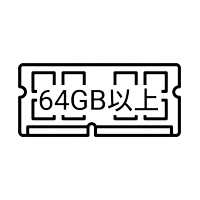 メモリ64GB以上
メモリ64GB以上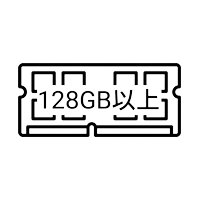 メモリ128GB以上
メモリ128GB以上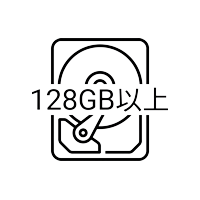 ストレージ128GB以上
ストレージ128GB以上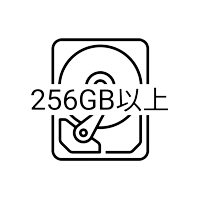 ストレージ256GB以上
ストレージ256GB以上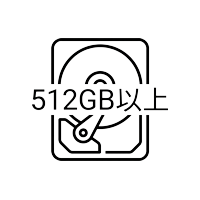 ストレージ512GB以上
ストレージ512GB以上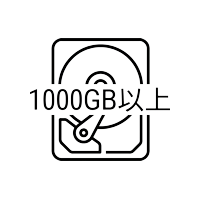 ストレージ1000GB以上
ストレージ1000GB以上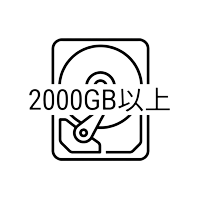 ストレージ2000GB以上
ストレージ2000GB以上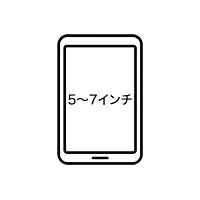 5〜7インチ
5〜7インチ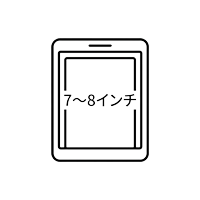 7〜8インチ
7〜8インチ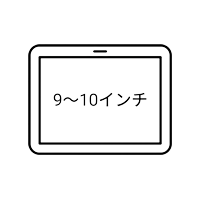 9〜10インチ
9〜10インチ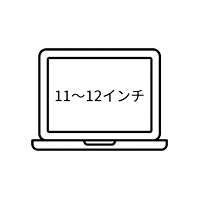 11〜12インチ
11〜12インチ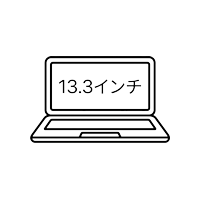 13.3インチ
13.3インチ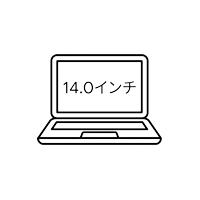 14.0インチ
14.0インチ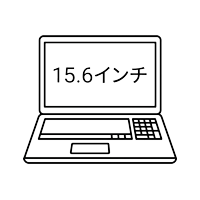 15.6インチ
15.6インチ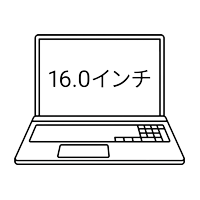 16.0インチ
16.0インチ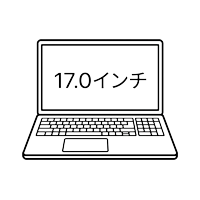 17.0インチ以上
17.0インチ以上




