
中古パソコンで音楽制作を始める:推奨スペックと導入ガイド
パソコン全般のお役立ち情報

この記事の最終更新日:2025年7月7日

先輩、私、最近、自分で曲を作ってみたくて、DTM(デスクトップミュージック)を始めたいと思っているんです。
でも、専用の機材やソフトだけじゃなくて、パソコンもすごく高性能なものが必要だって聞いて…。
クリエイターさんがよく使っているMacBook Proなんて、新品だと高すぎて、とても手が出ません。
中古のパソコンでも、本格的な音楽制作って、本当にできるものなんでしょうか?
スペックの見方もよくわからないし、何より、演奏してから『音が遅れて聞こえる』みたいな専門的なトラブルがすごく不安で、一歩が踏み出せないんです。

素晴らしい挑戦だね!そして、その不安は、DTMを本気で志す誰もが抱く、とても健全なものだよ。
結論から言うと、中古PCでも、選び方さえ間違えなければ、プロに匹敵する制作環境を、驚くほど低コストで構築できるんだ。
音楽制作のPC選びは、ゲームや動画編集のPC選びとは全く違う、独自の『物差し』が必要になる。
特に、君が心配している『音の遅れ』、専門用語でいう『レイテンシー』を制することが、快適な音楽制作を実現するための、最大の鍵なんだ。
今日は、そのレイてンシーの正体から、CPUやメモリが君の楽曲にどう影響するのか、そしてMacとWindowsの根本的なオーディオ思想の違いまで、君が最高の『最初の一台』を選び抜くための、プロの知識と視点を、全て伝授しよう。
【思想編】なぜ音楽制作用PCは特別なのか? - 全ては「レイテンシー」との戦い
音楽制作、すなわちDTM(デスクトップミュージック)用のPCを選ぶ際、多くの人がCPUのクロック周波数やメモリの容量といった、一般的なスペック表の数字に目を奪われがちです。
しかし、それらの数字以上に、DTMの世界で絶対的に重要視される概念があります。
それが「レイテンシー」です。
DTMにおける最大の敵「レイテンシー」とは何か?
レイテンシー (Latency)「遅延」を意味する言葉。DTMの世界では、鍵盤を弾いたりマイクに声を入力したりしてから、実際にスピーカーやヘッドフォンからその音が聞こえるまでの、ごくわずかな時間差を指します。は、デジタルオーディオを扱う上で、避けては通れない物理現象です。
音がPCに取り込まれる際、「アナログ信号→デジタル信号への変換(AD変換)」、PC内部での「データ処理」、そしてPCから音を出す際の「デジタル信号→アナログ信号への変換(DA変換)」という、複数の工程を経ます。
この各工程で発生する、ごくわずかな時間の遅れが積み重なったものが、レイテンシーの正体です。
この遅延が大きくなると、キーボードを弾く指のタイミングと、実際に聞こえてくる音のタイミングがズレてしまい、まともに演奏することができなくなります。
これは、ミュージシャンのインスピレーションやグルーヴを阻害する、致命的な問題です。
快適な音楽制作とは、このレイテンシーを、人間が知覚できないレベル(一般的に10ミリ秒以下)にまで、いかにして抑え込むか、という戦いの歴史なのです。
CPUとオーディオインターフェースの共同作業
レイテンシーを低減するためには、PCの「頭脳」であるCPUと、音の「入出力の専門家」であるオーディオインターフェースマイクや楽器などの音をPCに取り込んだり、PC内部の音をスピーカーやヘッドフォンに出力したりするための専用機器。高品質なAD/DA変換機能と、低レイテンシーを実現するドライバーを持ちます。との、緊密な連携が不可欠です。
CPUは、DAW(音楽制作ソフト)上で動く、ソフトウェア音源やエフェクトプラグインといった、膨大な計算処理をリアルタイムで実行する役割を担います。
CPUの性能が低いと、多くの処理を一度に行えず、音飛びやノイズの原因となります。
一方、オーディオインターフェースは、PC標準のサウンド機能よりも遥かに高品質なAD/DA変換を行うと同時に、OSの一般的なオーディオ処理経路をバイパスし、DAWと直接、高速にデータをやり取りするための、専用の「抜け道」を用意します。
この「抜け道」の性能こそが、レイテンシーを決定づける、もう一つの重要な要素です。
Mac vs Windows - OSレベルでのオーディオ処理思想の違い
この「抜け道」の作り方において、MacとWindowsには、OSレベルでの根本的な思想の違いがあります。
-
Macの「Core Audio」:
macOSに標準で搭載されている音声処理システムです。非常に優秀な設計で、OSレベルで低レイテンシーな音声のやり取りが保証されています。そのため、多くのオーディオインターフェースは、Macに接続するだけで、特別なドライバーをインストールしなくても、本来の性能を発揮できます。この「繋げばすぐ使える」手軽さと安定感が、長年、音楽業界でMacが標準機とされてきた大きな理由です。
-
Windowsの「ASIO」:
一方、Windowsの標準オーディオシステムは、音楽制作のような、リアルタイム性が求められる処理を、元々あまり得意としていませんでした。そこで、Steinberg社(Cubaseの開発元)が開発したのが、ASIO (Audio Stream Input/Output)Windows環境で、アプリケーションとオーディオインターフェースが直接、高速にデータをやり取りするための規格(ドライバー仕様)。低レイテンシーを実現するための、Windows DTMにおける事実上の標準です。という規格です。オーディオインターフェースのメーカーが、このASIO規格に準拠した専用ドライバーを提供し、それをDAW側で選択することで、初めて低レイテンシーな環境が実現します。ひと手間かかりますが、正しく設定すれば、Macと遜色ないパフォーマンスを発揮できます。
【第一部:スペック解剖編】快適な音楽制作を実現する4つの心臓部
レイテンシーとの戦いを有利に進めるためには、PCのどのパーツが、どのように音楽制作に影響するのかを、正確に理解する必要があります。
1. CPU - 楽曲の複雑さに直結する頭脳
CPU性能は、あなたの楽曲が、どれだけリッチで複雑になれるかを決定します。
特に重要なのが「シングルコア性能」です。
DAW上の個々のトラック(例えば、一つの壮大なシンセサイザーの音源)にかかる負荷は、基本的にCPUの一つのコアが担当します。
そのため、一つのコアあたりの処理速度が速ければ速いほど、より重い音源やエフェクトを、音飛びさせることなくスムーズに鳴らすことができます。
一方、トラック数が増えてくるミキシングの段階では、各トラックの処理を複数のコアに分散させるため、「マルチコア性能」も重要になってきます。
中古でPCを選ぶなら、一般的な事務用途で推奨されるCore i5では、すぐに性能限界に達します。
最低でもCore i7、予算が許すならCore i9や、Apple MシリーズのPro/Max/Ultraといった、高いシングルコア性能と、十分なマルチコア性能を両立したCPUを搭載したモデルを狙いましょう。
2. メモリ (RAM) - 同時に鳴らせる音源の数と種類
メモリは、特に、サンプリング音源実際の楽器の音を、一音一音、様々な強さで録音(サンプリング)し、それを再生することで、リアルな演奏を再現するソフトウェア音源。非常に大容量のデータを必要とします。を多用する場合に、極めて重要な役割を果たします。
リアルなオーケストラ音源や、高品質なピアノ音源は、そのライブラリ全体で数十GB、時には数百GBに達します。
これらの音源は、演奏時に高速にデータを読み出すため、その一部をあらかじめメモリ上にロードしておく必要があります。
メモリ容量が少ないと、一度にロードできる音色の数が限られたり、そもそも大容量の音源を快適に使うことができません。
一般的なPC利用では8GBでも十分と言われますが、DTMの世界では、8GBはもはや人権がありません。
16GBが最低限のスタートライン、そして、複数のサンプリング音源をストレスなく使いたいなら、32GB以上を強く推奨します。
3. ストレージ - 楽曲データと音源ライブラリの倉庫
ストレージ選びの基準は、ただ一つ、「速度」です。
旧来のHDDは、大容量のサンプリング音源の読み込みに時間がかかりすぎ、制作のテンポを著しく損なうため、もはや選択肢には入りません。
OSやDAW、プラグインをインストールするシステムドライブは、高速なNVMe SSDSSDの性能を最大限に引き出すために設計された、非常に高速な接続規格。従来のSATA接続SSDの数倍の速度が出ます。であることが必須です。
理想を言えば、システム用のNVMe SSDとは別に、大容量の音源ライブラリを保存するための、2台目のSSD(NVMeまたはSATA)を用意することです。
物理的にドライブを分けることで、OSの動作と、音源の読み込みが互いに干渉しなくなり、システム全体の安定性が向上します。
容量は、最低でも合計1TB、本格的に取り組むなら2TB以上を見積もっておくと安心です。
4. ポート類と静音性 - 見落とされがちな重要要素
スペック表の数字以外にも、DTM用PC選びでは、見落とせない重要なポイントがあります。
一つは、ポートの種類と数です。
高性能なオーディオインターフェースや、高速な外付けSSDは、その性能を最大限に発揮するために、Thunderbolt 3/4や、USB 3.1 Gen2といった、高速なデータ転送が可能なポートを必要とします。
もう一つは、「静音性」です。
特に、ボーカルやアコースティック楽器をマイクで録音する場合、PCの冷却ファンの音が大きいと、その騒音がマイクに入り込み、録音の品質を著しく低下させてしまいます。
この点では、ファンレス設計のMacBook Airや、そもそも冷却性能に余裕がある、筐体の大きなデスクトップPC、あるいは静音性に定評のある法人向けノートPCなどが有利になります。
【第二部:モデル選定・導入編】中古市場でダイヤモンドの原石を探す
では、これらの知識を元に、中古市場で具体的にどのようなモデルを狙うべきかを見ていきましょう。
Macの選択肢 - 揺るぎない業界標準
制作現場での互換性や、Core Audioの安定性を重視するなら、Macが第一候補となります。
中古市場では、数年前のMacBook ProやiMac、Mac miniが、非常に魅力的な価格で手に入ります。
特に、Intel CPUを搭載した最終世代のモデル(2019年~2020年頃)は、価格がこなれてきている一方で、依然として高いCPU性能を持っており、コストパフォーマンスに優れた選択肢です。
Apple Silicon搭載モデルを選ぶ場合は、その圧倒的な電力効率とパフォーマンスが魅力ですが、自分が使いたいプラグインやオーディオインターフェースが、そのMacのOSとチップに、ネイティブで対応しているか(あるいは、変換技術であるRosetta 2で安定動作するか)を、購入前に必ず、各メーカーの公式サイトで確認する必要があります。
Windowsの選択肢 - 隠れた逸材「法人向けPC」
Windows環境で、コストを抑えつつ、最高の安定性とパフォーマンスを求めるなら、最強の選択肢は、中古の「法人向けモバイルワークステーション」です。
DELLのPrecisionシリーズや、HPのZBookシリーズといったモデルは、元々、CADや科学技術計算といった、極めて高い負荷がかかる業務を、24時間365日、安定してこなし続けることを前提に設計されています。
そのため、搭載されているCPUは高性能なものが多く、冷却機構も非常に堅牢で、拡張性やメンテナンス性にも優れています。
新品では数十万円するこれらのモデルが、リースアップ品として中古市場に流れてくることで、同価格帯の新品のコンシューマー向けPCとは比較にならないほどの、高い性能と信頼性を、驚くほどの低価格で手に入れることができるのです。
【第三部:環境構築・最適化編】レイテンシーを極限まで減らす
最適なPCを手に入れたら、最後は、DAWソフトウェア側の設定で、パフォーマンスを最大限に引き出します。
最も重要な設定が、「バッファサイズ」です。
バッファサイズとは、データをCPUに送る前に、一時的に溜めておく「バケツ」の大きさのようなものです。
このバケツの大きさとレイテンシー、そしてCPU負荷は、トレードオフの関係にあります。
-
バッファサイズを小さくする(例: 64, 128 samples):
バケツが小さいので、データはすぐにCPUに送られます。これにより、レイテンシーは小さくなりますが、CPUは常にせわしなく働く必要があり、負荷が高まります。リアルタイムでの演奏や録音を行う際に、この設定にします。
-
バッファサイズを大きくする(例: 1024, 2048 samples):
バケツが大きいので、データをある程度まとめてから、余裕をもってCPUに送ることができます。これにより、レイテンシーは大きくなりますが、CPUの負荷は低減します。多数のプラグインエフェクトをかけて、楽曲全体を再生・ミキシングする際に、この設定にします。
このように、作業のフェーズに応じて、バッファサイズを適切に切り替えることが、快適なDTM環境の秘訣です。
また、DAWに搭載されている「フリーズ機能」も積極的に活用しましょう。
これは、CPU負荷の高いソフトウェア音源のトラックを、一時的にオーディオファイルに書き出してしまう機能です。
これにより、そのトラックのCPU負荷がゼロになり、他のトラックの処理にCPUパワーを割り当てることができます。
まとめ - 最適なPCは、あなたの音楽制作を加速させる「最高の相棒」である
音楽制作のためのPC選びは、一見すると複雑で、専門用語の壁に圧倒されてしまうかもしれません。
しかし、その本質は非常にシンプルです。
それは、「レイテンシー」という最大の敵を、いかにして打ち負かすか、という一点に集約されます。
-
1. 「レイテンシー」を理解し、低減する手段を知ること:
強力なCPUと、ASIO(Windowsの場合)に対応した優れたオーディオインターフェースの組み合わせが、そのための二大巨頭です。
-
2. 「メモリ」と「SSD」の重要性を認識すること:
CPUの性能を最大限に活かすためには、膨大な音源データを滞りなく供給するための、32GB以上の大容量メモリと、高速なNVMe SSDが不可欠です。
-
3. 自分の「OS」と「DAW」の特性を知り、最適化すること:
MacのCore Audio、WindowsのASIOドライバー、そしてDAWのバッファサイズ設定。これらのソフトウェア的な最適化が、ハードウェアの性能を限界まで引き出します。
中古PC市場には、数年前にプロフェッショナルが愛用した、数々の「ダイヤモンドの原石」が眠っています。
この記事で得た知識という名の「鑑定眼」で、それらの原石を見つけ出し、丁寧に磨き上げること。
そうして手に入れたPCは、単なる機材ではなく、あなたの創造性を刺激し、まだ見ぬ名曲を生み出すための、かけがえのない「最高の相棒」となるはずです。
パソコン購入のためのお役立ち情報
パソコン選びがよく分からない方、ご不安のある方、悩む前に!お気軽にご相談ください!
専門スタッフが、性能・ご予算・お好みなどご希望に合ったパソコンをお探しします!



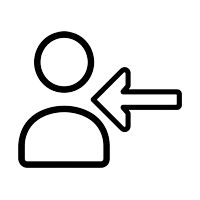 ログイン
ログイン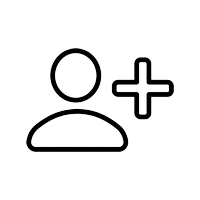 新しくアカウントを作成する
新しくアカウントを作成する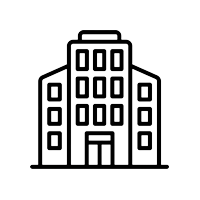 会社概要
会社概要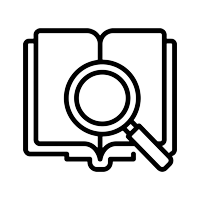 ご利用ガイド
ご利用ガイド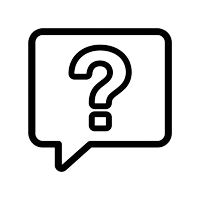 よくあるご質問
よくあるご質問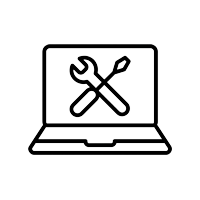 パソコン修理
パソコン修理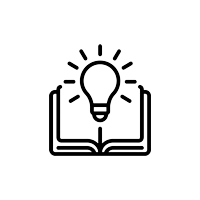 お役立ち情報
お役立ち情報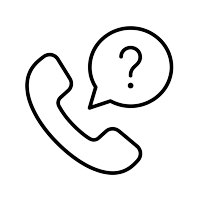 お問い合わせ
お問い合わせ 特定商取引に基づく表示
特定商取引に基づく表示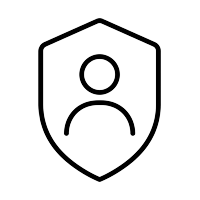 個人情報保護ポリシー
個人情報保護ポリシー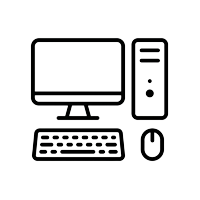 デスクトップパソコン
デスクトップパソコン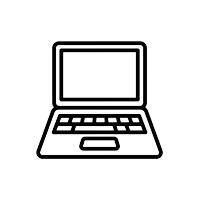 ノートパソコン
ノートパソコン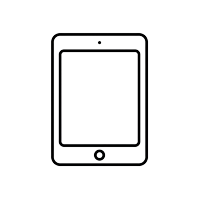 タブレット
タブレット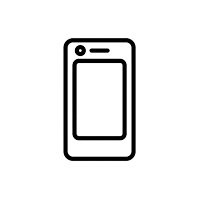 スマートフォン
スマートフォン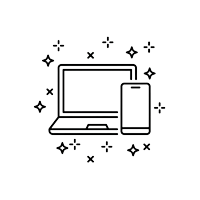 新品(Aランク)
新品(Aランク)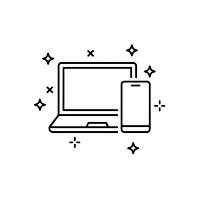 美品(Bランク)
美品(Bランク)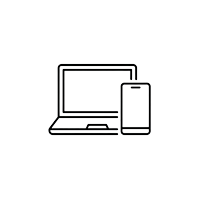 中古(Cランク)
中古(Cランク)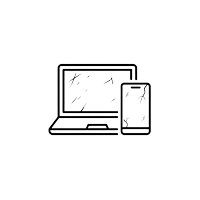 訳あり(Dランク)
訳あり(Dランク)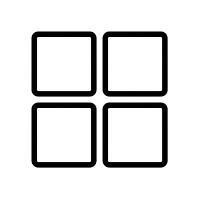 Windows 11
Windows 11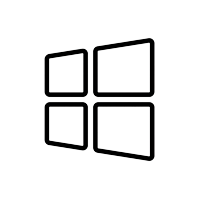 Windows 10
Windows 10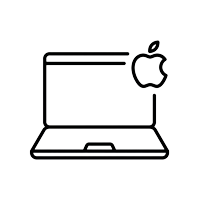 Mac OS
Mac OS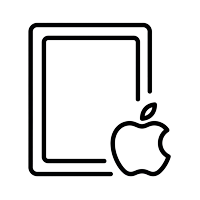 iPad OS
iPad OS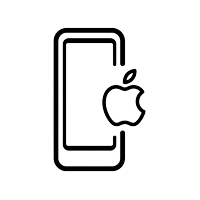 iOS
iOS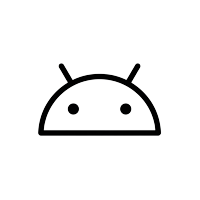 Android
Android コンシューマーモデル
コンシューマーモデル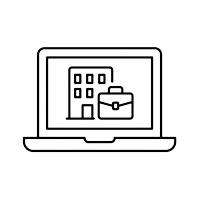 ビジネスモデル
ビジネスモデル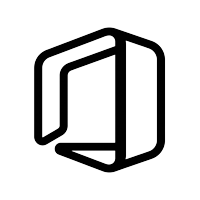 Microsoft Office搭載
Microsoft Office搭載 WPS Office搭載
WPS Office搭載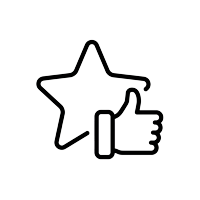 おすすめ商品
おすすめ商品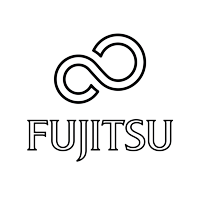
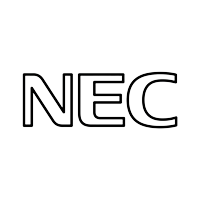
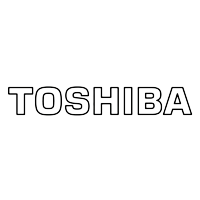


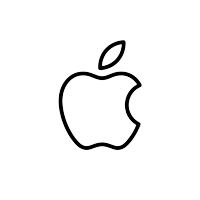


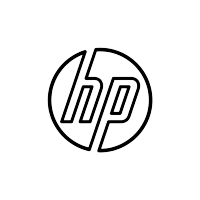
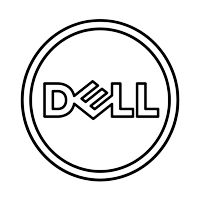

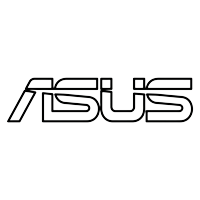
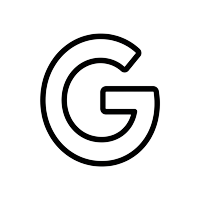

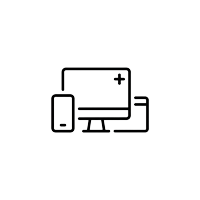
 Celeron|Athlon
Celeron|Athlon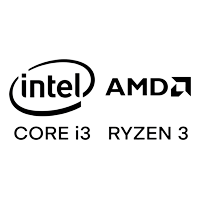 Core i3|Ryzen 3
Core i3|Ryzen 3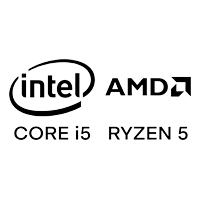 Core i5|Ryzen 5
Core i5|Ryzen 5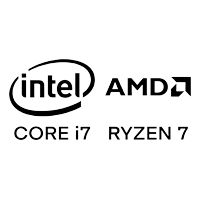 Core i7|Ryzen 7
Core i7|Ryzen 7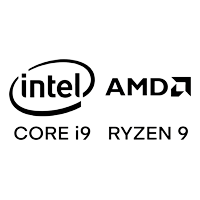 Core i9|Ryzen 9
Core i9|Ryzen 9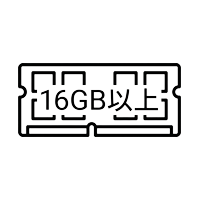 メモリ16GB以上
メモリ16GB以上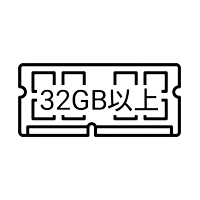 メモリ32GB以上
メモリ32GB以上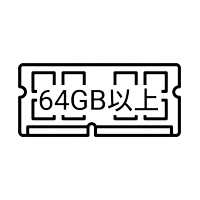 メモリ64GB以上
メモリ64GB以上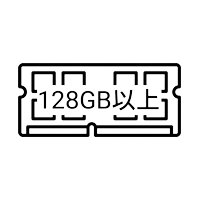 メモリ128GB以上
メモリ128GB以上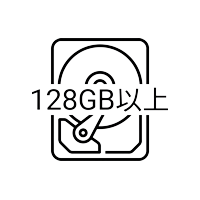 ストレージ128GB以上
ストレージ128GB以上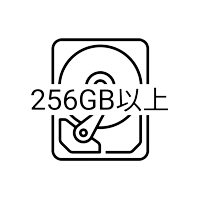 ストレージ256GB以上
ストレージ256GB以上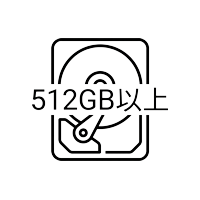 ストレージ512GB以上
ストレージ512GB以上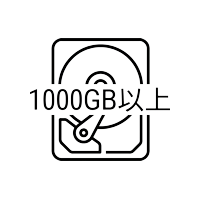 ストレージ1000GB以上
ストレージ1000GB以上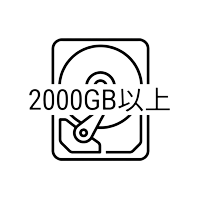 ストレージ2000GB以上
ストレージ2000GB以上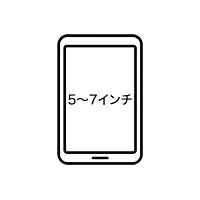 5〜7インチ
5〜7インチ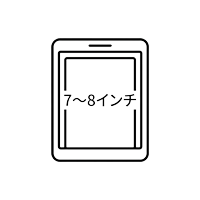 7〜8インチ
7〜8インチ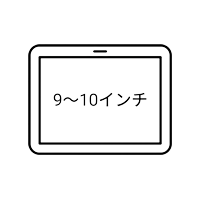 9〜10インチ
9〜10インチ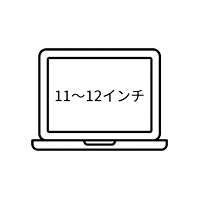 11〜12インチ
11〜12インチ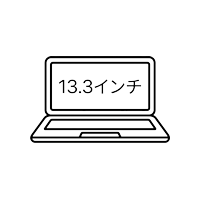 13.3インチ
13.3インチ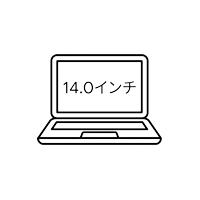 14.0インチ
14.0インチ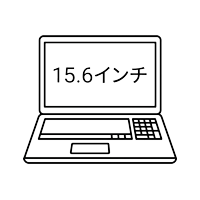 15.6インチ
15.6インチ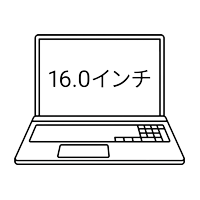 16.0インチ
16.0インチ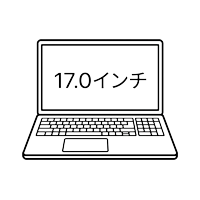 17.0インチ以上
17.0インチ以上



