
ノートパソコンをテレビに接続して大画面で楽しむ方法
ノートパソコンのお役立ち情報

記事の最終更新日:2025年7月10日
ノートパソコンに保存している旅行の動画や、契約しているストリーミングサービスの映画を、家族みんなで、リビングの大きなテレビ画面で楽しみたいんです。
でも、パソコンとテレビを繋ぐための、どのケーブルを買えばいいのか、ポートの形も色々あってよく分かりません。
以前、適当なケーブルで繋いでみたら、映像は映ったけど音がでなかったり、画質が悪かったりして、結局諦めてしまいました。
それに、できれば長いケーブルを部屋の中に這わせずに、ワイヤレスで接続する方法もあるって聞いたのですが、本当でしょうか?
確実で、高画質な接続方法と、そのための設定を、一から教えてほしいです。
そのお気持ち、とてもよく分かります。
あなたのノートパソコンは、それ自体が、無限のコンテンツを秘めた、ポータブルなエンターテインメントセンターです。
その真価を、リビングの大画面テレビで解放するのは、最高の体験ですよ。
ご安心ください。
ノートパソコンをテレビに接続する方法は、大きく分けて2つの道筋、「有線接続」と「無線接続」があり、それぞれに長所と、いくつかの「コツ」があります。
有線接続は、最高の画質と安定性を約束する「王道」。
無線接続は、ケーブルの煩わしさから解放される「自由な道」。
この記事では、まず、あなたのPCとテレビのポートを正しく鑑定する方法から始め、それぞれの接続方法の具体的な手順、そして4K HDRといった高画質映像を完璧に再現するための、専門的な設定の全てを、ステップ・バイ・ステップで解説していきます。
あなたのリビングを、今夜から、最高のプライベートシアターに変えましょう。
なぜPCをテレビに繋ぐのか? - スマートTVを超える「無限の可能性」
現代のテレビの多くは、単体でインターネットに接続し、様々な動画配信サービスを視聴できる「スマートTV」です。
では、なぜ今あえて、ノートパソコンをテレビに接続するのでしょうか。
その答えは、スマートTVという「完成された製品」の枠組みを超えた、圧倒的な「自由度」と「拡張性」にあります。
ノートパソコンは、それ自体が、完全な機能を持つ、高性能なコンピューターです。
それは、世界中のあらゆる動画配信サービスに、ブラウザや専用アプリを通じてアクセスできることを意味します。
スマートTVではサポートされていない、ニッチなサービスや、海外のスポーツ中継なども、PCなら問題なく視聴できます。
また、あなたがPC内に保存している、あらゆる形式の動画、音楽、写真といった、パーソナルなメディアライブラリを、最高の再生品質で、そして意のままに楽しむことができます。
さらに、大画面でのWebブラウジング、ビデオ通話、そしてPCゲームに至るまで、その用途は無限に広がります。
ノートパソコンをテレビに接続する行為は、テレビを、単なるコンテンツの「受信機」から、あらゆるデジタルコンテンツを映し出す、万能な「出力装置」へと、その本質から変貌させる、強力なアップグレードなのです。
第一章:有線接続 - 最高の画質と安定性を求める王道
4K HDRのような高画質コンテンツを、遅延やコマ落ちなく、完璧な品質で楽しみたいのであれば、有線接続が最も確実で、そして唯一の選択肢です。
物理的なケーブルで接続するため、無線環境のような干渉や速度低下の心配が一切なく、常に安定した接続が保証されます。
ステップ1:ポートの形状を確認する「コネクタ鑑定術」
まず、あなたのノートパソコン側にある「映像出力ポート」と、テレビ側にある「映像入力ポート」の種類を確認します。
これが、正しいケーブルを選ぶための、最も重要な第一歩です。
【ノートパソコン側の主なポート】
- ・HDMI: 最も一般的で、多くのノートパソコンに搭載されています。標準HDMI、Mini HDMI、Micro HDMIといったサイズのバリエーションがあるため、形状をよく確認しましょう。
- ・USB Type-C: 近年の薄型ノートパソコンの主流です。ただし、注意が必要なのは、全てのUSB-Cポートが映像出力に対応しているわけではない、という点です。「Thunderbolt(稲妻のマーク)」や「DisplayPort(Dのマーク)」のロゴが付いているポートは、ほぼ確実に映像出力に対応しています。
- ・DisplayPort / Mini DisplayPort: ビジネス向けやゲーミングノートPCに搭載されていることが多い、高性能な映像出力ポートです。
【テレビ側の主なポート】
現代のテレビの映像入力は、ほぼ「HDMI」一択です。
複数のHDMIポートがある場合は、どのポートが4K/60HzやHDRに対応しているか、あるいはARC/eARC(※注釈:テレビの音声をAVアンプなどに送るための機能)に対応しているかを、テレビの取扱説明書などで確認しておくと、より高度な設定の際に役立ちます。
ステップ2:4K HDR体験のための機材選定
4K解像度(3840x2160)で、かつ毎秒60フレーム(60Hz)の滑らかな映像、さらにはHDR(ハイダイナミックレンジ)の鮮やかな色彩を、完全に再現するには、PC、ケーブル、テレビの全てが、その規格に対応している必要があります。
PCとテレビのHDMIポートが「**HDMI 2.0**」以上、DisplayPortであれば「**DisplayPort 1.4**」以上に対応していることが条件となります。
USB-Cポートから出力する場合は、そのポートがDisplayPort 1.4 Alternate Mode以上に対応している必要があります。
そして、意外と見落としがちなのが、これらを繋ぐ「**HDMIケーブルの品質**」です。
4K/60Hz HDRの映像を伝送するには、18Gbps以上の帯域幅を保証する、「ハイスピード」または「プレミアムハイスピード」と記載されたHDMIケーブルが必要です。
古いケーブルを使い回すと、「信号がありません」と表示されたり、画面が点滅したりする原因となります。
ステップ3:物理的な接続とOSでの認識
正しいケーブルを用意したら、PCとテレビの電源が入っている状態で、それぞれのポートにしっかりと接続します。
次に、テレビのリモコンで、「入力切換」ボタンを押し、PCを接続したHDMIポート(例:「HDMI 1」「HDMI 2」など)を選択します。
通常は、これだけでPCの画面がテレビに映し出されます。
もし映らない場合は、キーボードの「Windowsキー + P」を押し、表示されるメニューから「複製」または「拡張」を選択してみてください。
第二章:無線接続 - ケーブルの呪縛から解放される自由
リビングの美観を損ねる長いケーブルを引き回したくない、あるいは、もっと手軽に接続したい、という場合には、無線接続が非常に便利な選択肢となります。
ただし、画質や安定性は、有線接続に一歩譲ることを念頭に置く必要があります。
Windowsの標準機能「Miracast(ミラキャスト)」
Miracastは、Wi-Fiの技術を使い、PCとテレビを1対1で直接接続する、ワイヤレスディスプレイの標準規格です。
近年のWindows 11 PCと、多くのスマートTVが、このMiracastを受信する機能を標準で備えています。
接続するには、PCとテレビが同じWi-Fiネットワークに接続されている必要はありません。
Windows 11 PCで、キーボードの「Windowsキー + K」を押すと、接続可能なワイヤレスディスプレイの一覧が表示されます。
リストにあなたのテレビ名が表示されたら、それをクリックするだけで、接続が開始されます。
手軽さが最大のメリットですが、通信環境によっては、遅延や画質の劣化が発生しやすいという側面もあります。
Appleのエコシステム「AirPlay(エアプレイ)」
MacBookユーザーであれば、AirPlayが最も簡単で高品質な無線接続方法です。
Apple TV、あるいはAirPlay 2に対応したスマートTVがあれば、Macとテレビを同じWi-Fiネットワークに接続した状態で、メニューバーのコントロールセンターから「画面ミラーリング」を選択し、リストから目的のテレビを選ぶだけで、Macの画面をワイヤレスで映し出すことができます。
Appleデバイス間の連携に最適化されているため、比較的安定しており、高品質なストリーミングが可能です。
Google Cast(Chromecast)によるキャスト
GoogleのChromecastデバイスをテレビに接続している場合、あるいはテレビ自体がChromecast built-inに対応している場合、Google Chromeブラウザの機能を使って、特定のタブや、デスクトップ全体をテレビに「キャスト」することができます。
これは、厳密にはPCの画面をミラーリングするのとは少し異なり、特にYouTubeやNetflixといった対応サービスでは、Chromecastデバイスが、インターネットから直接コンテンツをストリーミング再生するため、PCへの負荷が少なく、安定した再生が可能です。
第三章:大画面体験の最適化 - OSの表示・音声設定をマスターする
テレビへの接続が完了したら、次は、ソファから快適に視聴・操作できるように、PC側の設定を最適化していきます。
表示モードの選択:「複製」と「拡張」、そして「セカンドスクリーンのみ」
「Windowsキー + P」で呼び出せる「表示」メニューには、重要な選択肢があります。
- ・複製: PCの画面とテレビの画面に、全く同じ内容を表示します。プレゼンテーションなどで、手元のPCで確認しながら、聴衆に同じ画面を見せたい場合に適しています。
- ・拡張: PCのデスクトップ空間が、テレビの画面へと広がり、2つの画面を一つの広大な作業領域として使えます。テレビで動画を再生しながら、PC側では別の作業をするといった、マルチタスクに適しています。
- ・セカンドスクリーンのみ: ノートPCの画面は消灯し、テレビの画面のみに映像を出力します。映画などを視聴する際に、PCの画面が光って邪魔になるのを防ぎ、かつ、PC側のグラフィック性能をテレビへの出力に集中させることができるため、パフォーマンス的にも最も推奨されるモードです。
解像度、スケーリング、そしてHDR設定
「設定」>「システム」>「ディスプレイ」で、テレビに最適な表示設定を行います。
まず、「解像度」が、お使いのテレビのネイティブ解像度(例:4Kテレビなら3840 x 2160)に設定されていることを確認します。
次に、「拡大/縮小」のスケーリング設定を調整します。
高解像度のテレビでは、100%表示だと文字やアイコンが小さすぎて読めないため、「200%」や「300%」といった具合に、ソファからでも快適に読める大きさに調整します。
お使いのPCとテレビがHDRに対応している場合は、同じ設定画面で「HDRを使用する」をオンにすることで、より現実に近い、鮮やかでダイナミックな映像表現を楽しむことができます。
音声出力先の切り替え
映像はテレビに映ったが、音声がPC本体からしか聞こえない、という場合は、音声の出力先を切り替える必要があります。
タスクバーのスピーカーアイコンをクリックし、音量スライダーの右側にある「>」ボタンを押して、出力デバイスの一覧から、お使いのテレビや、接続しているAVアンプの名前(例:「SONY TV (*- HDMI)」)を選択してください。
これにより、音声もHDMIケーブルを通じて、テレビから出力されるようになります。
第四章:トラブルシューティング - よくある問題とその解決策
【問題】テレビに「信号がありません」と表示される。
【解決策】①ケーブルがPCとテレビの両方にしっかりと接続されているか再確認します。②テレビのリモコンで、正しいHDMI入力が選択されているか確認します。③PC側で「Windowsキー + P」を押し、「複製」モードなどを選択して、強制的に信号を送ってみます。
【問題】テレビ画面の端が切れて表示される(オーバースキャン)。
【解決策】これは、テレビ側の設定が原因であることがほとんどです。テレビの「設定」メニューから、「画面モード」や「映像設定」といった項目を探し、「オーバースキャン」や「フィットスクリーン」、「ジャストスキャン」といった設定項目を見つけ、PCからの映像が、ドットバイドット(1:1)で表示されるモードに切り替えてください。
【問題】無線接続が途切れたり、カクカクしたりする。
【解決策】①PCとテレビ(または受信機)を、Wi-Fiルーターに近づけて、電波強度を改善します。②電子レンジや他のワイヤレス機器など、電波干渉の原因となるものからルーターを遠ざけます。③可能であれば、Wi-Fiのチャンネルを、比較的空いている5GHz帯に変更します。④同じネットワークで、他の家族が大きなファイルのダウンロードなどを行っていないか確認します。
まとめ:あなたのノートPCは、最高のポータブル・エンターテインメント・ステーションである
ノートパソコンをテレビに接続する技術は、あなたのデジタルライフの楽しみ方を、無限に拡張する可能性を秘めています。
書斎で作成したプレゼンテーションをリビングでリハーサルする、一人で楽しんでいたPCゲームを友人と大画面で共有する、そして、世界中のあらゆる映像コンテンツを、家族と共に、最高の環境で鑑賞する。
その全てが、一本のケーブル、あるいは数クリックのワイヤレス設定で、実現するのです。
- ・品質の「有線」か、自由の「無線」か: まず、あなたの目的を明確にしましょう。最高の画質と安定性を求めるなら有線接続、手軽さとスマートな見た目を求めるなら無線接続。それぞれの長所を理解することが、最初のステップです。
- ・機材の「格」を合わせる: 4K HDRという最高の映像体験を求めるなら、PC、テレビ、そしてケーブルの全てが、HDMI 2.0以上の規格に対応している必要があります。ボトルネックになる機材がないか、事前に確認しましょう。
- ・「セカンドスクリーンのみ」を使いこなす: 映画などのコンテンツに集中したい時は、「Windowsキー + P」から「セカンドスクリーンのみ」を選択する。これが、パフォーマンスと没入感を両立させる、プロの選択です。
- ・トラブルは、切り分けて考える: 問題が発生した際は、「ケーブルの問題か?」「テレビの入力設定か?」「PCの出力設定か?」と、一つずつ原因を切り分けていくことで、必ず解決の糸口は見つかります。
あなたのノートパソコンは、仕事の道具であると同時に、最高のエンターテインメント・プレーヤーでもあります。
この記事を参考に、ぜひそのポテンシャルを最大限に引き出し、あなたと、あなたの大切な人々のための、特別な視聴体験を創造してください。

パソコン購入のためのお役立ち情報
パソコン選びがよく分からない方、ご不安のある方、悩む前に!お気軽にご相談ください!
専門スタッフが、性能・ご予算・お好みなどご希望に合ったパソコンをお探しします!



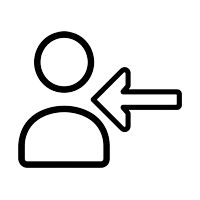 ログイン
ログイン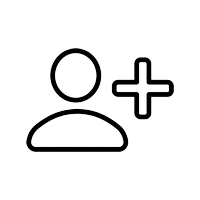 新しくアカウントを作成する
新しくアカウントを作成する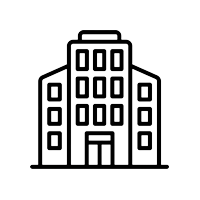 会社概要
会社概要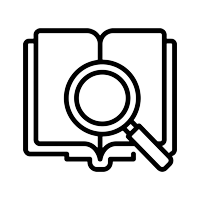 ご利用ガイド
ご利用ガイド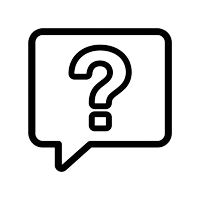 よくあるご質問
よくあるご質問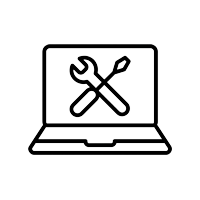 パソコン修理
パソコン修理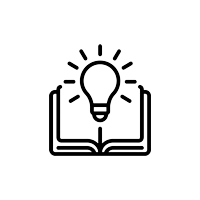 お役立ち情報
お役立ち情報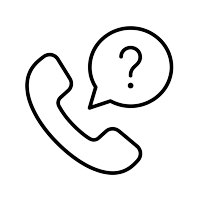 お問い合わせ
お問い合わせ 特定商取引に基づく表示
特定商取引に基づく表示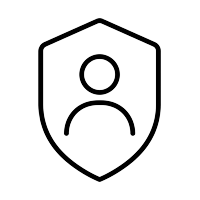 個人情報保護ポリシー
個人情報保護ポリシー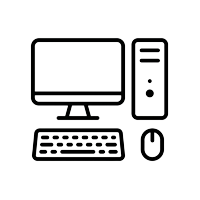 デスクトップパソコン
デスクトップパソコン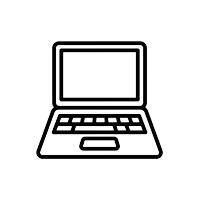 ノートパソコン
ノートパソコン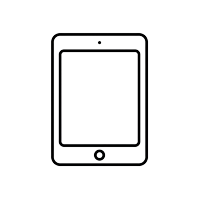 タブレット
タブレット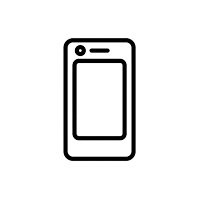 スマートフォン
スマートフォン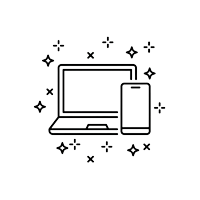 新品(Aランク)
新品(Aランク)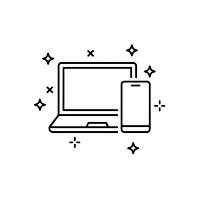 美品(Bランク)
美品(Bランク)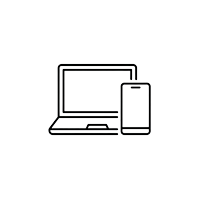 中古(Cランク)
中古(Cランク)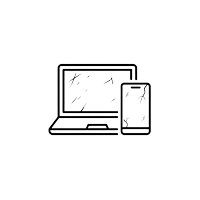 訳あり(Dランク)
訳あり(Dランク)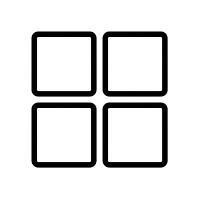 Windows 11
Windows 11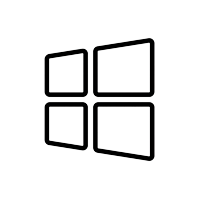 Windows 10
Windows 10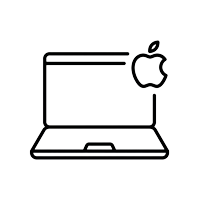 Mac OS
Mac OS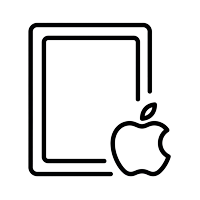 iPad OS
iPad OS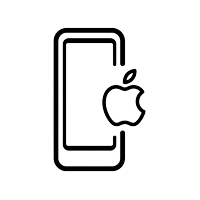 iOS
iOS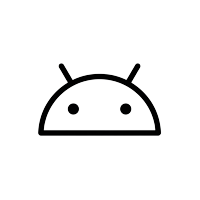 Android
Android コンシューマーモデル
コンシューマーモデル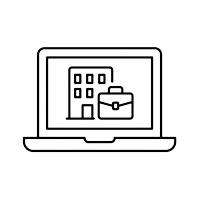 ビジネスモデル
ビジネスモデル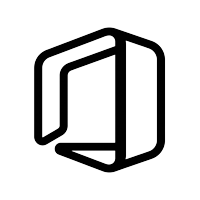 Microsoft Office搭載
Microsoft Office搭載 WPS Office搭載
WPS Office搭載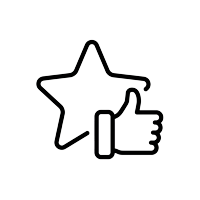 おすすめ商品
おすすめ商品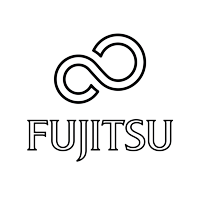
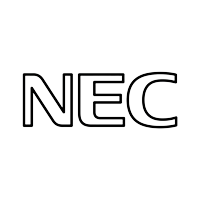
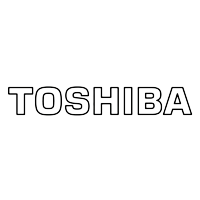


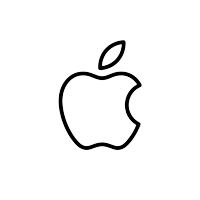


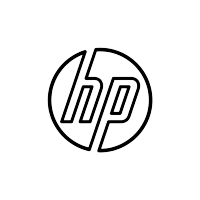
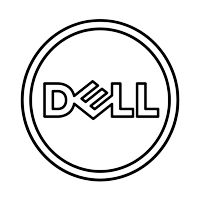

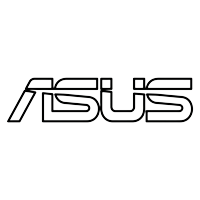
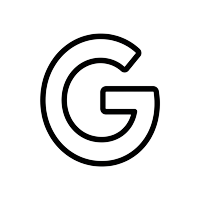

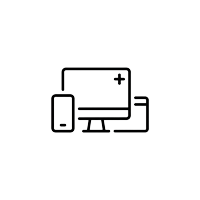
 Celeron|Athlon
Celeron|Athlon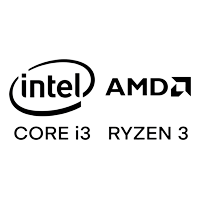 Core i3|Ryzen 3
Core i3|Ryzen 3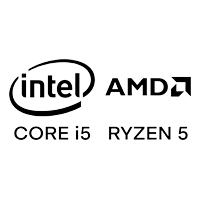 Core i5|Ryzen 5
Core i5|Ryzen 5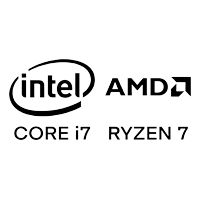 Core i7|Ryzen 7
Core i7|Ryzen 7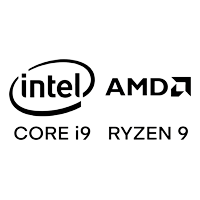 Core i9|Ryzen 9
Core i9|Ryzen 9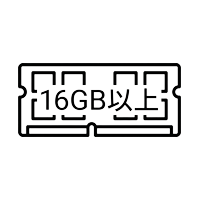 メモリ16GB以上
メモリ16GB以上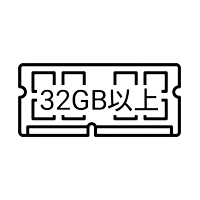 メモリ32GB以上
メモリ32GB以上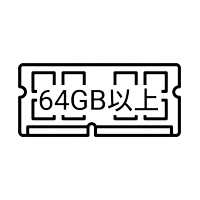 メモリ64GB以上
メモリ64GB以上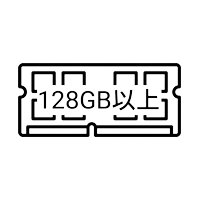 メモリ128GB以上
メモリ128GB以上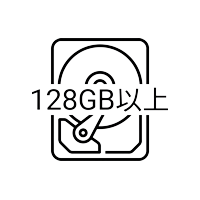 ストレージ128GB以上
ストレージ128GB以上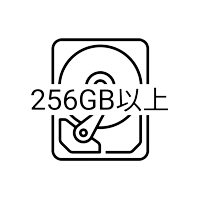 ストレージ256GB以上
ストレージ256GB以上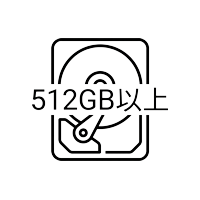 ストレージ512GB以上
ストレージ512GB以上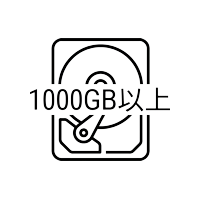 ストレージ1000GB以上
ストレージ1000GB以上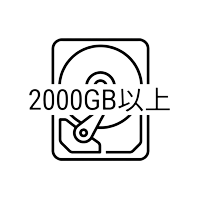 ストレージ2000GB以上
ストレージ2000GB以上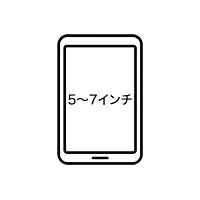 5〜7インチ
5〜7インチ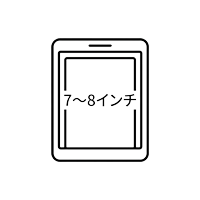 7〜8インチ
7〜8インチ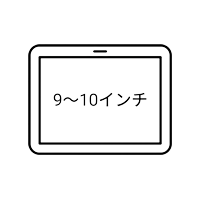 9〜10インチ
9〜10インチ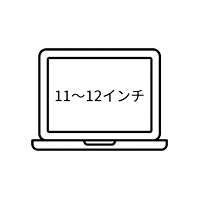 11〜12インチ
11〜12インチ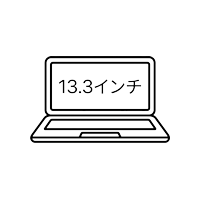 13.3インチ
13.3インチ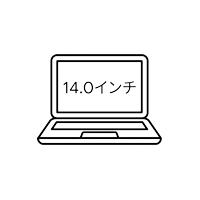 14.0インチ
14.0インチ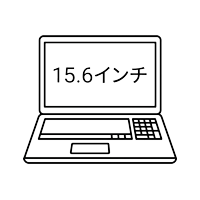 15.6インチ
15.6インチ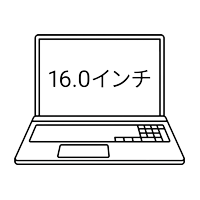 16.0インチ
16.0インチ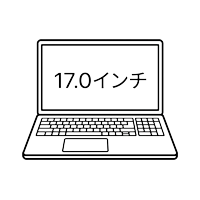 17.0インチ以上
17.0インチ以上




