
ノートパソコンの画面をキャリブレーションして色を正確に表示する方法
ノートパソコンのお役立ち情報

記事の最終更新日:2025年7月11日
趣味で、ノートパソコンで写真の編集をしているんです。
でも、大きな問題があって…。
自分のパソコンの画面では、完璧だと思った色合いの写真も、スマートフォンで見たり、友人のパソコンで見せてもらったりすると、全然違う、なんだか色褪せたような、あるいは変に赤みがかった色に見えてしまうんです。
これでは、自信を持って作品を公開できません。
どうすれば、私のノートパソコンの画面に表示される色を、他の人が見る色や、印刷した時の色と、同じ「正しい色」に合わせることができるのでしょうか?
「キャリブレーション」という言葉を聞いたことはあるのですが、具体的に何をすればいいのか、専門的で難しそうで…。
その問題こそ、デジタルで「色」を扱う、全てのクリエイターが直面する、最も根源的で、そして最も重要な課題、「色の標準化」です。
あなたは、極めて重要な真実に気づかれました。
そう、初期状態のPCのディスプレイが表示している色は、残念ながら、全く「正しく」ありません。
それは、ディスプレイ個体の製造誤差や、経年劣化によって、微妙に、あるいは大胆に、本来あるべき色からズレてしまっているのです。
そして、そのズレを、科学的な手法で測定し、補正するための、唯一の信頼できるプロセスが、「**カラーキャリブレーション**」なのです。
それは、例えるなら、楽器の「チューニング」。
狂った音程を、正しい音階へと調律するように、あなたのディスプレイが発する色を、世界共通の「正しい色」の基準へと、正確に合わせ込む、プロフェッショナルな技術です。
この記事では、そのための基本的な知識から、OS標準ツールによる簡易的な調整法、そして、専用の測定器(キャリブレーター)を使った、本格的なハードウェアキャリブレーションの全手順まで、あなたの「色」に対する不安を、絶対的な「信頼」へと変えるための、全ての知識を解説します。
色の哲学:あなたの「目」は、絶対的な基準にはなれない
カラーキャリブレーションの重要性を理解するためには、まず、人間の「目」がいかに、主観的で、曖昧な感覚器であるかを知る必要があります。
私たちの目は、非常に優秀な適応能力を持っています。
例えば、少し黄色がかった照明の下で、白い紙を見ても、私たちの脳は、それを「白」として、自動で補正して認識します。
これは、日常生活においては便利な能力ですが、色を正確に評価する、という作業においては、致命的な弱点となります。
あなたのディスプレイが、もし、わずかに青みがかっていても、あなたの目は、数分もすれば、その色に順応してしまい、その画面上の白を、「正しい白」だと誤認し始めてしまうのです。
この状態で色調整を行えば、当然、そのデータは、客観的には、本来よりも黄色がかった、不正確なものになってしまいます。
したがって、真に正確な色再現を目指すのであれば、人間の主観的な感覚に頼るのではなく、機械的な、客観的な「目」によって、ディスプレイの色を測定し、そのズレを、ソフトウェア的に補正してあげる、という科学的なアプローチが、不可欠となるのです。
カラーキャリブレーションとは、この、人間と機械の、それぞれの長所を組み合わせた、ハイブリッドな色合わせの技術なのです。
第一章:ソフトウェアキャリブレーション - OS標準ツールによる簡易調整法
本格的な機材を導入する前に、まずは、お使いのOSに標準で搭載されている、簡易的なキャリブレーションツールを試してみましょう。
これは、あなた自身の「目」を基準に、画面の色味を調整していく方法です。
絶対的な精度は望めませんが、明らかに色がおかしい、といった場合の、応急処置としては、有効な手段です。
Windows 11の場合:「色の調整」(`dccw.exe`)
Windowsには、「色の調整」という、対話形式のキャリブレーションツールが、古くから搭載されています。
スタートメニューで「色の調整」と検索するか、「ファイル名を指定して実行」(`Win + R`)から、「`dccw`」と入力して起動します。
ウィザードの指示に従い、以下の項目を、あなたの目で見て、最も自然に見えるように、スライダーを調整していきます。
- ・ガンマの調整: 各円の中にある、小さな点が見えなくなるように、スライダーを調整します。これは、中間階調の明るさを定義する、重要なプロセスです。
- ・明るさとコントラストの調整: サンプル画像を見ながら、「シャツのXが見え、かつ、背景の壁との区別がかろうじてつく」明るさと、「シャツのしわやボタンが見える」コントラストに、ディスプレイ本体のボタンを使って調整します。
- ・カラーバランスの調整: グレーの濃淡バーに、余計な色味(赤、緑、青)が感じられなくなるように、RGBのスライダーを調整します。
全ての調整が完了すると、調整前と調整後の比較が表示され、結果は、新しい色のプロファイルとして保存されます。
macOSの場合:「ディスプレイキャリブレータ・アシスタント」
macOSにも、同様の機能が搭載されています。
「システム設定」>「ディスプレイ」を選択し、使用しているディスプレイのプリセットのプルダウンメニューから、「ディスプレイを調整...」を選択すると、キャリブレータ・アシスタントが起動します。
こちらも、基本的には、画面に表示される図形やサンプルを見ながら、あなたの目で見て、最も自然な状態になるように、設定を進めていきます。
ただし、これらの方法は、あくまで、あなたのその時の目の状態や、部屋の照明環境に大きく依存する、**主観的な調整**である、という限界を、決して忘れてはいけません。
第二章:ハードウェアキャリブレーション - 「測色器」による、客観的で正確な色調整
ここからが、写真家、デザイナー、映像作家といった、色の正確性を業務レベルで求める、全てのプロフェッショナルが実践する、本格的なキャリブレーションの領域です。
その主役は、「**キャリブレーター**」や「**測色器**」と呼ばれる、専用のハードウェアセンサーです。
キャリブレーターとは何か?
キャリブレーターとは、ディスプレイが実際に表示している色や明るさを、光学的に、そして極めて正確に測定するための、専用のセンサーデバイスです。
形状は様々ですが、多くは、マウスのような形状をしており、測定時には、センサー面をディスプレイに密着させて使用します。
この機械的な「目」は、人間の目のように、環境光や、その日の体調によって、その判断がぶれることはありません。
常に、客観的で、一貫性のある、数値に基づいた測定結果を提供してくれます。
ハードウェアキャリブレーションのプロセス
ハードウェアキャリブレーションは、キャリブレーターと、それに付属する専用のソフトウェアを組み合わせて行います。
その基本的な流れは、以下の通りです。
- 準備: ディスプレイを、最低でも30分以上ウォームアップさせ、安定した表示状態にします。また、キャリブレーションを行う部屋の照明は、実際に作業する時と同じ、一定の環境光の状態を保ちます。
- ソフトウェアの起動と目標設定: キャリブレーションソフトウェアを起動し、目標とする「白色点」「ガンマ」「輝度」といった、専門的なパラメータを設定します。(詳細は次章)
- センサーの設置: ソフトウェアの指示に従い、キャリブレーターのセンサー面を、画面に表示されたガイドの内側に、ぴったりと密着させて設置します。
- 自動測定の開始: 測定を開始すると、ソフトウェアは、画面上に、赤、緑、青、白、黒、そして様々な階調のグレーといった、一連の「カラーパッチ」を、順番に表示していきます。キャリブレーターは、その一つ一つの色が、目標値に対して、どれだけズレているかを、物理的に測定し、記録していきます。
- ICCプロファイルの生成と適用: 全ての色の測定が完了すると、ソフトウェアは、その測定結果(ディスプレイの色のクセ)を基に、そのズレを補正するための、特殊な変換データテーブル、すなわち「**ICCプロファイル**」を、自動で生成します。このICCプロファイルが、OSのカラーマネジメントシステムに適用されることで、以降、あなたのディスプレイは、常に、補正された、正確な色を表示するようになります。
第三章:目標値の理解 - 我々は何を「正しい色」とするのか
ハードウェアキャリブレーションを行う際には、我々が、どのような基準を「正しい色」として目指すのか、その「目標値」を、ソフトウェアに指示してあげる必要があります。
これらは、専門的ですが、非常に重要なパラメータです。
- ・白色点 (White Point): ディスプレイが表示する「白」の、色温度を定義します。一般的なWebコンテンツや、映像の制作・鑑賞では、自然な太陽光に近い「**D65(6500K)**」が、国際的な標準として広く使われています。一方、印刷業界では、印刷用紙の白さに合わせるため、「D50(5000K)」が、標準として用いられることが多いです。
- ・ガンマ (Gamma): 黒から白への、明るさの変化の度合い(階調特性)を定義するカーブです。これも、ほとんどのPC環境では、「**ガンマ 2.2**」が、事実上の標準となっています。
- ・輝度 (Luminance): ディスプレイの「明るさ」そのものです。単位は「cd/m²(カンデラ毎平方メートル)」で表されます。一般的なノートパソコンの最大輝度は300~500cd/m²程度ですが、これは、プロの写真編集など、色を厳密に評価する作業環境にとっては、明るすぎます。印刷物とのカラーマッチングなどを考慮する場合、一般的に「**80~120cd/m²**」程度の、比較的落ち着いた明るさを、目標値として設定します。
- ・色域 (Color Gamut): そのディスプレイが表示できる、色の範囲そのものです。一般的なディスプレイは、「**sRGB**」という、Webの標準規格を、ほぼ100%カバーするように作られています。より高性能な、クリエイター向けのディスプレイでは、さらに広い色の範囲を表現できる「**Adobe RGB**」や「**DCI-P3**」といった規格を、高いカバー率でサポートしています。キャリブレーションは、この、ディスプレイが物理的に持つ色域の範囲内で、その色表現の正確性を、最大限に高める作業です。
第四章:キャリブレーション後の世界 - 正しい色の維持と活用
一度、ハードウェアキャリブレーションを行えば、あなたのディスプレイは、客観的に「正しい色」を表示するようになります。
しかし、その状態を維持し、正しく活用するためには、いくつかの注意点があります。
まず、ディスプレイのバックライトや液晶は、時間と共に、僅かずつですが、その特性が変化(ドリフト)していきます。
そのため、プロフェッショナルの現場では、最低でも、月に一度の頻度で、定期的に再キャリブレーションを行い、常に、色の正確性を維持し続けることが、常識となっています。
また、生成されたICCプロファイルが、その真価を発揮するのは、Photoshop, Lightroom, Illustrator, DaVinci Resolveといった、「カラーマネジメントに対応した」アプリケーション上です。
これらのアプリケーションは、OSに適用されたICCプロファイルを正しく解釈し、色の変換を適切に行うことで、厳密なカラーワークフローを実現します。
あなたが、色にこだわるクリエイターであるならば、ハードウェアキャリブレーションは、もはや、特殊な作業ではなく、あなたの作品の品質を保証するための、必須の、そして日常的なプロセスとなるのです。
まとめ:カラーキャリブレーションとは、あなたの「作品」に、世界共通の「信頼」を与える行為である
ノートパソコンの画面キャリブレーションは、あなたの視覚体験を、主観的な「好み」の世界から、客観的な「正確性」の世界へと、引き上げるための、科学的なプロセスです。
特に、その成果物を、他者と共有し、あるいは、商業的な品質を求めるクリエイターにとって、それは、自身の作品に、世界中のどこでも、意図通りに再現されるという「普遍的な信頼性」を与えるための、不可欠な儀式と言えるでしょう。
- ・人間の目を過信しない: 私たちの目は、非常に優秀ですが、色の絶対的な基準にはなり得ません。客観的な色の正確性を求めるなら、機械の「目」が必要です。
- ・ソフトウェア調整は、あくまで応急処置: OS標準のキャリブレーションツールは、明らかな色被りを補正するには有効ですが、それは、あなたの主観に基づいた、近似値でしかありません。
- ・ハードウェアキャリブレーションこそが、唯一の正解: 専用の測色器(キャリブレーター)を使い、ディスプレイの「色のクセ」を科学的に測定し、ICCプロファイルで補正する。これこそが、プロフェッショナルが実践する、唯一無二の、真のカラーマネジメントです。
- ・目標値を意識する: あなたの成果物が、Webで消費されるのか、あるいは印刷されるのか。その最終的な出力先を意識し、白色点(D65)や輝度といった、適切な目標値を設定することが、より高いレベルでの色合わせを実現します。
あなたのノートパソコンの画面は、あなたの創造性が、世界へと出力される、最初の、そして最も重要な「窓」です。
ぜひ、その窓を、カラーキャリブレーションという技術で、一点の曇りもない、クリアで、そして「真実」を映し出す状態へと、磨き上げてください。
その先に、あなたの作品が、世界中の人々に、あなたの意図した通りの、本来の色彩で届く、という、クリエイターとしての、最高の喜びが待っています。

パソコン購入のためのお役立ち情報
パソコン選びがよく分からない方、ご不安のある方、悩む前に!お気軽にご相談ください!
専門スタッフが、性能・ご予算・お好みなどご希望に合ったパソコンをお探しします!



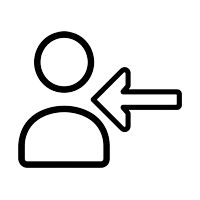 ログイン
ログイン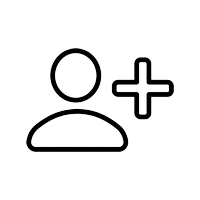 新しくアカウントを作成する
新しくアカウントを作成する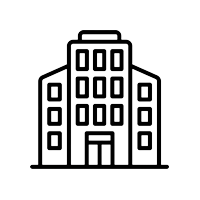 会社概要
会社概要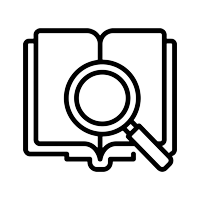 ご利用ガイド
ご利用ガイド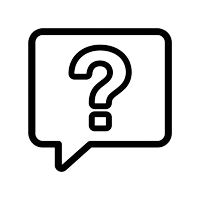 よくあるご質問
よくあるご質問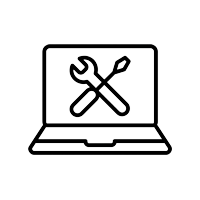 パソコン修理
パソコン修理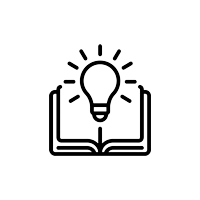 お役立ち情報
お役立ち情報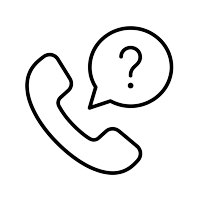 お問い合わせ
お問い合わせ 特定商取引に基づく表示
特定商取引に基づく表示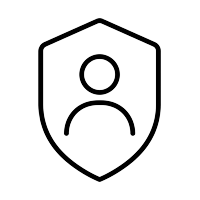 個人情報保護ポリシー
個人情報保護ポリシー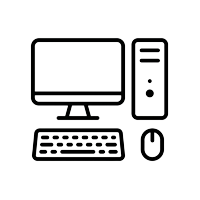 デスクトップパソコン
デスクトップパソコン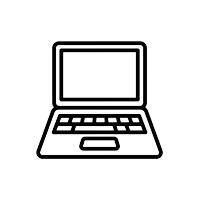 ノートパソコン
ノートパソコン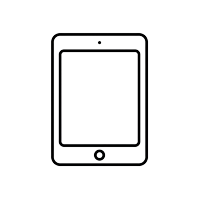 タブレット
タブレット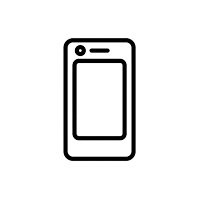 スマートフォン
スマートフォン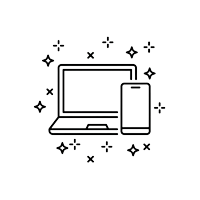 新品(Aランク)
新品(Aランク)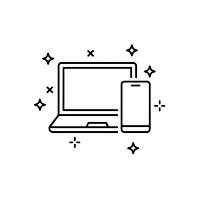 美品(Bランク)
美品(Bランク)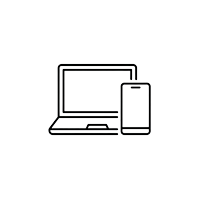 中古(Cランク)
中古(Cランク)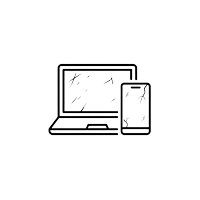 訳あり(Dランク)
訳あり(Dランク)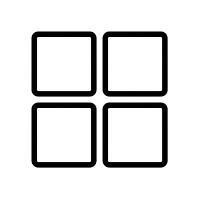 Windows 11
Windows 11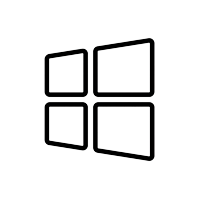 Windows 10
Windows 10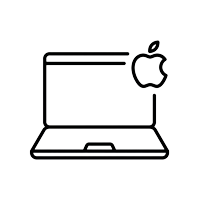 Mac OS
Mac OS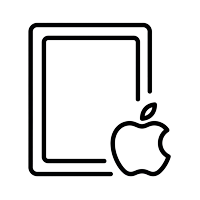 iPad OS
iPad OS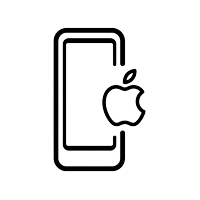 iOS
iOS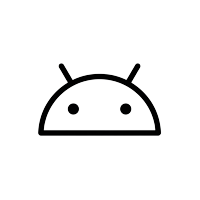 Android
Android コンシューマーモデル
コンシューマーモデル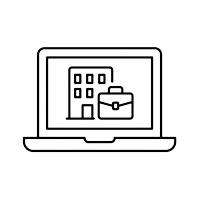 ビジネスモデル
ビジネスモデル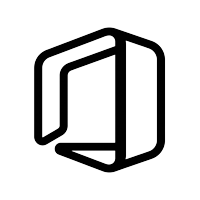 Microsoft Office搭載
Microsoft Office搭載 WPS Office搭載
WPS Office搭載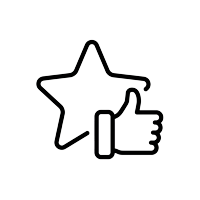 おすすめ商品
おすすめ商品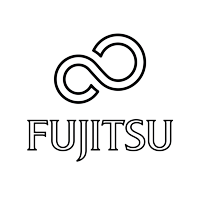
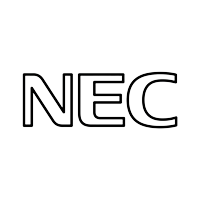
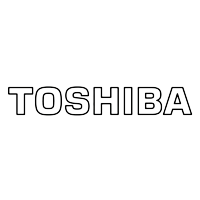


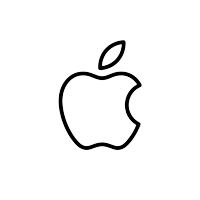


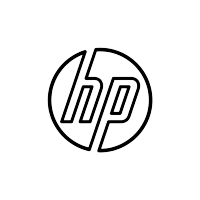
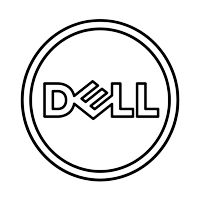

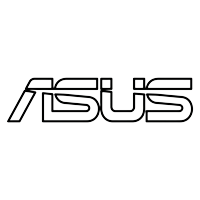
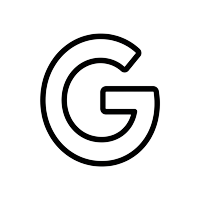

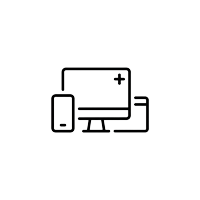
 Celeron|Athlon
Celeron|Athlon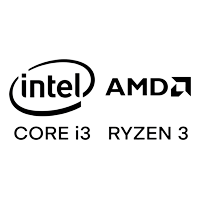 Core i3|Ryzen 3
Core i3|Ryzen 3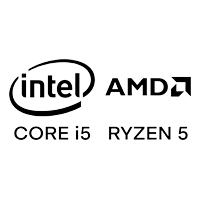 Core i5|Ryzen 5
Core i5|Ryzen 5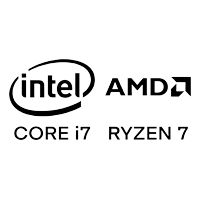 Core i7|Ryzen 7
Core i7|Ryzen 7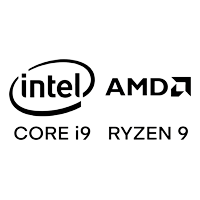 Core i9|Ryzen 9
Core i9|Ryzen 9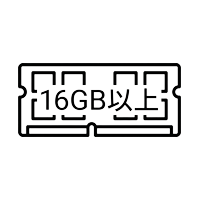 メモリ16GB以上
メモリ16GB以上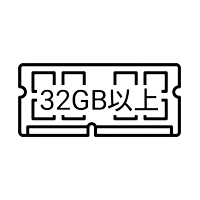 メモリ32GB以上
メモリ32GB以上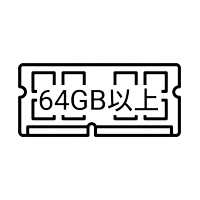 メモリ64GB以上
メモリ64GB以上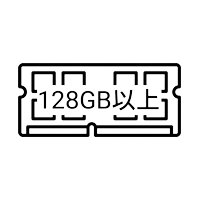 メモリ128GB以上
メモリ128GB以上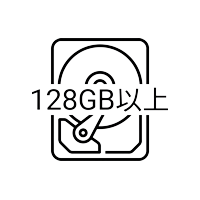 ストレージ128GB以上
ストレージ128GB以上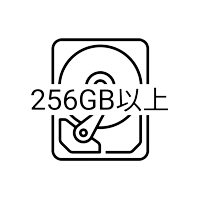 ストレージ256GB以上
ストレージ256GB以上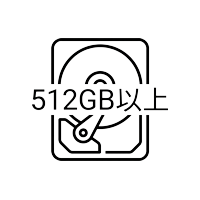 ストレージ512GB以上
ストレージ512GB以上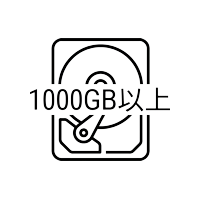 ストレージ1000GB以上
ストレージ1000GB以上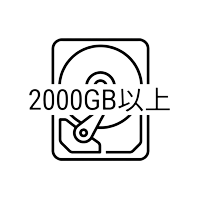 ストレージ2000GB以上
ストレージ2000GB以上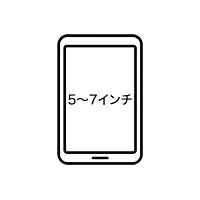 5〜7インチ
5〜7インチ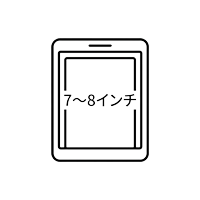 7〜8インチ
7〜8インチ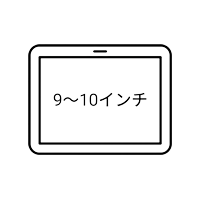 9〜10インチ
9〜10インチ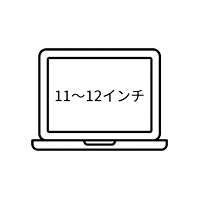 11〜12インチ
11〜12インチ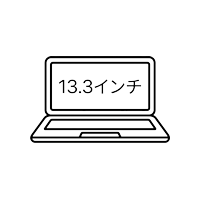 13.3インチ
13.3インチ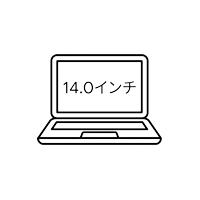 14.0インチ
14.0インチ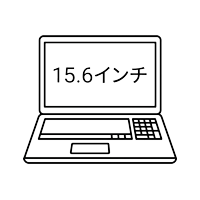 15.6インチ
15.6インチ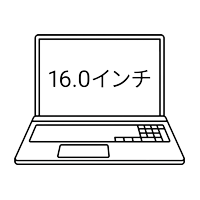 16.0インチ
16.0インチ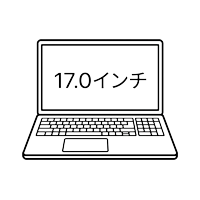 17.0インチ以上
17.0インチ以上




