
Macで複数ディスプレイを設定して作業スペースを広げる方法
MacOSのお役立ち情報

記事の最終更新日:2025年7月10日
仕事でMacBook Airを使っているのですが、Windowsの時のように、外部モニターをもう一台繋いで、作業スペースを広げたいんです。
でも、実際にモニターを繋いでみたら、2台目の外部モニターには、1台目と同じ画面が映るだけで、「拡張」することができませんでした。
友人に聞いたら、「そのMacのチップだと、外部モニターは1台までかも」と言われてしまって…。
本当なのでしょうか?
自分のMacが何台までモニターを繋げるのかを確認する方法や、もし制限がある場合に、それを回避してマルチディスプレイを実現するような、何か特別な方法はありませんか?
その問題こそ、現代のMacユーザーが直面する、最も重要で、そして最も誤解の多いテーマ、「Apple Siliconと外部ディスプレイの制限」です。
ご友人の言う通り、近年のApple Silicon搭載Macでは、内蔵されているチップの種類によって、接続できる外部ディスプレイの台数が厳密に定められています。
しかし、絶望する必要は全くありません。
その公式な制限を、ある特定の技術を使って「乗り越える」ための、非常に強力な解決策が存在するのです。
この記事では、まず、あなたのMacの心臓部であるチップの能力を正確に鑑定する方法から始め、公式な制限とその理由を解説します。
その上で、DisplayLinkという魔法のような技術を使い、公式にはサポートされていないはずの、2台、3台の外部ディスプレイ環境を構築するための、具体的で専門的な手順の全てを、あなたに伝授します。
あなたのMacの潜在能力を解放し、無限の作業空間を手に入れましょう。
マルチディスプレイの真価:それは脳の「外部メモリ」を増設する行為
複数のディスプレイを導入する最大のメリットは、単にデスクトップが物理的に広くなることではありません。
それは、人間の脳が一度に記憶し、処理できる情報量、いわゆる「ワーキングメモリ」の制約を、テクノロジーによって外部に拡張する行為です。
一方の画面に参考資料やコミュニケーションツールを常に表示させ、もう一方の画面でメインの作業に集中する。
この環境では、あなたはアプリケーションのウィンドウを切り替えたり、情報を記憶したりするために、貴重な認知資源(集中力)を浪費する必要がなくなります。
思考は中断されることなく、よりスムーズに、より深く、本来の創造的な作業へと没入していくことができます。
これは、あなたの生産性を文字通り倍増させる可能性を秘めた、最も費用対効果の高いワークスペースへの投資なのです。
第一章:最初の関門 - Apple Siliconの「ディスプレイ制限」という壁
Windowsの世界では、ほとんどのPCが比較的容易に複数の外部ディスプレイを接続できます。
しかし、Apple Siliconを搭載したMacの世界では、事情が大きく異なります。
接続可能な外部ディスプレイの最大数は、搭載されているチップの「グレード」によって、ハードウェアレベルで厳密に制限されています。
この事実を知らずにモニターを購入してしまうと、「繋いだのに映らない」という悲劇に見舞われることになります。
あなたのMacの「格」を知る:チップ別ディスプレイサポート数の階層
まず、画面左上のアップルメニュー()から「このMacについて」を選択し、「チップ」の項目を確認して、あなたのMacの心臓部がどのチップなのかを正確に把握してください。
その上で、以下の公式なサポート数を確認します。
- ・M1, M2, M3(無印チップ): MacBook Airや、下位モデルのMacBook Pro、iMacなどに搭載されているこれらの標準チップは、原則として**1台の外部ディスプレイ**しかサポートしません。(※Mac miniの無印チップ搭載モデルは例外的に2台までサポートします)
- ・M1 Pro, M2 Pro, M3 Proチップ: 上位モデルのMacBook Proなどに搭載。これらは、**最大2台の外部ディスプレイ**をサポートします。
- ・M1 Max, M2 Max, M3 Maxチップ: 最上位クラスのMacBook ProやMac Studioに搭載。これらは、**最大4台の外部ディスプレイ**という、非常に広大な作業空間の構築を可能にします。
- ・M1 Ultra, M2 Ultraチップ: Mac StudioやMac Proに搭載される、フラッグシップチップ。さらに多くのディスプレイを接続できます。
あなたのMacBook Airや、M3搭載のiMacで2台目の外部ディスプレイが拡張できなかったのは、このハードウェアレベルでの制限が原因なのです。
【究極の解決策】制限を乗り越えるDisplayLinkという魔法
では、無印Mシリーズチップを搭載したMacBookユーザーは、マルチディスプレイを諦めるしかないのでしょうか?
いいえ、その公式な制限を乗り越えるための、非常に強力なサードパーティ技術が存在します。
それが、「**DisplayLink(ディスプレイリンク)**」技術です。
DisplayLinkとは、映像信号を一度USB経由で伝送可能なデータに圧縮し、専用のチップを内蔵したアダプターやドッキングステーション側で、そのデータを映像信号に再変換してモニターに出力する、という仕組みです。
これは、Mac本体のGPUが持つネイティブな映像出力機能(の制限)を、完全にバイパスするアプローチです。
DisplayLink対応のドッキングステーションやUSBアダプターを使用し、Macに専用のドライバーソフトウェアをインストールすることで、公式には1台しかサポートされていないはずのMacBook Airでも、2台、3台といった、複数の外部ディスプレイを「拡張モード」で利用することが可能になります。
ただし、この技術には、映像を圧縮・展開するプロセスが介在するため、超高フレームレートのゲームや、厳密な色管理が求められるプロの映像編集などには不向きな場合があります。
しかし、Webブラウジング、Officeアプリケーション、プログラミングといった、一般的なビジネスユースにおいては、そのデメリットをほとんど感じることはないでしょう。
DisplayLinkは、多くのMacBookユーザーにとって、マルチディスプレイ環境を実現するための、まさに「救世主」と言える技術なのです。
第二章:物理的な接続 - ポート、ケーブル、そしてドックの選定
お使いのMacの能力と、それを拡張する方法を理解したら、次は物理的な接続の段階です。
近年のMacのポートは、非常にシンプルですが、その分、正しいケーブルやハブの選定が重要になります。
【Thunderbolt / USB4ポート】
楕円形のUSB-Cコネクタを持つ、このポートが、近年のMacにおける全ての接続のハブとなります。
このポートは、超高速なデータ転送(Thunderbolt)、映像出力(DisplayPort Alternate Mode)、そしてPC本体への給電(USB Power Delivery)といった、複数の役割を兼ね備えています。
外部モニターに直接USB-Cケーブルで接続するか、あるいは、USB-CからHDMIやDisplayPortへと変換するアダプターやケーブルを使って接続するのが基本です。
【ドッキングステーションの活用】
複数のディスプレイや、その他の多くの周辺機器(キーボード、マウス、外付けドライブ、有線LANなど)をスマートに接続するには、良質なドッキングステーションへの投資が、結果的に最も快適な環境を構築します。
ケーブル一本をMacに接続するだけで、デスクトップPCのような、完全なワークステーション環境が瞬時に現れるのです。
そして、前述のDisplayLink技術を利用したい場合は、必ず「DisplayLink認定」と明記されたドッキングステーションを選ぶ必要があります。
第三章:ソフトウェアの設定 - macOSをマルチディスプレイ環境に最適化する
ハードウェアの接続が完了したら、macOSに、その新しい広大な作業空間を、あなたの意図通りに認識・制御させるための設定を行います。
全ての操作は、「システム設定」>「ディスプレイ」のパネルで行います。
ディスプレイの「配置」:物理的世界とデジタル世界の同期
複数のディスプレイが認識されると、この設定パネルに、それぞれのディスプレイを表す青い四角のアイコンが複数表示されます。
まず、「識別」ボタンを押して、どちらのアイコンが、物理的にどちらのモニターに対応しているかを確認します。
次に、このアイコンをドラッグ&ドロップし、実際のモニターの物理的な配置(例:MacBook本体が中央下、右側に大型モニター、左側に縦置きモニター)と、完全に一致するように並べ替えます。
この「配置」作業が、モニター間をマウスカーソルがスムーズに行き来できるかどうかを決定する、最も重要なステップです。
モニターの上下位置も、できるだけぴったりと合わせることで、カーソル移動の違和感がなくなります。
メインディスプレイの指定と表示モード
白いメニューバーが表示されているディスプレイが、現在の「メインディスプレイ」です。
このメニューバーを、別のディスプレイのアイコンにドラッグ&ドロップすることで、メインディスプレイを変更できます。
メインディスプレイは、通知が表示されたり、アプリケーションが最初に開かれたりする、中心的な役割を果たします。
また、「用途」のプルダウンメニューから、各ディスプレイを「拡張ディスプレイ」として使うか、「ミラーリング」として使うかを選択できます。
作業空間を広げることが目的ですので、ここは必ず「拡張ディスプレイ」を選択します。
第四章:Appleエコシステムの真価 - Sidecarとユニバーサルコントロール
もしあなたがiPadも所有しているなら、Appleのエコシステムは、さらに魔法のような拡張性を提供してくれます。
【Sidecar:iPadを第二のディスプレイに】
Sidecarは、あなたのiPadを、Macのワイヤレス(または有線)なサブディスプレイとして利用できる機能です。
特別な設定はほとんど不要で、コントロールセンターから簡単に接続できます。
これにより、外出先のカフェなどでも、即席のデュアルモニター環境を構築できます。
Apple Pencilを使えば、iPad側を液晶タブレットのように使うことも可能です。
【ユニバーサルコントロール:ディスプレイ拡張との違い】
ユニバーサルコントロールは、Sidecarとしばしば混同されますが、その目的は全く異なります。
これは、ディスプレイを「拡張」するのではなく、一つのキーボードとマウス(トラックパッド)で、MacとiPadの両方を、シームレスに「操作」できるようにする機能です。
マウスカーソルをMacの画面の端から、そのまま隣のiPadの画面へと移動させ、iPadのアプリを操作し、さらにはMacとiPad間でファイルをドラッグ&ドロップすることさえ可能です。
これは、複数のAppleデバイスを同時に使う際の、操作の壁を取り払う、革新的な機能です。
第五章:パワーユーザーの流儀 - 複数ウィンドウの効率的な管理
広大なデスクトップ空間を手に入れても、ウィンドウの配置が乱雑では、その真価を発揮できません。
Mission ControlやSpaces(仮想デスクトップ)といったmacOSの標準機能を使いこなし、「このアプリは、必ずディスプレイ2で開く」といった設定をすることで、常に整理された作業環境を維持できます。
さらに、より高度なウィンドウ管理を求めるなら、サードパーティ製のウィンドウマネージャーアプリ(※注釈:MagnetやRectangleといった名前で知られる種類のアプリ)の導入を検討するのも良いでしょう。
これらのツールは、キーボードショートカット一発で、ウィンドウを指定した位置やサイズ(例:画面左半分、右上4分の1)に整然と配置する機能を提供し、マルチモニター環境下での作業効率を、さらに一段階上のレベルへと引き上げてくれます。
まとめ:マルチディスプレイとは、思考の速度に、作業環境を同期させる技術である
Macでのマルチディスプレイ環境構築は、単に画面を増やす行為ではありません。
それは、あなたの思考が、アプリケーションの切り替えやウィンドウの再配置といった、些末な雑務によって中断されるのを防ぎ、真に創造的なタスクへと集中するための、最強の環境投資です。
- ・まず、汝のMacを知れ: あなたのMacに搭載されたApple Siliconチップが、公式に何台の外部ディスプレイをサポートするのか。その「格」を知ることが、全ての戦略の出発点です。
- ・制限は、乗り越えるためにある: 無印Mシリーズチップの「外部ディスプレイは1台まで」という制限は、DisplayLink技術を搭載したドッキングステーションやアダプターを導入することで、安全に、そして確実に突破できます。
- ・物理とデジタルを同期させる: 「ディスプレイの配置」設定で、モニターの物理的なレイアウトと、macOSが認識するデジタルなレイアウトを完璧に一致させる。この一手間が、日々のストレスを激減させます。
- ・エコシステムを最大限に活用する: iPadを第二の画面にする「Sidecar」や、複数のデバイスを自在に操る「ユニバーサルコントロール」。Appleエコシステムの真価は、こうしたシームレスな連携にこそあります。
たった一枚の外部ディスプレイを追加するだけで、あなたの作業効率と、仕事の質は、驚くほど向上する可能性があります。
この記事を元に、ぜひあなただけの、広大で、快適で、そしてこの上なく生産的な、デジタルな書斎を構築してください。

パソコン購入のためのお役立ち情報
パソコン選びがよく分からない方、ご不安のある方、悩む前に!お気軽にご相談ください!
専門スタッフが、性能・ご予算・お好みなどご希望に合ったパソコンをお探しします!



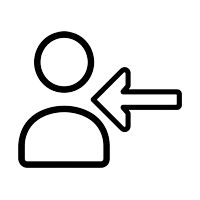 ログイン
ログイン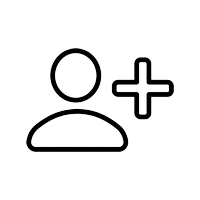 新しくアカウントを作成する
新しくアカウントを作成する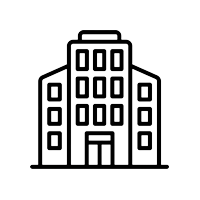 会社概要
会社概要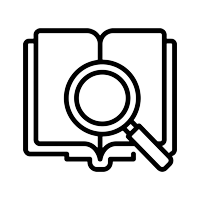 ご利用ガイド
ご利用ガイド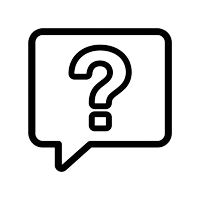 よくあるご質問
よくあるご質問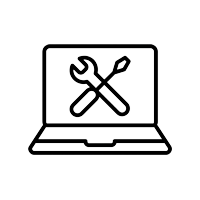 パソコン修理
パソコン修理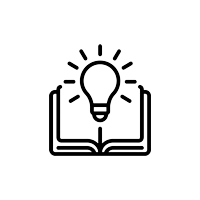 お役立ち情報
お役立ち情報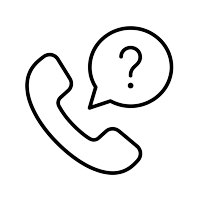 お問い合わせ
お問い合わせ 特定商取引に基づく表示
特定商取引に基づく表示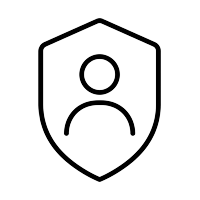 個人情報保護ポリシー
個人情報保護ポリシー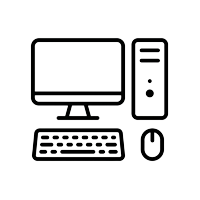 デスクトップパソコン
デスクトップパソコン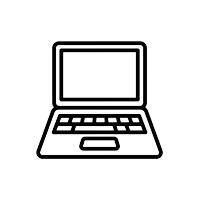 ノートパソコン
ノートパソコン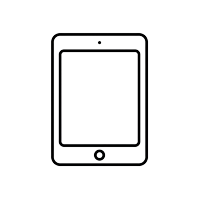 タブレット
タブレット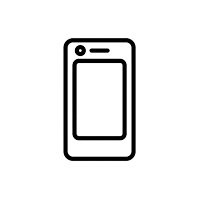 スマートフォン
スマートフォン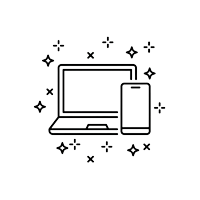 新品(Aランク)
新品(Aランク)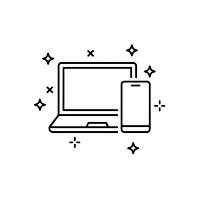 美品(Bランク)
美品(Bランク)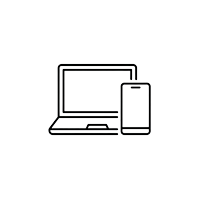 中古(Cランク)
中古(Cランク)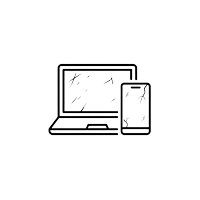 訳あり(Dランク)
訳あり(Dランク)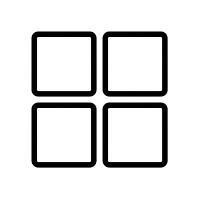 Windows 11
Windows 11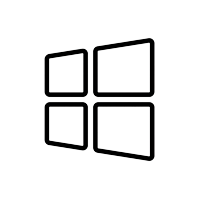 Windows 10
Windows 10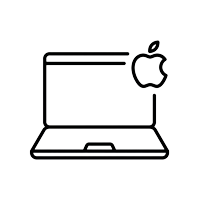 Mac OS
Mac OS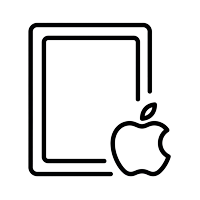 iPad OS
iPad OS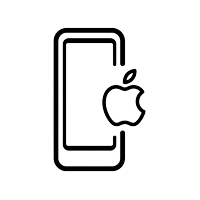 iOS
iOS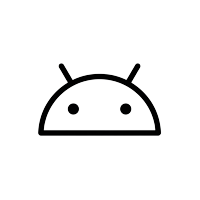 Android
Android コンシューマーモデル
コンシューマーモデル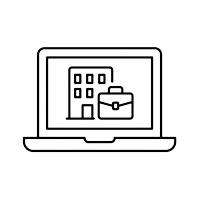 ビジネスモデル
ビジネスモデル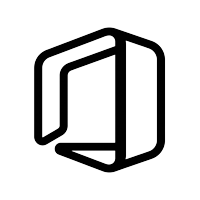 Microsoft Office搭載
Microsoft Office搭載 WPS Office搭載
WPS Office搭載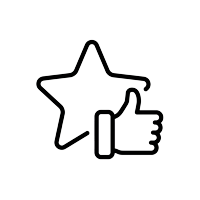 おすすめ商品
おすすめ商品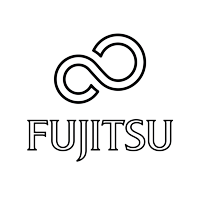
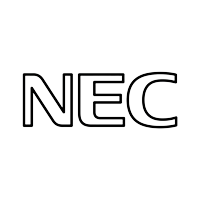
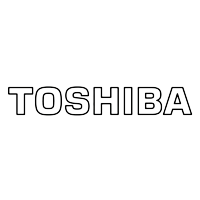


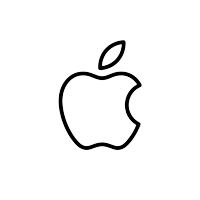


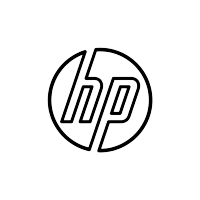
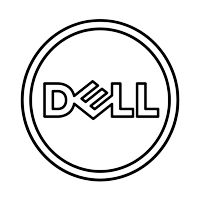

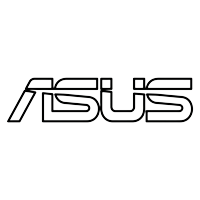
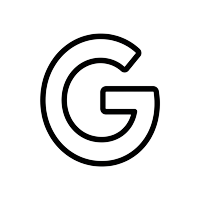

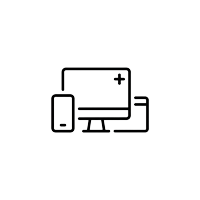
 Celeron|Athlon
Celeron|Athlon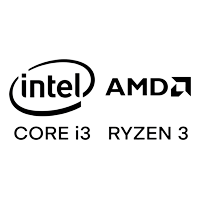 Core i3|Ryzen 3
Core i3|Ryzen 3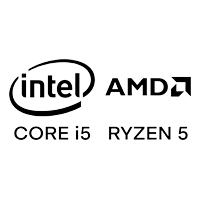 Core i5|Ryzen 5
Core i5|Ryzen 5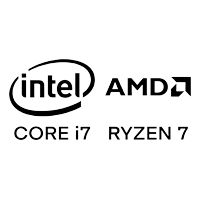 Core i7|Ryzen 7
Core i7|Ryzen 7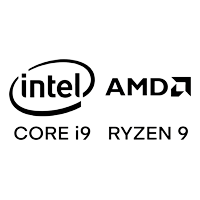 Core i9|Ryzen 9
Core i9|Ryzen 9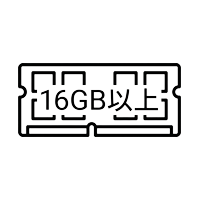 メモリ16GB以上
メモリ16GB以上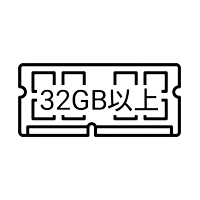 メモリ32GB以上
メモリ32GB以上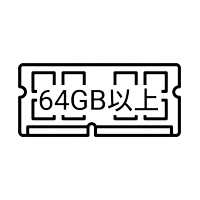 メモリ64GB以上
メモリ64GB以上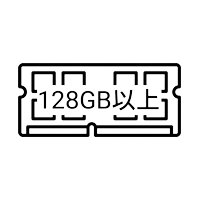 メモリ128GB以上
メモリ128GB以上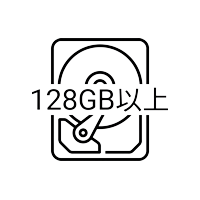 ストレージ128GB以上
ストレージ128GB以上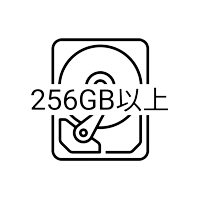 ストレージ256GB以上
ストレージ256GB以上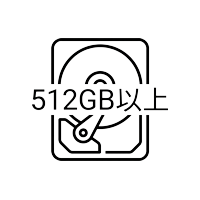 ストレージ512GB以上
ストレージ512GB以上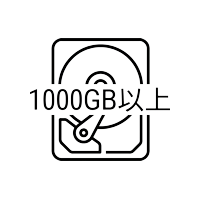 ストレージ1000GB以上
ストレージ1000GB以上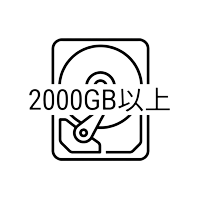 ストレージ2000GB以上
ストレージ2000GB以上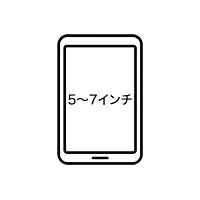 5〜7インチ
5〜7インチ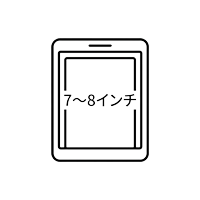 7〜8インチ
7〜8インチ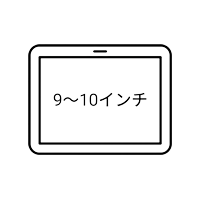 9〜10インチ
9〜10インチ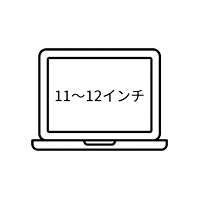 11〜12インチ
11〜12インチ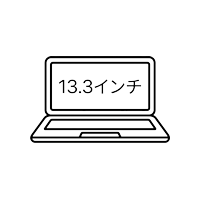 13.3インチ
13.3インチ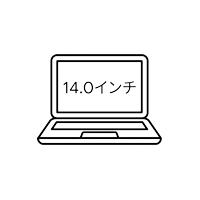 14.0インチ
14.0インチ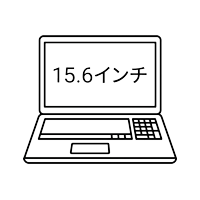 15.6インチ
15.6インチ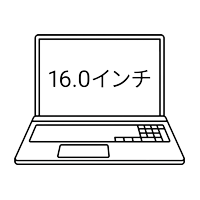 16.0インチ
16.0インチ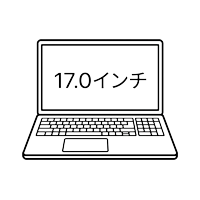 17.0インチ以上
17.0インチ以上




